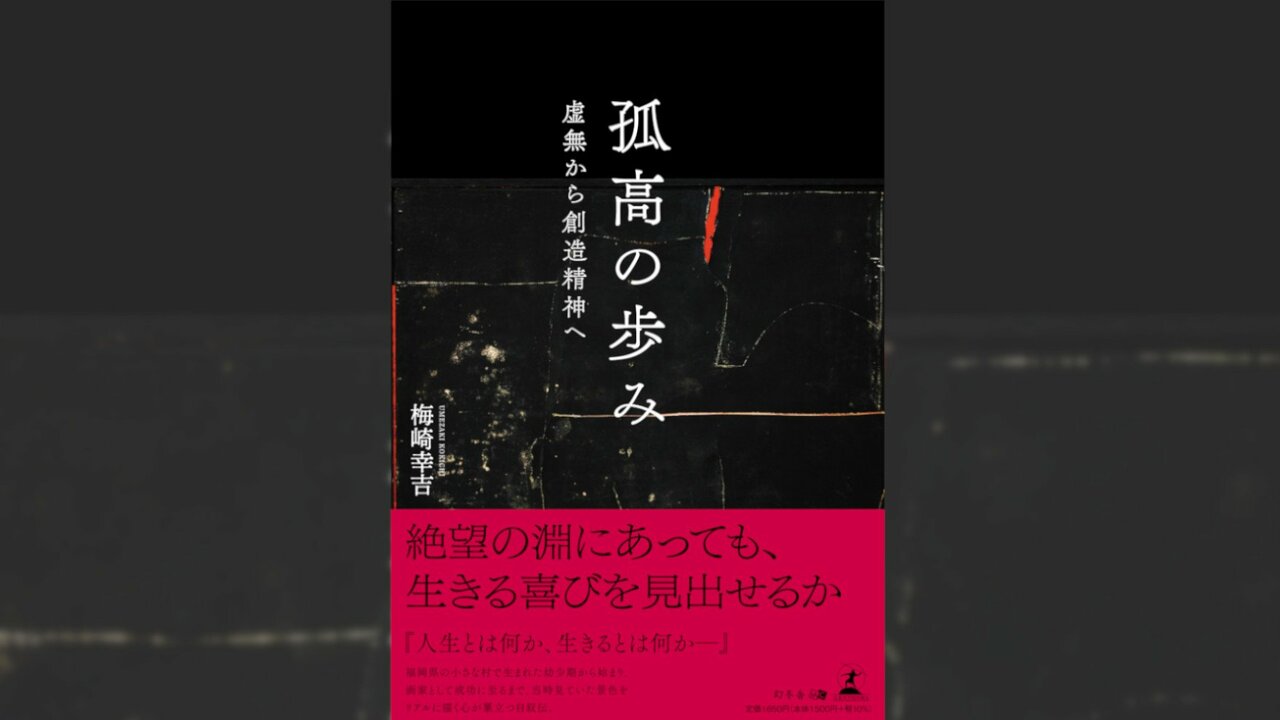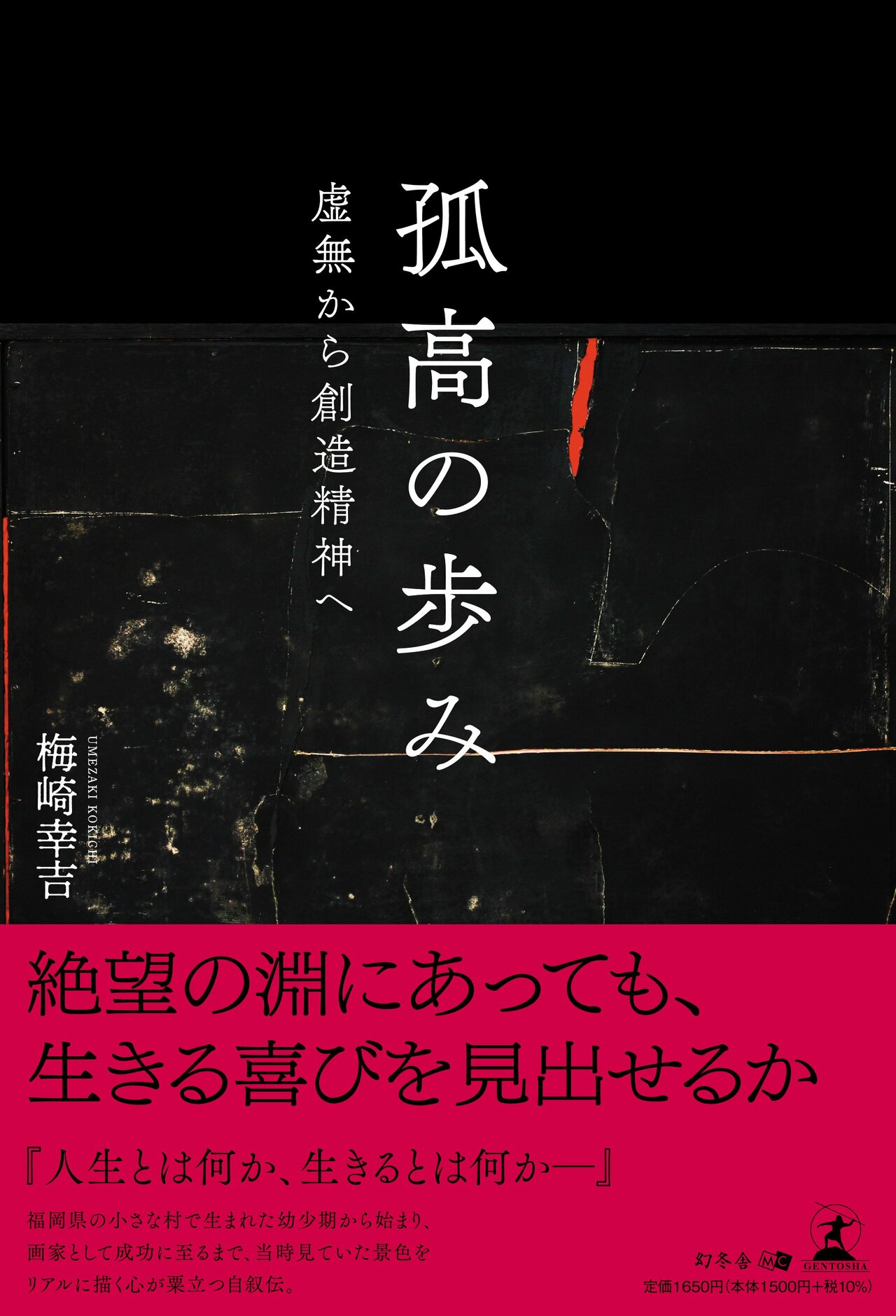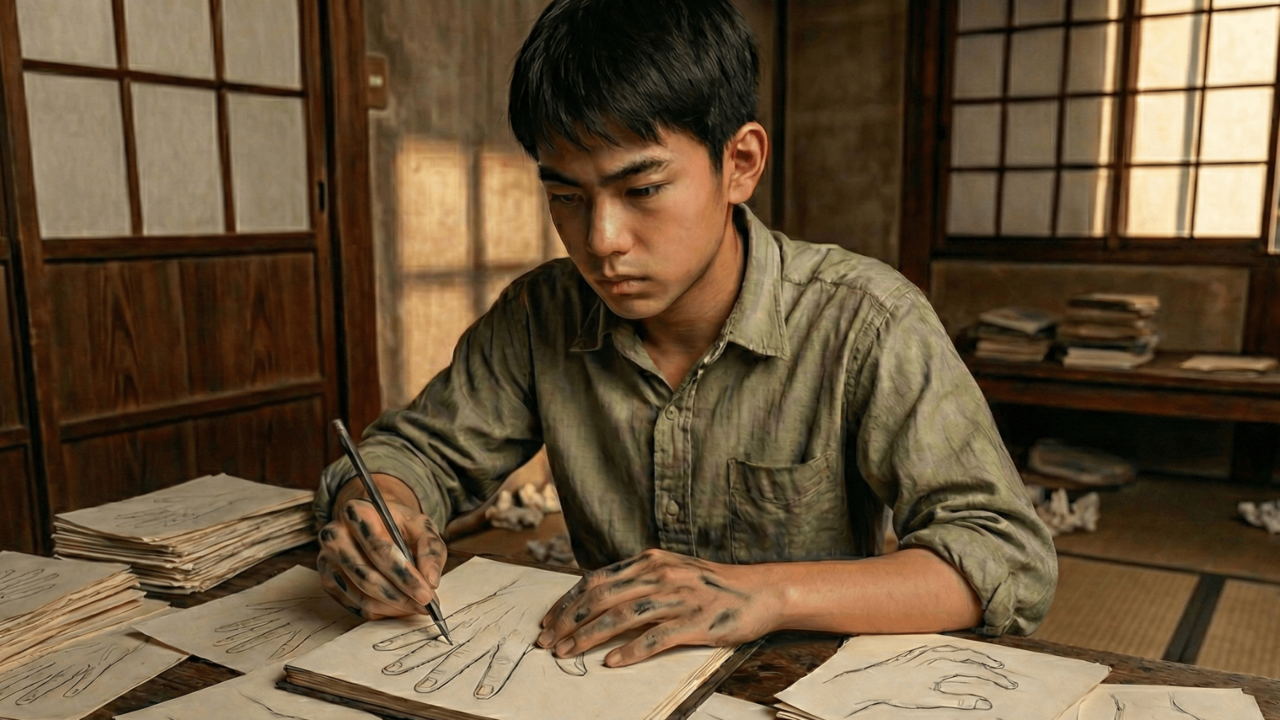【前回の記事を読む】氷が張っている池にも平気で入ってしまう。その常軌を逸した行動に、私は感動した。彼は、今で言う知的障がい者だった。
一、
近代以降の文学者、詩人達が謳(うた)った孤独は、私にとっては日常的意識であった。根本的な違いは、私にはそれが生来の素質としてあったということである。
私には、孤独は敢えて言葉にして言うほどのことではなかった。孤独とは社会生活における人間関係性の欠如、喪失の自覚化にほかならぬ。近代の心理学、哲学者の考察分析などは私の日常的なものであった。
ただ、専門的な概念的言葉を私が知らなかっただけである。文学者の苦悩も孤独も、彼等は人間社会という既知の幻想に囚われて、その実体を知った時の観念的自覚、生存自体の不条理、無意味であるというなかでの「あがき」の姿であった。東洋の無常観も、西洋の無知の知も単に言い方の違いにすぎない。
近代人の悲喜劇は相対的意識が観念化、自覚され虚無的世界観となり、それを自覚したことが人生の方向性の喪失となったことに起因する。私の子供時代は、その近代人の悲劇的虚無的観念が日常的な感覚的知覚であった。
私の父は五尺(約151 ・5センチ)の身長であった。
子供の頃から働いていたせいか、がっちりした筋肉質の体格であった。腕の力こぶを作って、その部分をぽんと叩くとぷくっとふくれるのをよく見せてくれた。
父は三度名字が変わっていた。離婚と同時に前の梅崎になった。その前は河村と言ったそうである。
父から、祖父はある時に突然狂ってしまったと聞いていた。父はその時の状況を詳しく話してくれた。
祖父は佐世保の下駄問屋の仕事をしていた家に生まれた。若い頃は相当遊んだらしい。祖父の仕事は卸した下駄屋の集金であったという。その集金した金をいつも遊興費に使い果たしていたらしく、それで勘当された。
父が子供の時、祖父は天秤棒を担いで行商していた。父はよく祖父の後をついてまわっていたという。ある日、家に帰る途中のことである。道の真ん中に「大きい石があって通れない!」と祖父が言った。父が見ても道には何もない、その時に祖父の担いでいた天秤棒が二つに音をたてて折れたという。
祖父は、何かに怯えるように自分の家とは反対のほうに追われるように走っていった。その時、父はまだ五歳くらいだったと聞いた。父は何だか恐くなって家に戻った。
その後、祖父は一ヶ月以上もかかって実家に戻ったが、その時の様子はまるで乞食のような格好で疲労困憊していて、実家に着くとそのまま寝込み死んでしまったらしい。
父は祖父の異様で狂った時の様子を何度も「あん時は恐かった。天秤棒がぼきっと折れた、あんな太か棒が」と言いながら、見えない大きな石を見つめる祖父の恐怖の様子を身振り手振りで話してくれた。
父はよほど恐かったらしい。話す時の様子でそれはよく伝わった。自分が神経を病んだのも、祖父の血を引いているからだと思ったようである。