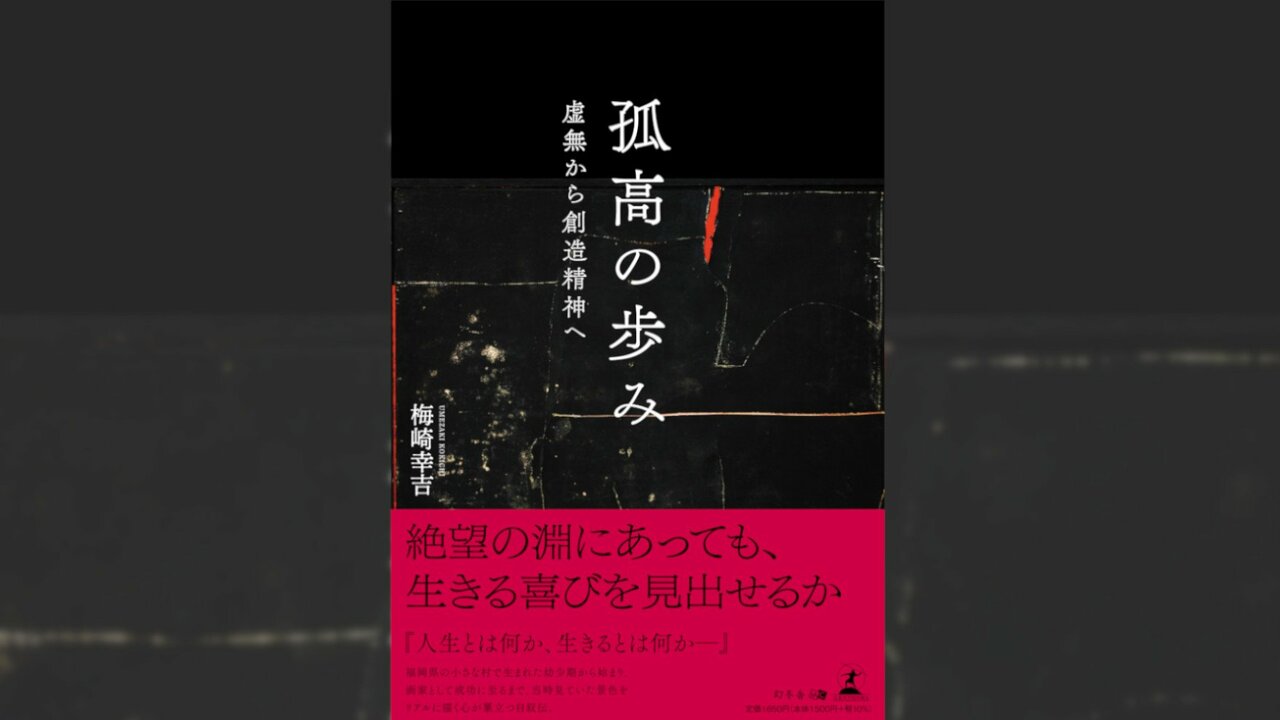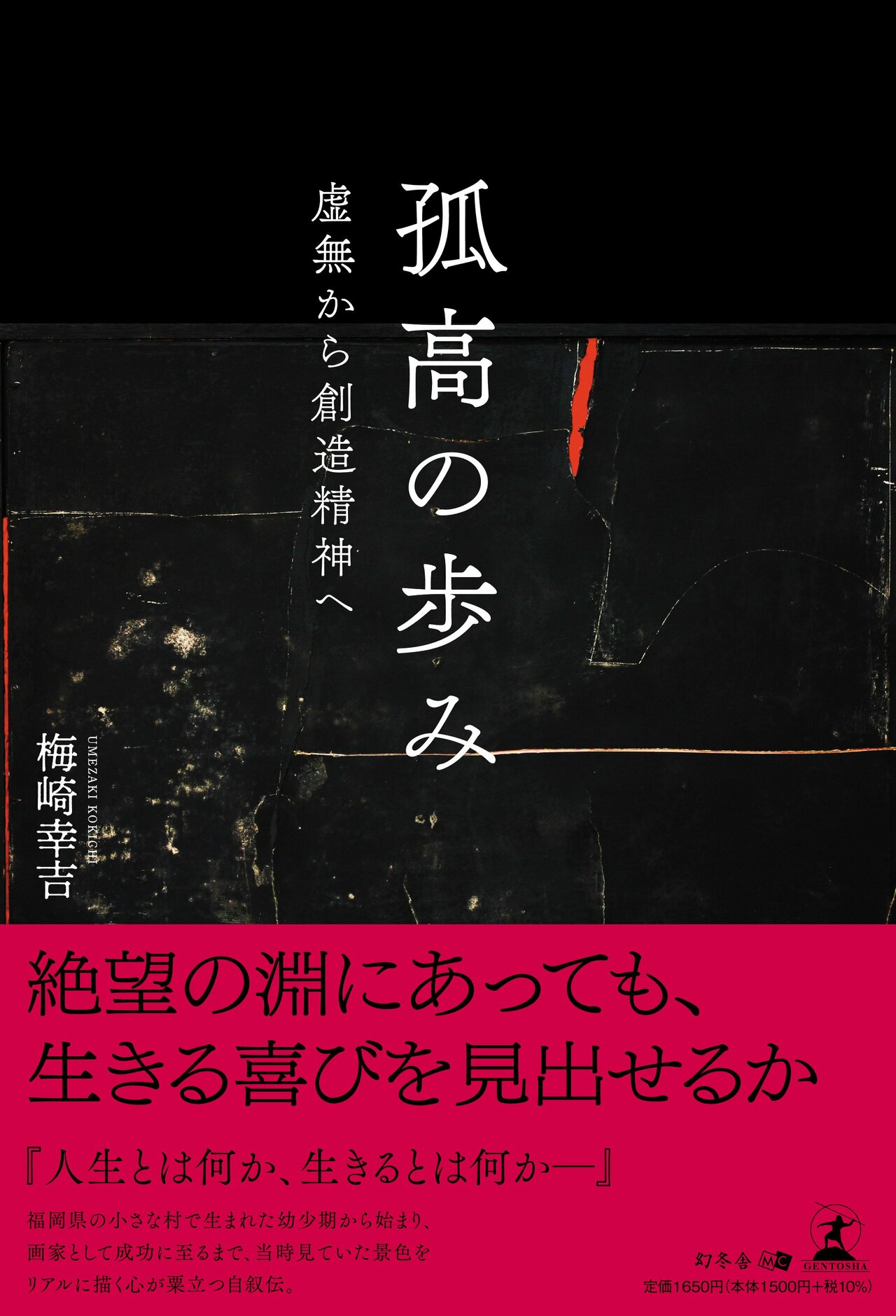【前回の記事を読む】「あなたには、まだおかあさんの気持ちは分からないのよ。人生には色々あるのよ」くだらない言い訳に辟易していた子供時代
一、
当然だが皆に睨まれて叱られた。だが、それでも私はおかしさをこらえて下を向いていた。兄は私と違って大声で泣いていた。
私の嫌いなものに坊主がいた。命の尊さを説く坊主が平気でよく他の命を食べていられるな、と思った。私にとって宗教も権威の一つにすぎない。まことしやかに命の尊さを説く坊主の頭を後ろからひっぱたいたらさぞ怒ることであろう。坊主の頭も木魚も同じ形に見えた。
宗教家は断じて無償ではない。お金を払わなければ何もしない。商人とどこも違わない。目に見えない教義を用いて金で売っている。詐欺師とたいして変わらない。私は子供の時にそう思っていたのである。
墓掘の男達も金で動く。学校の先生も、坊主もみんな金だ。私は無償で活動し、生きている人間を知らなかった。この考えは私が成長しても簡単には変化しなかった。
私の目から見れば、同世代の子供は全てが幼稚であった。学校の先生も人の良い人はいたが、私から見れば、化粧をし、衣装を着飾った者にしか見えない。きつい言い方だが、人が良いとは愚鈍の異名にすぎぬ。
私の人間に対する考えは、私の生来の素質と村人の悪意の差別を通してしたたかに鍛えられた。尤も、村人達にとっては自分達の生活習慣や縄張り意識、異物に対する排除が自分達を守る苦肉の策であったのであろう。
それは弱者である各個人が自分を守るための、したたかな知恵である。しかし、単に無知であることから生み出された姑息な知恵と私は理解した。彼らはその世界で一生を終えていくのだろう。彼らの生き方には私は何の興味もなかったし、私の関与することでもない。
私は、自分の不快な環境からは脱したかったが、それには私はまだ幼すぎただけである。
私を感動させるものは稲妻だけであった。稲妻が走ると私は外に出てよく見とれていた。
当時、私がどうしても友人になりたかった子供がいた。彼は、今で言う知的障がい者であった。しかし、当時の私は、そのことを理解できなかった。氷が張っている池や沼にも裸で平気で入ってしまう。その常軌を逸した行動は、私を感動させたのである。
彼は、私に唯一感動を与えた希有な存在であった。私は彼を自分に振り向かせるためにいろいろな手段を使った。彼は私を一瞬は見るが、次の瞬間には見ていない。私は、彼が見ているものを見たかった。