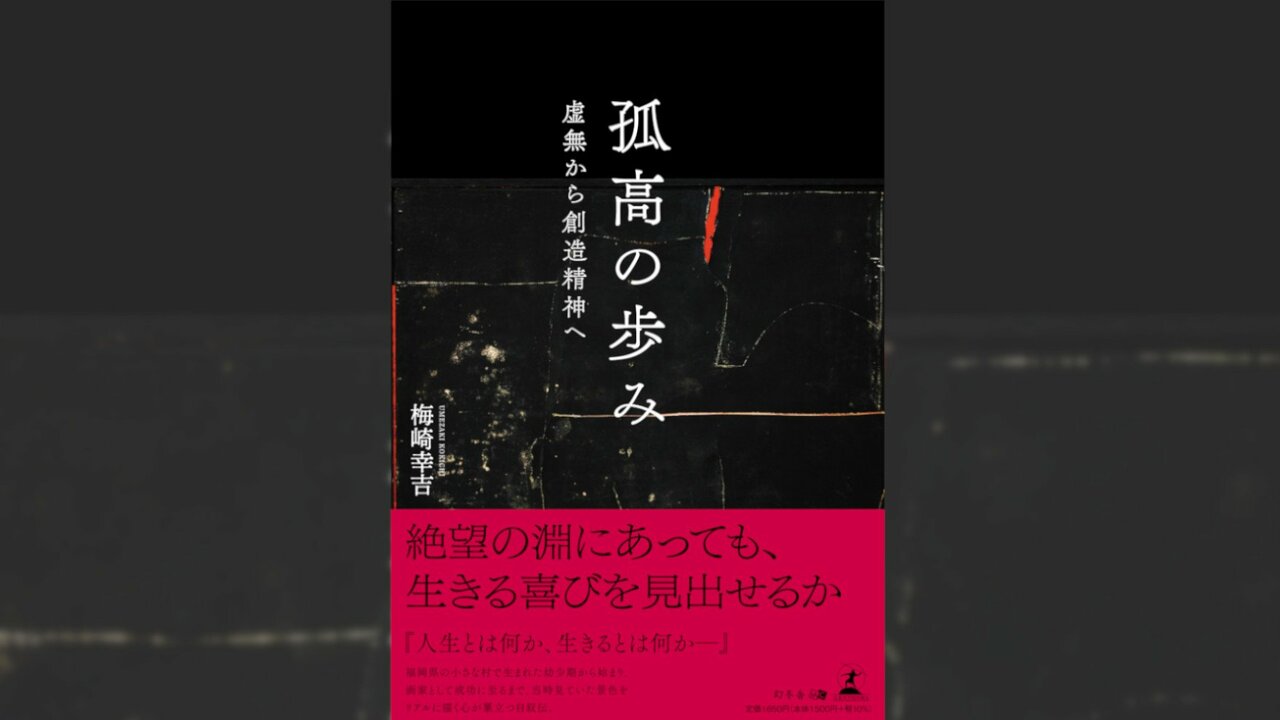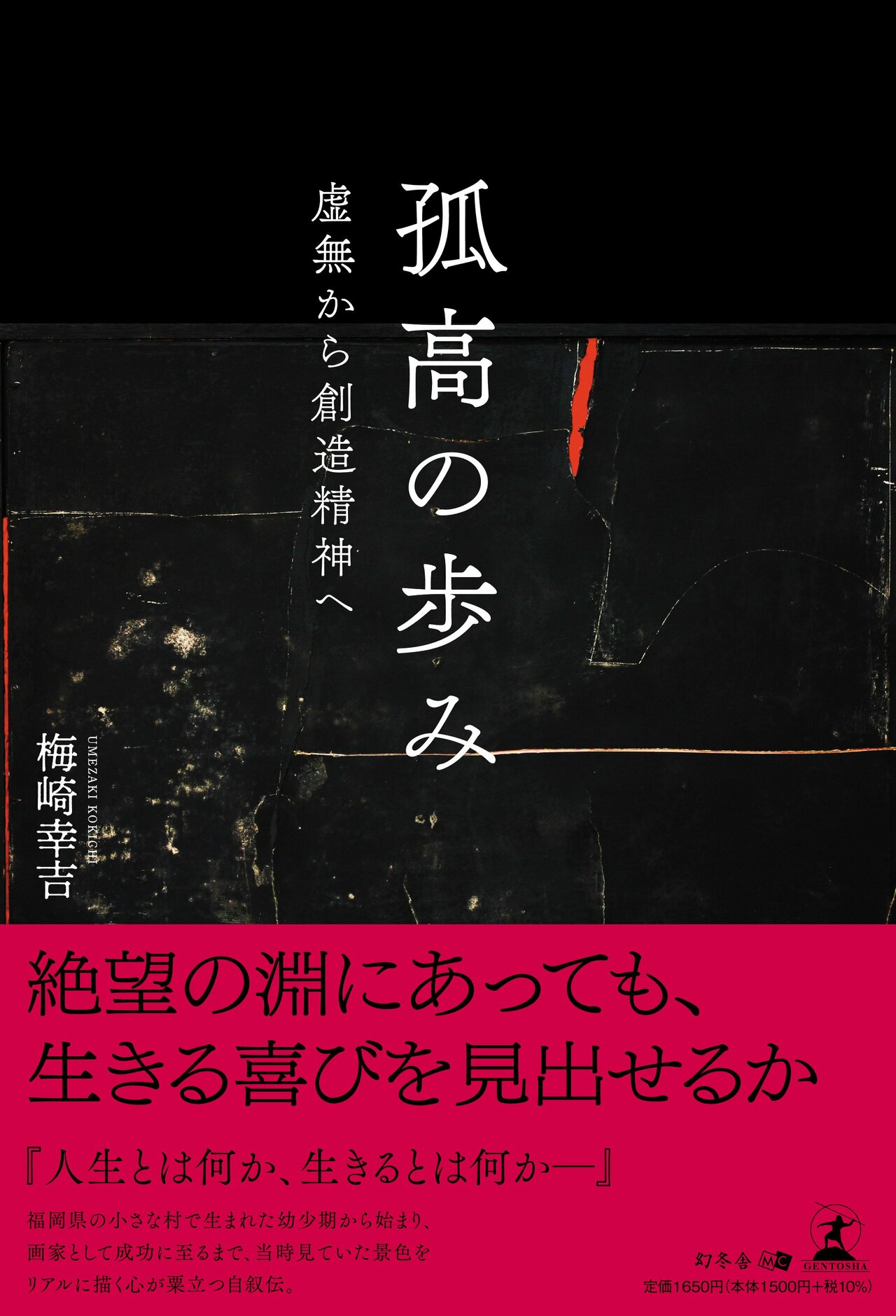【前回の記事を読む】学校から帰ると離れ離れになったはずのクロが飛びついてきた。私は嬉しかったが、口の周りは傷つき、血が滲んでおり...
一、
私は、意識、無意識で非難していた薄汚い人間達の一人であることを犬のクロによって思い知らされた。だが、私はそんな自分自身をどう扱えばよいのか、ただ何もできない無力な自分をもてあますことしかできないまま、一日、一日と時は過ぎていった。
私の内で何かが変化した。ただ、それを当時は意識化はできず、さらに私の虚無感は深まった。
それでも私は生きている。私は田んぼのあぜ道を通りながら、初夏の日差しに照らされた稲穂のまぶしい新緑の風景の中を歩いている。蛙やバッタ、様々な生き物が私の周りにいる。この蛙や虫達も、私もまだ生きている。何の理由があって生きているのかも分からずに命が命を食い、その命をまた他の命が食い……。
ふいに私は一匹のヘビが蛙を頭から飲み込んでいる所に出くわした。まだヘビの口から蛙の足が出ている。以前の私はヘビが蛙を飲み込んでいたら棒で叩いて蛙を助けていた。私はその光景を一瞬立ち止まって見ていたが、この時はその場を逃げるように速足で遠ざかった。
預けられている家に着くと、よたよたと私に近づいてくる黒い犬がいる。クロであった。
クロの首輪から鉄のクサリがぢゃらぢゃらと音をたてて、その三メートルくらい先には三十センチほどの鉄の杭が付いている。クロは杭ごと引き抜いてきたのである。クサリは噛みきれなかったのであろう、クロは何度も噛み、それで今度は地中に打ち込まれた杭を噛んだりして抜いたのである。それで口の周りも首の周りも血だらけになった。
クロはしゃがれた声で私に向かって嬉しそうに鳴いている。足も痛めて走れないようである。私はクロの傷口を井戸のきれいな水で洗った。私に会うため、クロは鉄のクサリを噛み、杭を抜くのに必死であっただろう。全身で杭を引っ張り、噛み、抜けばまた私に会える─。
私に会うためには足が傷つこうが、首が裂けようが歯が折れようが何ともなかったのであろう。一番自分を可愛がっているこの私に会えるのだから。私はただ泣くしかなかった。泣いても無駄なのに。私はただクロの一途さに胸が押しつぶされ、苦しくて、悲しくて泣くことしかできない、怒りや悔しさやら何もかもが混ざり、言い知れぬ哀しみに襲われていた。
クロが来た夕方にまた、老夫婦は来た。前回と同じく自分の子が悪いことでもしたかのように何度も頭を下げていた。帰る時に私を見る老夫婦の眼差しには何ともいえぬ悲しみがあった。
私はこの時に、二度と犬は飼うまいと強く決意した。