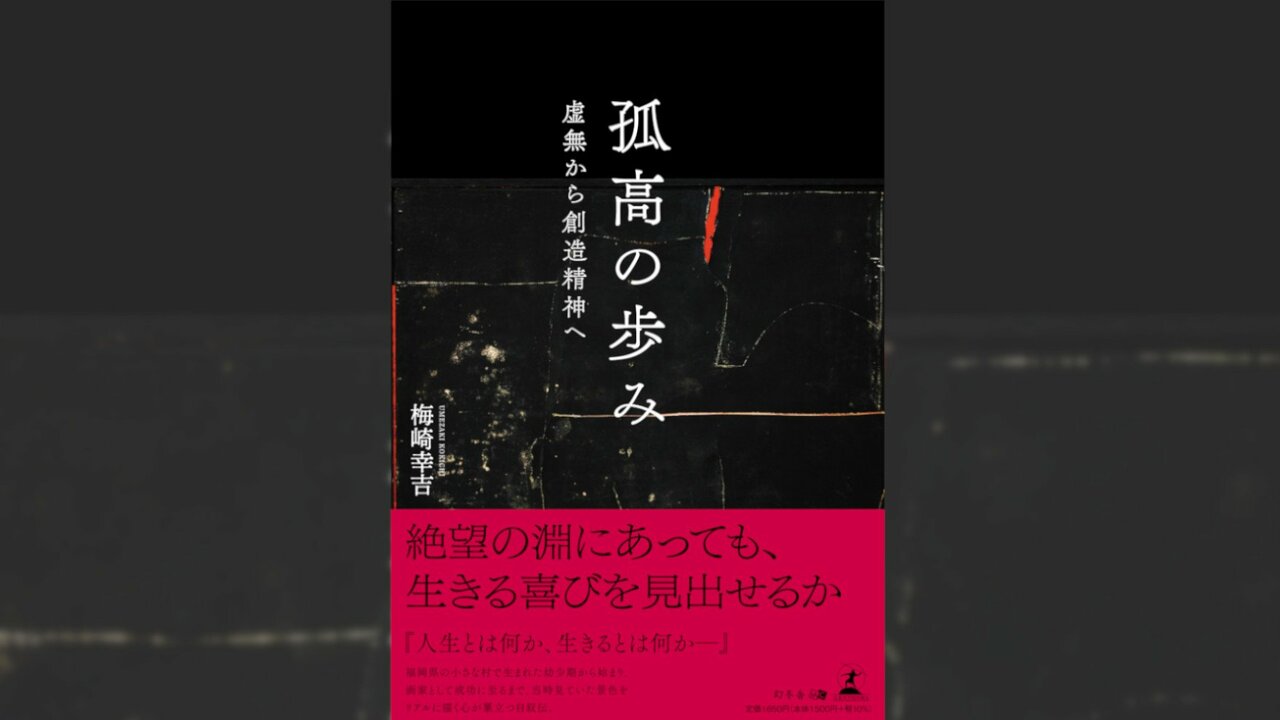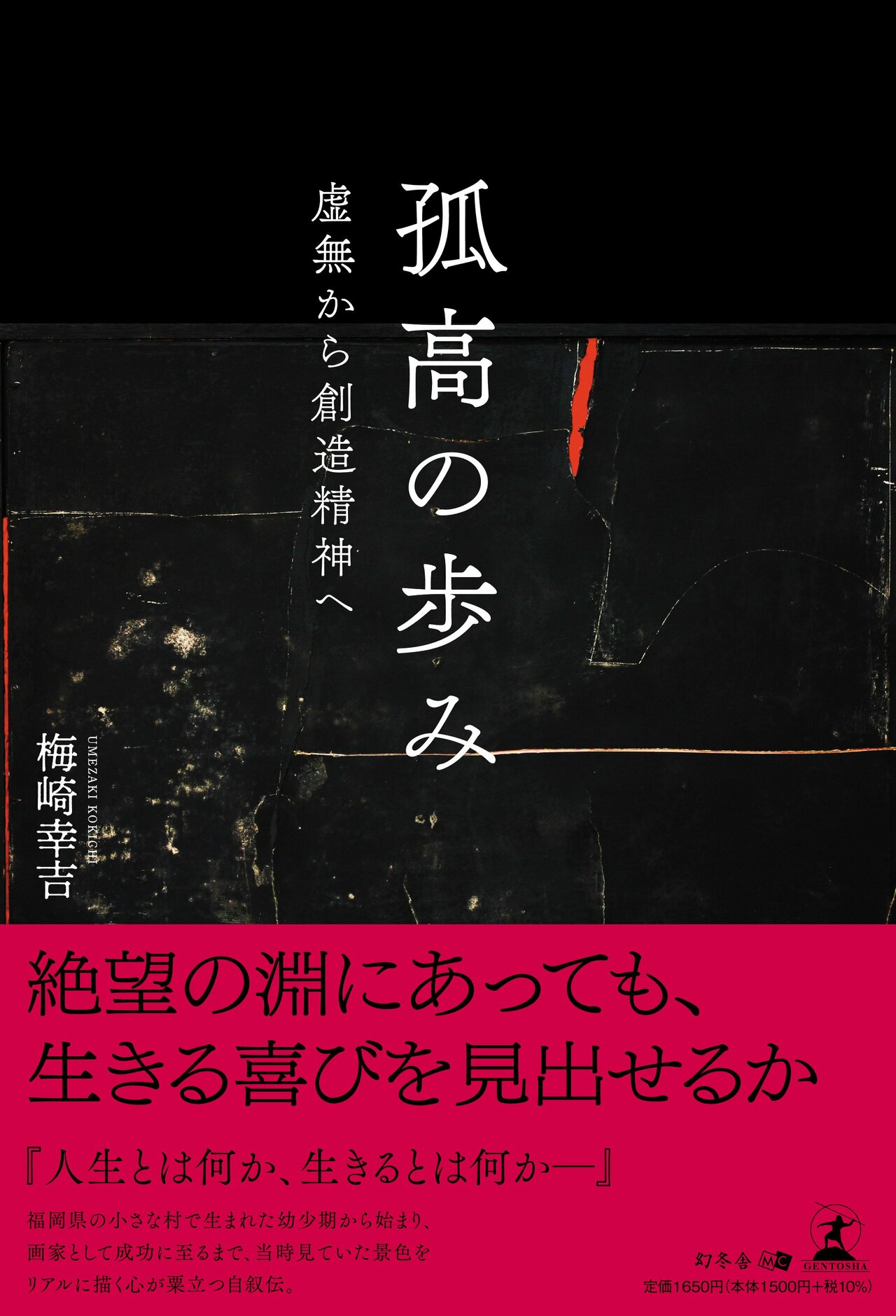一、
父は長崎の佐世保で生まれ、幼い時にすでに両親を亡くしていた。母の静香は八女市から義祖母である津留崎ヤクの所に来た。
父は幼少時に両親を失って叔父に預けられ、そこで十歳の頃から仕事をさせられた。叔父は家具職人であった。父は十五歳の時にはすでに一人で箪笥を作れるほどの家具職人になり、無給でこき使う叔父の下を去って独立した。
その後、転々として、縁があって祖母に気に入られた。義祖母のヤクは気性の激しい女性であった。
私が三歳の時に義祖母の背中におんぶされていた時、私が面白がって揺さぶった。ふらつく義祖母を見て私はさらに揺さぶった。義祖母は私を背負ったまま、前のめりで倒れた。その時に義祖母の鼻が潰れた。倒れる時も私をしっかりと掴まえていたのである。
顔中血だらけの義祖母はそれでも私を心配して「何ともなかか?」と、何度も聞いた。私が悪かったのだが、義祖母は倒れたのは自分の年のせいだと人には言っていた。
私はそれ以来、二度と義祖母の背中を揺さぶらなくなった。義祖母は私や兄弟の誰かが村人にいじわるされたり、何かされたりすると、その家に草刈り鎌を持って怒鳴り込んでいた。
「ヤクしゃんは、きつかけんなあ」
村人は義祖母を恐れていた。その理由は私にはまだ分からなかった。だが、私達が村にとって「よそ者」であることがはっきりと分かったのは、義祖母が亡くなってからであった。
義祖母は私が小学二年の時に火傷が原因で死んだ。冬の寒い日に火鉢を跨(また)いで身体を暖めていたのが命取りになった。垂れていた着物の紐が燃えて着物全体に広がったのである。気がついた時にはすでに手遅れであった。その日の夜に息絶えた。
義祖母が亡くなってから私の家庭の歯車が狂いだした。彼女の死で私の家族は村にとっては「よそ者」となった。
秋になると台風で筑後川の支流の川が氾濫し、村は毎年のように洪水になっていた。父が独立するために買っておいた木材が洪水によって全て流された。借財を返しながらの仕事と村人達の陰湿なよそ者に対する態度の心理的圧迫は徐々に父の神経を蝕(むしば)んでいった。