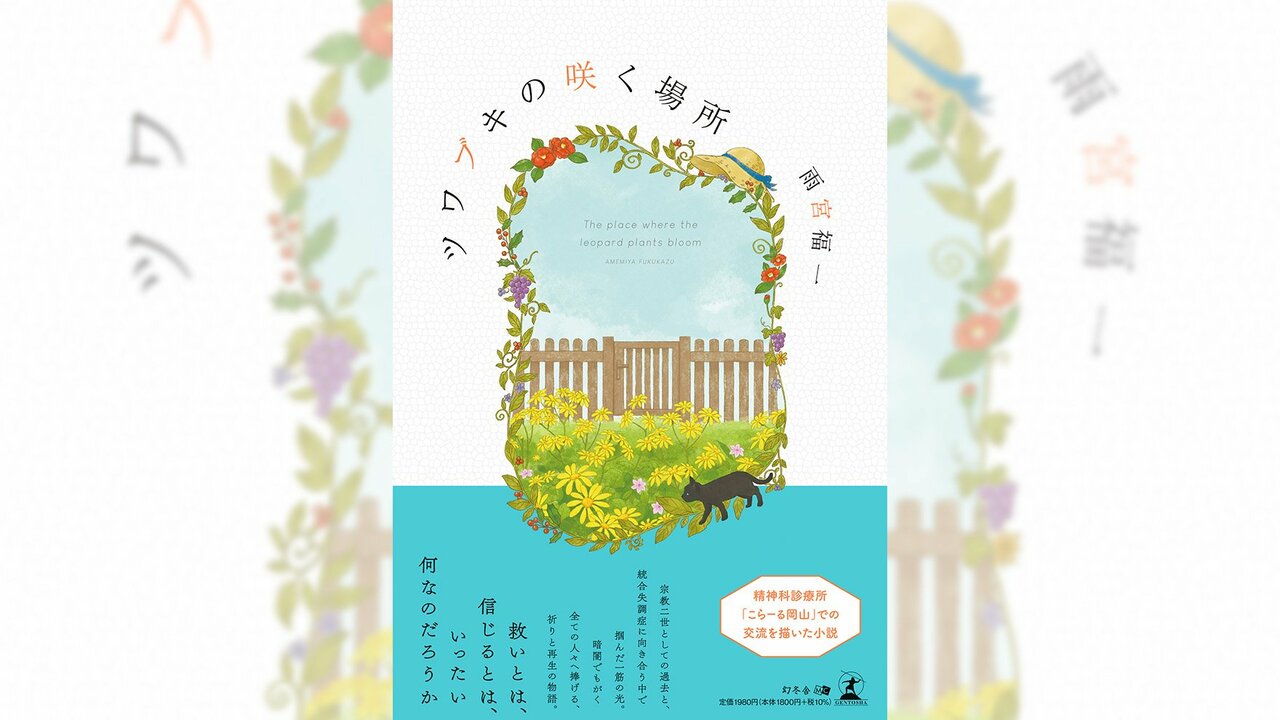第一章 靴
【 一 】
「……夢だ」
ぽつり、私は呟いた。ベッドの上。いつもと同じ一日の始まり。ダウンジャケットを羽織って、廊下に出る戸を押し開けたら、きい、と音がした。
「喉、渇いたな」
カーテンの隙間から、太陽の光が差し込む。ついカーテンを開けて外を見た。木の枠に縁取られた窓からは、ざわざわ揺れる雑木林、そして手入れの行き届かない伸び放題の松が見える。ありふれた一日の始まり。
階段を下りる。
ふすまで仕切られた部屋を抜け、キッチンにたどり着く。ステンレスの流しに一晩放置されたコップは、半分水で満たされている。
岡山市内へはバスで行けるが、住む人のあまり多くもない地区の、とある古民家。
私はこの古民家にたった一人で暮らしている。一軒家であり、改修には費用がそれなりにかかった。実際、町の移住制度がなかったなら、住むことは叶わなかったろう。ちなみに、収入は決して多くない。
電気ケトルに水を注ぐ。ぱちり、とスイッチを入れた。いつも食事をするテーブルに、ふと、中身が詰まって膨らんだ一通の封筒が置いてあることに気付く。
――それは突然の手紙であった。
差出人の名は「夏春茜」(なつはるあかね)。私の実の妹である。もしかすると……この手紙がもとで、私は「あの四歳の日の夢」を見たのかもしれない。
彼女とはもう、七年以上は、会っていなかった。それが、突然に手紙を送ってきた。彼女が今さら連絡を取ろうとしたわけを知ることが怖くて、昨日の私は、居間のテーブルにその封筒を置いたままにしておいたのであった。
開ける勇気はなかったけれど、捨てる勇気はもっとなかった。
「……よし!」
意を決し、私が妹の寄越した封筒を開封した、まさにその時。
「ねーぇ。私の分のお茶がないけど?」
煤(すす)けたかまどの中から声がする。私はそちらを見ないようにしながら、「知らない」と返事しそうになる口をつぐんだ。
「無理しないで、涼。私、淋しくなっちゃう」とん。とん。
床へ降り立った足は、恐ろしく白い。手指の爪は桜色をして、さやさやと揺れる白のワンピースには、かまどの煤が黒くこびりついている。けほっ、と短く息を吐いたのは少女だった。