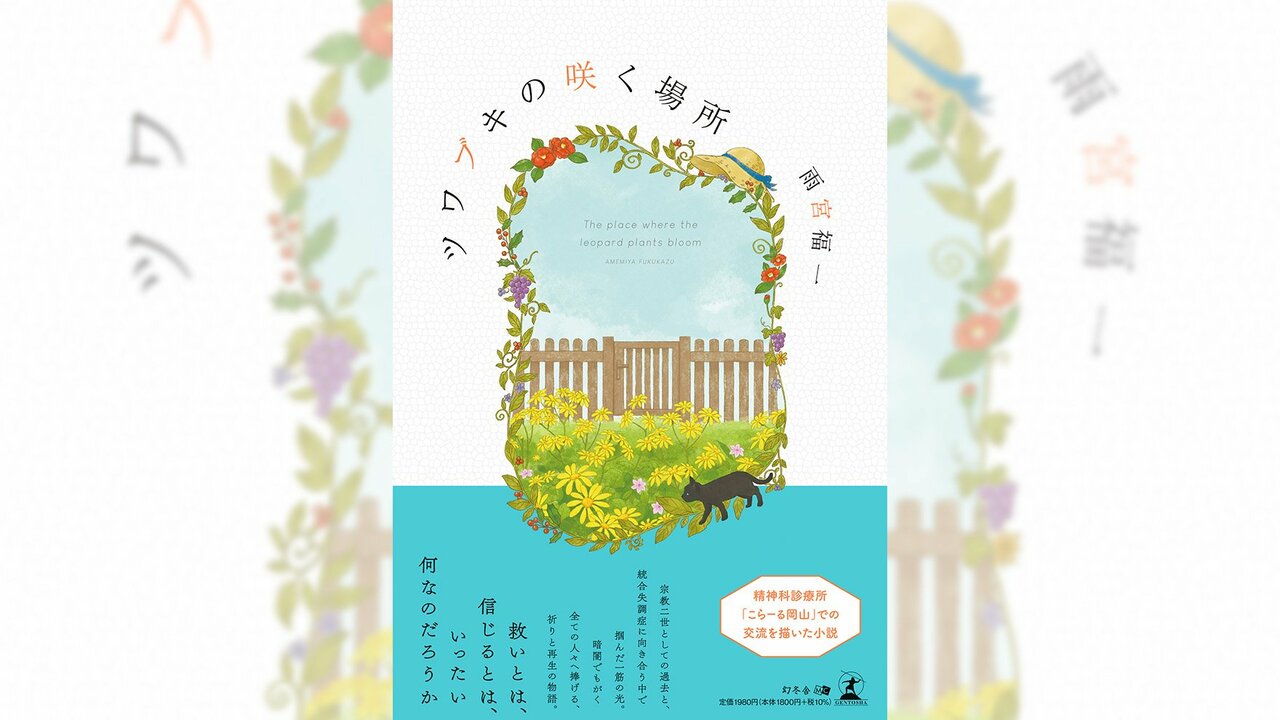プロローグ
夢と思いたくなるような、凄惨な光景である。私の視界はとめどなく流れる涙でぐしゃぐしゃになり、もはや女の子の表情を識別することもかなわない。
アパートから母が飛び出してきた。奇妙なことに、表の騒ぎに今ようやく気付いたらしい。
「涼? どこ、どこにいるの!」
母がそう呼ばわったけれど、私の姿は大きな草の陰に隠れて見えない。母の目にはむろん留まらず、立て続けに私の名を呼ぶ声がする。
「お母さん!」
私が叫び返すと、母は彼方から鋭くこちらを見やった。すぐに駆け寄ってきて、男から私を奪い返す。母の腕へと抱き取られて、私はつかの間安心を得たが、すぐに向き直って男たちをにらみつけた。
男たちは、女の子を連れてどこかへ行くところだった。草むらの間に、女の子の印象的な赤いスカートと美しい黒髪とが見えなくなっていく。
私は母に「追いかけてほしい」と言いたかったが、母は母で、息子である私をかばいつつその場から離れるのに必死の様子である。
いよいよ遠くなっていく少女の白い脚が、男たちの一人の腰を挟む恰好に広げられて、右左、まるでキーホルダーか何かのようにぷらぷらと揺られているのが見える。
かろうじて爪先に引っかかっていた黄色の靴下が草原に振り落とされて、少女の姿は今や影も形もない。
私は目を背けることをしないで、ただもう一心に、懇願したのである。
「お願い、やめて」
しかしその声は、まるで浴槽の中にいるように、反響して戻ってくるだけだ。
大股で急ぐ母が軽く悲鳴を上げて、不自然に数歩右側へよろけた。土がむき出しの道の上に、ぺしゃんこに踏みつぶされたカエルの死骸が見える。
女の子の叫ぶ声は届かなくなり、男たちの声も聞こえてこなくなった。でも、それでも、一人の少女が傷つけられたということ。それは本当にあったことなんだ。