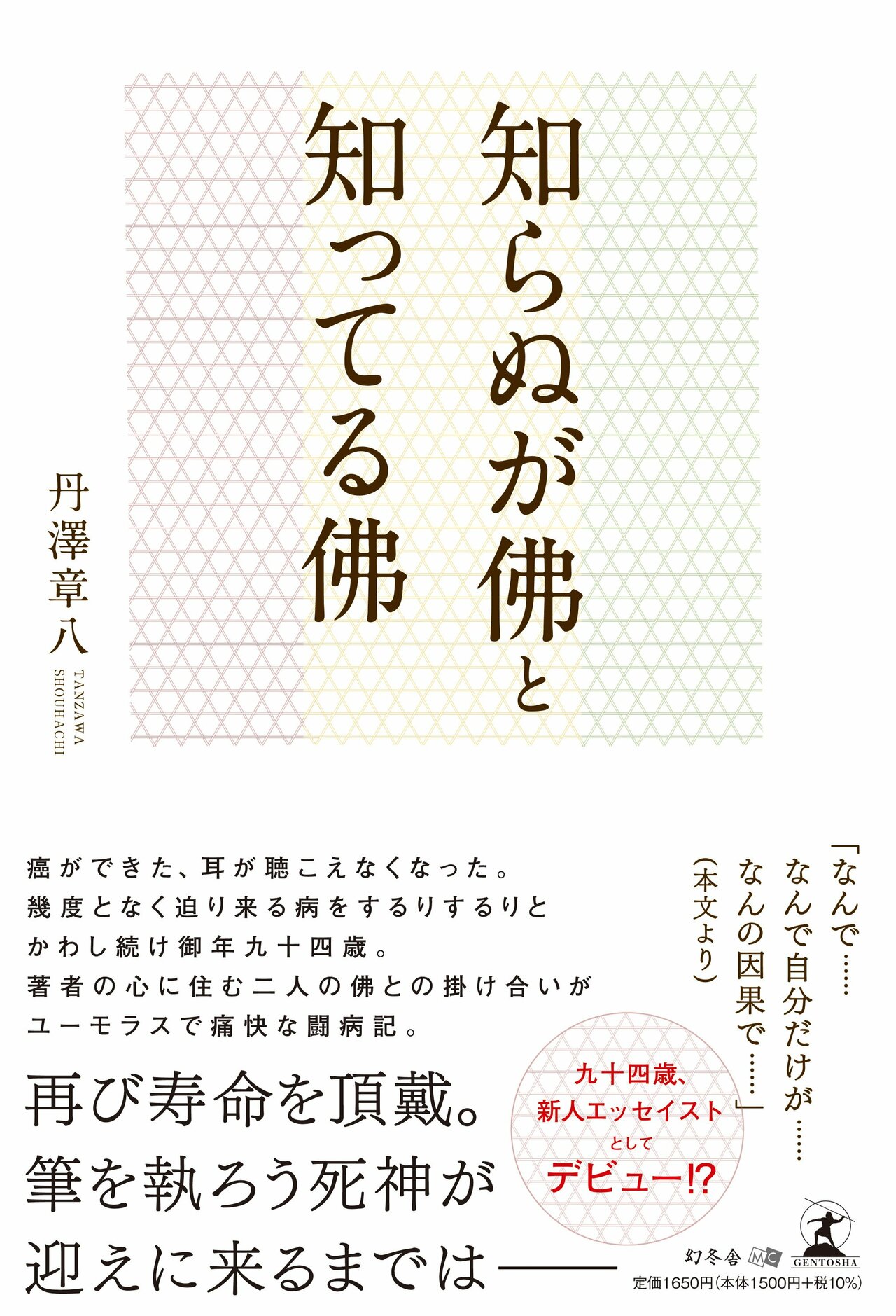三月二十二日
午後二時をまわったころに美瑛子と日出夫と長女の朝子が面会に訪れた。入院後一週間、食止めの君の憔悴の度合いを案じていたが、意外に元気そうな姿にまずは美瑛子も日出夫も朝子も安堵した。
「あなたは沢山の人を助けてきたんだから、そのご褒美はきっとあるから大丈夫」
美瑛子は真底からそう信じていた。夫も自分も両親よりはるかに長生きをしている。いや生かしてもらっている。常々の感謝の心の中に、いま夫を失うなどという業念は、美瑛子には微塵も存在しなかった。
勇気づけられる言葉に感謝しつつも君は、その言葉をかけられるたびに、命が尽きるときは地獄に落ちるという想念が首をもたげる。
というのは、君の医師としての出発は産婦人科医であった。医師は一生病者と付き合わなければならない。それが嫌だった。
妊婦は健常者の代表的対象であり、さらに出産という新たな命と出会う、きわめてポジティブな医療という認識が選択の理由であった。が、昭和二十年代後半、敗戦の社会的困窮から産児制限を内容とした優生保護法のもと、当時の産婦人科医にとって、妊娠中絶術はルーチンの医療行為であった。
君もその時代に青年医師として現場に在った。その姿を現在に呼び戻す度に、振り返って、自身は重殺人罪を負っていると思っている。
『ちょっと待った! お前様よ! いまそんな追想にふけっている時ですか! 奥さんの心情を察して、手をしっかり握って、礼と、逆に勇気づけをしなくちゃいけないのに、何をもたもたしているんですか! お前様は常々、いま、いまが一番大切であると言っているじゃないですか!』