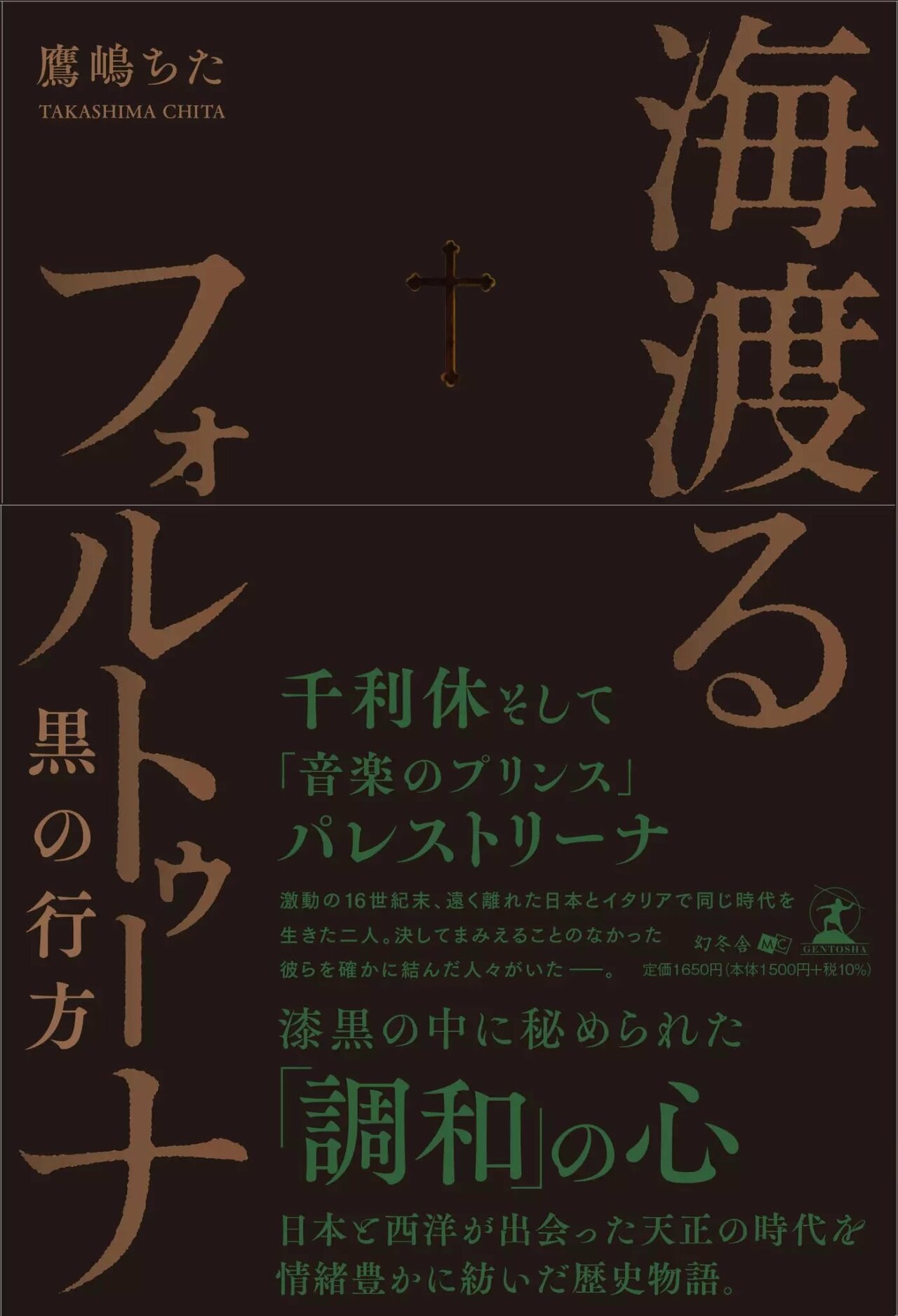「高麗時代の様に古い物は、それ程多くはございません。殆どが今物でございますぞ」
「存じております。元や明の時代に作られても『唐物』というように、高麗時代でなくとも『高麗物』と敬意をもって呼ばせて頂いております。茶道具も、以前は唐物だけの世界でございました。
八代将軍足利義政公の頃、奈良の村田珠光が、信楽焼、備前焼、手桶の水指などを使用しだしました。そしてそれらを組み合わせて、客前で主人が自ら茶を点てることが始まりました。
茶入を中次や棗(なつめ)などの塗物にしたりと、『和漢の境を紛らかす』茶に変化して参りました。しかし、茶碗だけは未だに青磁や天目など唐物のまま。そこにやっと天目に代わりうる物として、高麗物が少しずつ使われるようになりました。
しかしまだまだです。道具は『なり・ころ』。即ち『姿と大きさ』なのです。未だ『なり・ころ』の良いものに出会えないのです」
「ではご自分で探されては如何ですか」
「え?」
「朝鮮に参りましょう。博多から朝鮮までは、堺までの半分の距離でございますよ」
堺で見なれた瀬戸内の穏やかな海とは異なる玄海灘を見ていると、全く違う世界に漕ぎ出したのだという想いに駆られる。勢いで松栄と共に豊後まで来て、大友宗麟に出会った。
そこで島井茂勝の言葉に乗せられて、今は博多から漕ぎ出で、壱岐から対馬に向かっているのだ。
「宗易様、もう直ぐ対馬の島影が見えてまいりますぞ。ご覧ください。海の色が変わって参りました。ここからは潮の流れが速くなりますから船が揺れます。お気をつけください」
「同じ海でも随分と色が違うものじゃな。様々な「物」がこの海を渡って来た。数多くの唐物道具もそうだ。しかし、その数より遥かに多くの物がこの底に沈んでいる。生き残った物を大事に使わせて頂かなくてはな」
「三〇〇年前には、この海を通って、中国と朝鮮の兵五〇万人が攻めて来ました。対馬と壱岐の民は、二度に亘って皆殺しにされました」
「あってはならぬ事だ。我々も決してしてはならない」
そう言って目を西北にやると、対馬の島影が見えてきた。これから二四年後、宗易が死んだ次の年から二度に亘って、逆に三〇万人の日本兵がこの海を渡るとは、この時の宗易には想像すら出来なかった。
【前回の記事を読む】門をたたき30年、新たな境地を目指す千利休の茶道は行き詰まっていた…