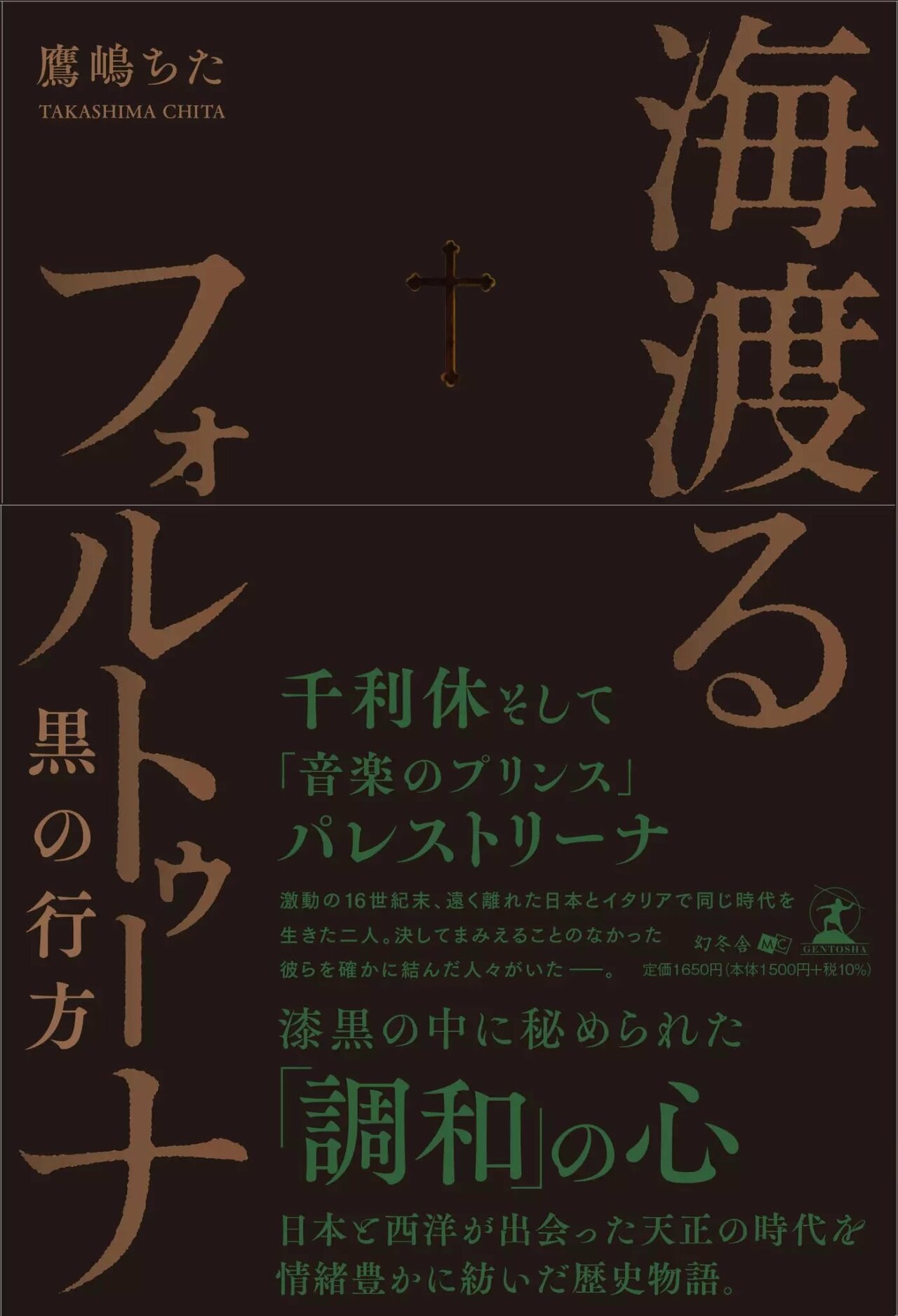朝鮮渡海
「三島の二碗は、何がお気に召されたのですか」
「端反(はたぞ)りの方は姿と、何と言っても白の美しさです。見込みの部分にある三段の暦模様も静かです。桶型の方は実に端正です。斜線や花小紋がはっきりとして重厚な趣があります。口が広い物が多い中、抱き込みになっております。とても心惹かれる形です」
「こちらの琵琶色の茶碗は」
「腰の柔らかさです。形がやや扁平な所が人間味があります。師匠の紹鷗様がお持ちの物より薄く小ぶりです。口の開きがおおらかでしょう。この美しい赤味と腰の姿に、妻のりきを思い出していました」
「それは恐れ入ります。宗易様の奥方様には、是非ともお会いしてみたいものです。ところで最後のこの二つは、何にお使いになるのですか。何時選ばれたのか、全く気がつきませんでした」
「面白いでしょ。水が飲みたくなり台所を借りた時見つけたのです。この小さい方は薬膳に使う松の実が入っていたのです。何に使うかはまだ考えていません。香炉にしても面白いかもしれません。黒い筒型の物は花を一輪入れてあった姿に感動致しました」
蓋付きの器は、高さ二寸五分(七・五センチメートル)の愛らしい姿である。井戸の釉薬(ゆうやく)が掛けられた塩笥(しおげ)形で、高台際と蓋の撮(つま)みに僅かな梅花皮が見られる。
後世、利休(宗易)の書付で「此世」と呼ばれる利休愛蔵の香炉と、最晩年に好んで多く使われた花入「高麗筒」との出会いである。
宗易は茂勝と共に豊後に戻り、大友宗麟に挨拶をした。
「ありがとうございました。お陰様で、やってみたいことが、雲のように湧き出して参りました」
「それは重畳。ところで松栄殿も仕事が終わり、宗易殿を待っておられた。共に帰るもよし、未だ暫く領内におられるのもよし。好きにされるがよい」
「恐れ入ります。一緒に帰ろうと思いますが、その前に府内で伴天連にあってもよろしいでしょうか」
「無論じゃ。今はアルメイダ殿とロレンソ殿が布教しておられるはずじゃ」