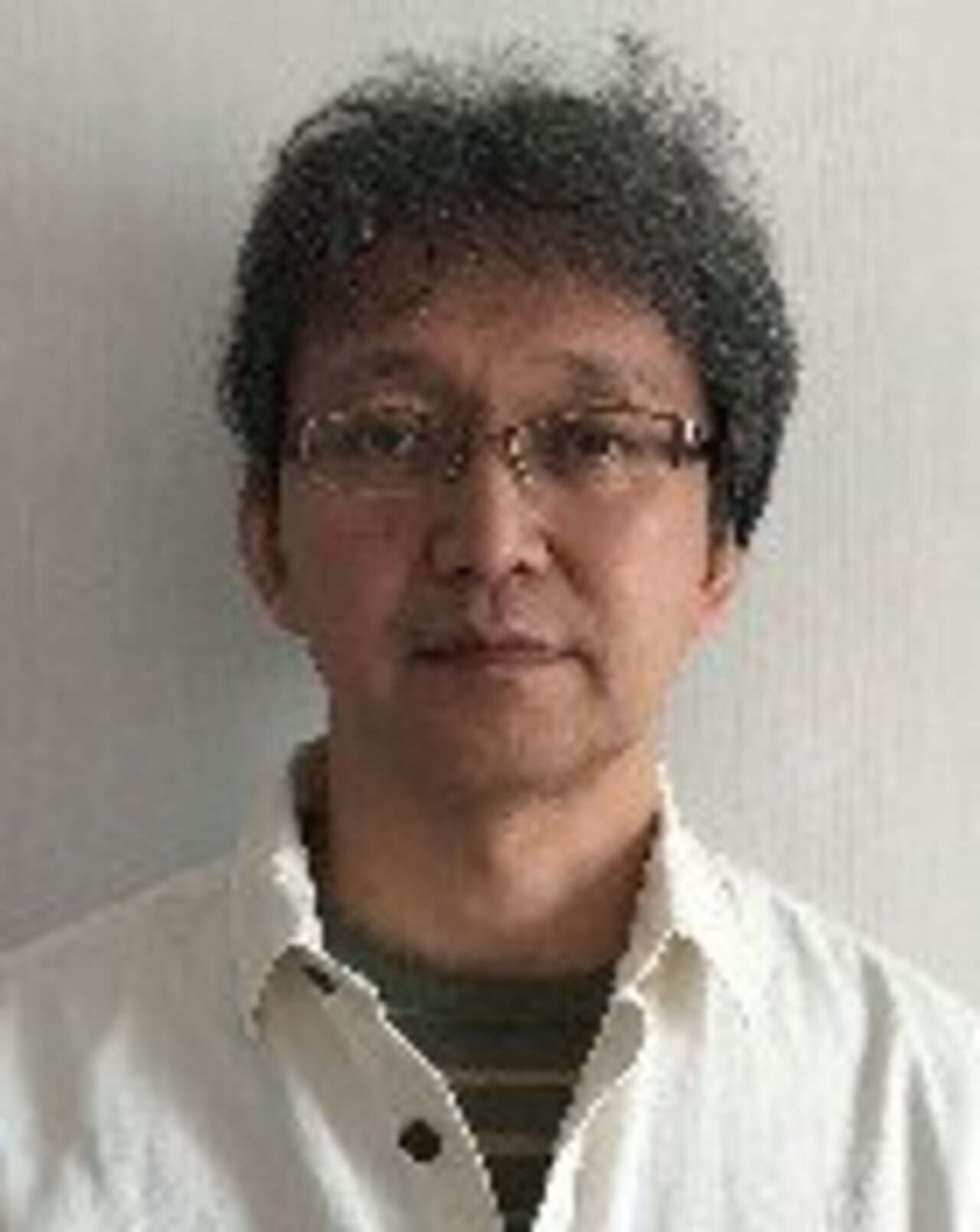ハ短調に

戻れない道
二〇一五年五月のある朝。夜勤明けの廉は薄ぼんやり目を開けた。
眠りが足りていないことに軽く失望しつつ隣のベッドに目を向けると、和枝が横になったまま廉を見ていた。
「おはよ、もう起きてたの? いま何時? 遥は?」
「九時半回ったとこよ。遥、きょう学校休みでしょう。お昼過ぎから愛絵ちゃんと静那ちゃんが家に来て6手連弾の合わせをやるんだって」
「えーと、カルメンだっけ」
「そう」
いつもと変わることのない朝が始まりかけたとき、和枝が口早に何かを言った、廉の目を真っ直ぐ見て。
口は動いているのに声がすぐに伝わって来ないような妙な錯覚を覚えた。
「私、肺がんかもしれないって」自分の言葉に戸惑いながらも口元はかすかに笑っていた。
その日一日を、会社でどう乗り切ったのか。それについての記憶は全くない。
廉はとにかく、深夜、宅送りのハイヤーに乗っていた。
首都高速に入ると、車はちょうど羽田空港に向かう東京モノレールとぴったり隣り合って走り始めた。天王洲アイル駅を過ぎる辺りからは互いの間隔はさらに縮まって、まばらに座る乗客の表情までもはっきり見えるようになる。
「和枝、和枝、和枝」心が叫んでいた。
やがてハイヤーは緩やかな右カーブに導かれていき、モノレールは方角違いの空港ターミナルへと流れていく。廉は遠ざかる赤いテールランプを見送った。
「明日からどうすれば」
廉は車内灯を点け、出がけに和枝から預かったCT画像のコピーに目を落とした。
思い返せば桜の散る頃から和枝の体に異変の兆しはあった。
最初は声が出づらくなった。和枝にとっては声も大切な商売道具だ。
「ピアノを弾くこと即ち歌うこと」なので、小さな子どものレッスンでは歌にも時間を割く。
伴奏を付けながらお手本を示し、さらに一緒に声を出す。のど飴が手放せず、キッチンにもピアノの上にもいつも缶が乗っていた。
今回の声枯れはストレスが原因だろうと和枝自身は考えていた。風邪でも花粉症でもなく、体調も少しも悪くないので。まあいつものことかな、と。
四月中旬頃から咳と痰が酷くなり始めた。
夜中に隣のベッドの廉まで目を覚ますほど激しく咳き込むこともしばしばだった。
街の漢方薬局で、ドロリとした真っ黒い咳止め薬を処方してもらったりもしたが効果は芳しくない。声枯れも良くなる気配がなく、そのうち咳をすると背中の左側面に痛みが走るようになった。
【前回の記事を読む】「これに決めさせていただきます」音とつながり、潜り込み感じた将来性。
【イチオシ記事】「気がつくべきだった」アプリで知り合った男を信じた結果…
【注目記事】四十歳を過ぎてもマイホームも持たない団地妻になっているとは思わなかった…想像していたのは左ハンドルの高級車に乗って名門小学校に子供を送り迎えしている自分だった