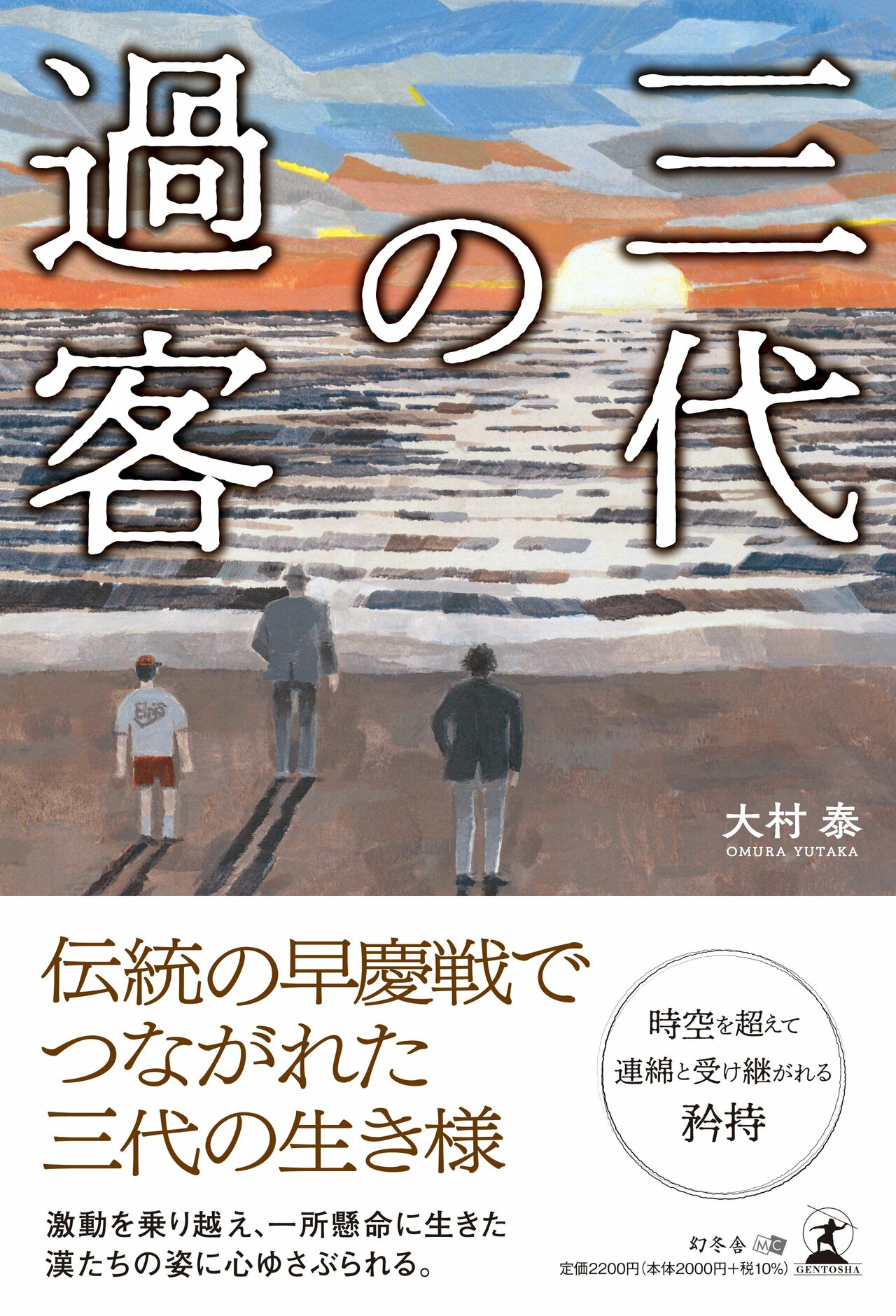もう、君に費やす時間はない、といわんばかりに鷲尾はパソコンをいじり始める。席を立つと、背中に追い打ちの矢が突き刺さる。
「俺のモットーは分かっているな? スピード第一だ」
「肝に銘じます」と振り返ると、肢体(したい)からは想像だにできないバルちゃんの冷たい視線がチラッと頬を打つ。
「ちょっと、いいかい? 別室で」と経理の鬼が口を開く。側近である辻のオフィスはCEOがふんぞり返るVIPルームに隣接する通称「番犬小屋」だ。「新聞メディア部門の収益が芳しくない」と、いきなり強烈なジャブ。
「部数が伸びないなら、経費を切り詰めろ。事業収支が赤字に陥りかねんぞ」。
グラフやデータを駆使して追い込んでくる。出張費や交通費、交際費、果ては鉛筆など文房具代に至るまで、項目別に細かな数字が並ぶ。
うんざりしながらも、なんだ、そっちか。人件費じゃなくてよかった。
「極力、不要不急の出費はそぎ落とす。このあとの打ち合わせで徹底します」とおためごかしに返した。もちろん、そんな気はない。若手二人を甲子園へ出張させている件は伏せておく。
やや打算的だったかなと思い直し、「今回の戦後六十年特集は新聞だけでなく、インターネットや映像を使った二の矢、三の矢の収益も生むはずです」とフォローしておく。これは必ずしもその場しのぎの方便ではない。
十五年前のことである。「ミレニアム=千年紀」と世間が浮足立っていた二〇〇〇年、二十世紀と二十一世紀のはざま。大山胖は新聞大手「東京政経新聞」の記者だった。
当時の上司とそりが合わず、悶々としていた。いきなり、鷲尾から誘いの声がかかる。短躯(たんく)ながらスポーツジムで鍛えたとおぼしき筋骨。ぎょろ目に鷲鼻の顔貌は威圧感がある。皇居の堀が垣間見えるホテルの喫茶室でこんなやり取りをした――。
【前回の記事を読む】ゆくゆく、この男が微妙な立ち回りをすることになろうとは、この時点では気づかなかった