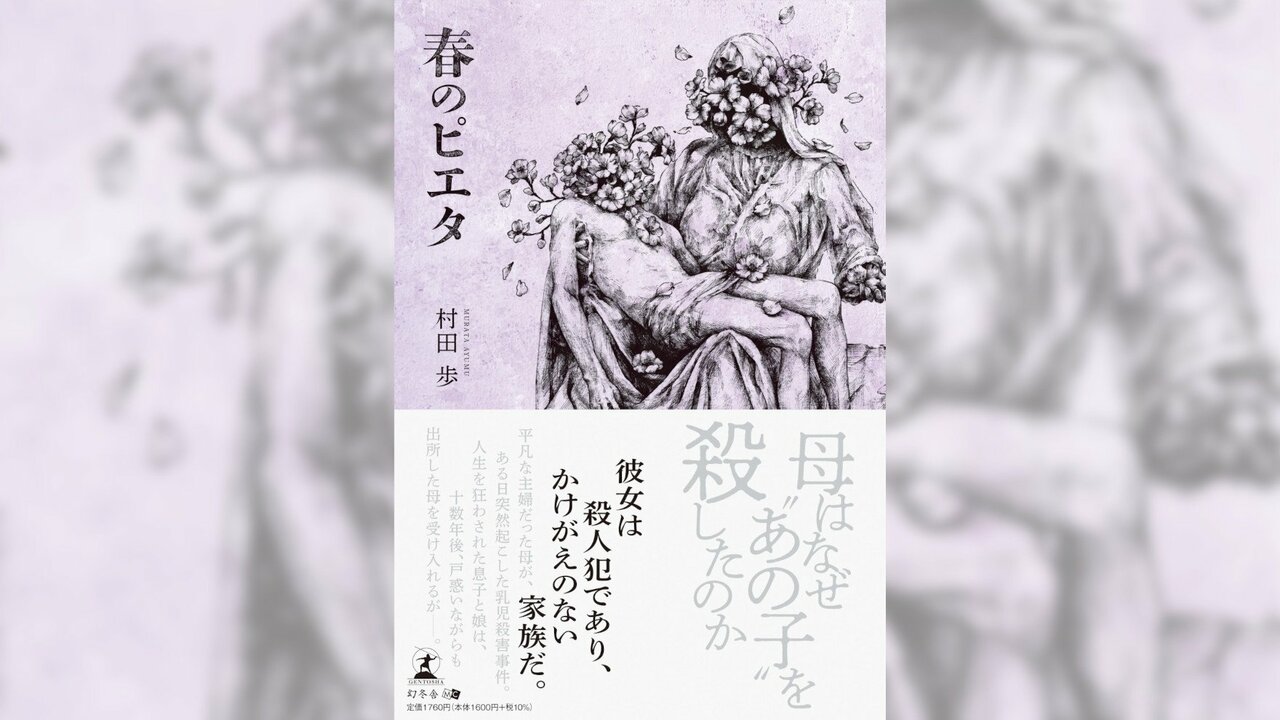劉生 ―春―
先導して前を歩いていた親父が、ふいに歩道を逸れ、広いパーキングエリアへ入っていった。俺と優子を振り向きもせず、大きなえび茶色の建物へ向かって歩いていく。
東京では見かけない名前のホームセンターだ。まだ午前九時をまわったところだが、駐車場にはもう何台も車が停まっていた。
二重扉になった入り口を入ると、名産品や地酒の並んだ一角だった。目の前の棚に、見慣れた縦長の菓子箱が山型に積まれている。難しい名前のついた薄い煎餅で、読み方はとうに忘れた。
親父は月に一度、必ずこの煎餅を手土産に買って帰った。おばあちゃんが一番喜んで食べていた。十五枚入り、五百四十円か。つまりここは親父が帰り道に必ず寄る場所というわけだ。そこに行きに寄ったのは、お腹の大きい優子を気遣ってのことだろう。
双子でも入っているのでは、というくらいお腹のせり出した優子は、つわりの時期こそなまっちろい顔がひしゃげたようになっていたが、それを過ぎると嘘のように元気になり、今日は朝からピクニック気分で燥(はしゃ)いでいる。
歩幅が狭くペンギンのように歩くのは、せり出したお腹で足元が見えないせいだ。一昨日降った雪がまだ路肩や日陰に残っている。俺は優子がこけそうになったときの用心のため、駅からずっと妹の背後にくっついて歩いてきた。
片道一・五キロ。このペースだと三十分以上かかるだろう。
親父は駅前でタクシーに乗ろうとしたが「あたし歩けるもん、たくさん歩いた方がいいって、お医者さんも言ってるもん、ジョギングしてる人もいるんだよ」と強情を張る優子に負けて、行きだけ歩くことに決めた。
「ジョギングする妊婦なんて見たことねえや」と俺は妹の頭を軽くはたいたが、歩きながら考えたことは、どんなに悪天候の日でも、親父はこの道を徒歩で通ったんだろうな、ということだった。
煎餅の山の奥に飲食コーナーのような場所があった。テーブル席が二つだけ、あとカウンターに電子レンジと製茶機がのっている。案の定、親父がテーブルを指さして座れという素振りをした。「時間はだいじょうぶなの?」という優子の問いを聞き流して、奥の食料品売り場へずんずん歩いていく。
まさか食い物を持ってくるんじゃないだろうな、朝飯食ったのに午前九時半にまた食事かよと思ったが、飯を食ったのはまだ外が暗い五時前で、コーヒーにコッペパンだけだったから、正直、俺は腹が減っていた。