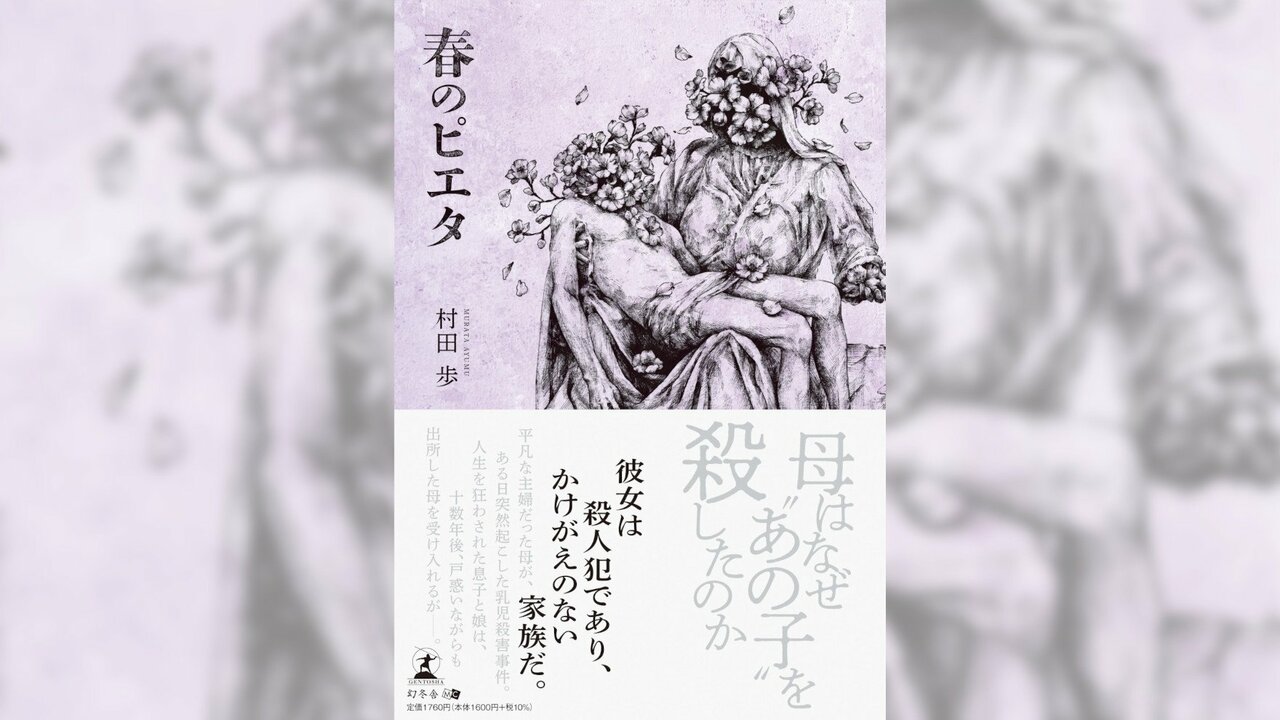劉生 ―秋―
「見つかったら見つかったでそのときだ、なんて思っちゃだめよ」
「わかってるよ、そんなことくらい」
見透かされている。先生はときどき俺に向かって、子供を諭(さと)すような言い方をする。
たまには家に顔を出してあげなさい、ご両親、心配してるわよ。妹さんにだけでも居場所を知らせておいたら? ――等々。余計なお世話だ、などと答えると、俺の耳にも自分の発した言葉が子供の口答えのように聞こえてしまう。
「そう、優子ちゃん」
先生がふいに妹の名を口にした。
「いろいろ思い出したわ。ひとつ思い出すとね、芋づる式に次々と浮かんでくる……」
松嶋先生が塾に訪ねてきたとき、室長に代わって面接したのは俺だった。中学の古典教師を十年以上勤めた年上の女を前に、俺は臆(おく)し気味だった。
加えて、差し出された履歴書の職歴を見て、俄かに緊張した。最後の行に妹の卒業した中学校の名前が記されていたのだ。とっさに年月を確かめ、妹の在学中とダブっていることを知った。俺と妹の姓は、母方の祖母と同じ、良知という。東京で同姓の人間に出会ったことはまだ一度もない。珍しい苗字なのだ。
松嶋先生は俺の緊張を敏感に感じ取ったらしく、終始にこやかに接してくれて、面接はスムーズにいった。先生の方にもなにか事情がありげだったが、そのことを俺は室長に黙っていた。そして採用はすんなり決まった。
「優子ちゃん、中学三年でもう百七十近く身長があったじゃない。それにちょっとアグレッシブなところがあったから、とても目立ったの」
「優子が? ウソだろ」