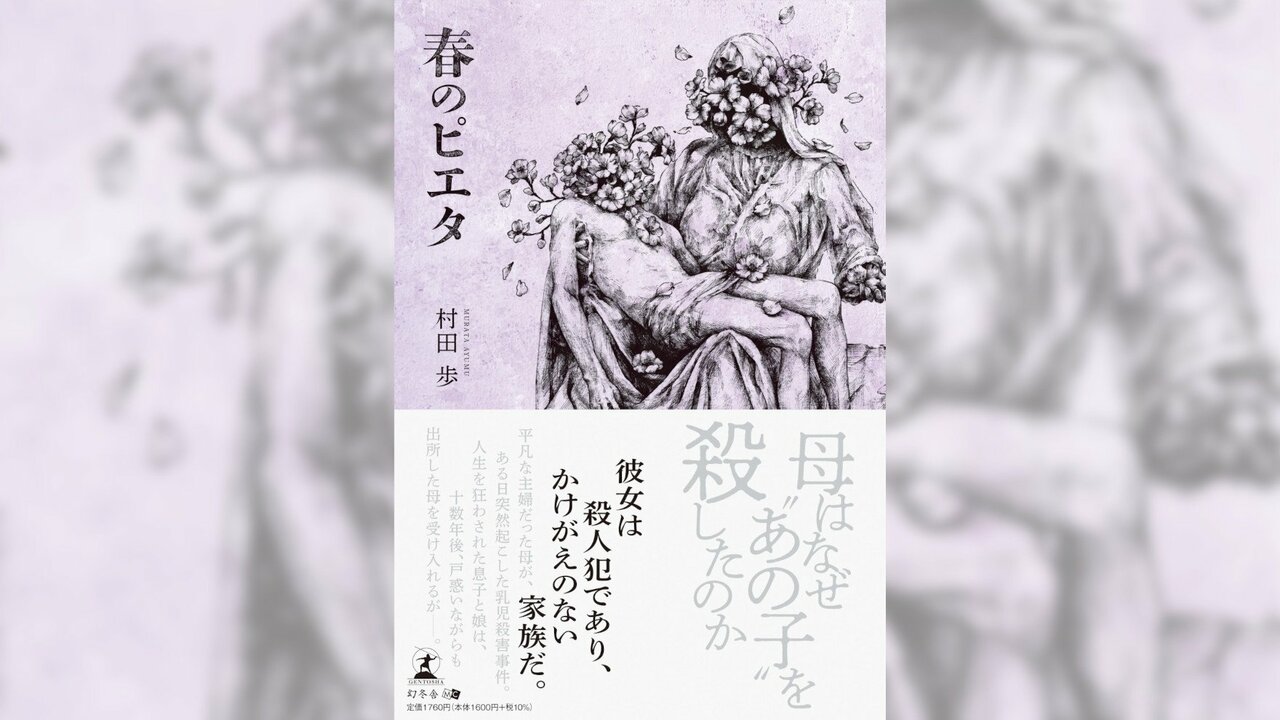劉生 ―春―
七つで突然母親を奪われて――当時の状況を考えると、奪われた、という言い方しか浮かばない――妹はひと月あまり、夜布団に入ると決まって泣いた。しかし、母親の欠けた家庭に馴染むのは俺よりはるかに早かった。
俺たちはかたちだけ田舎に住む母方の祖母の養子となり、姓が変わった。母方の祖母はお袋が親父と結婚したあと離婚したから、俺たちの今の苗字はお袋の旧姓ではない。
優子は新しい姓になると、入学して間のない小学校を転校した。親父は心配していたが、そこで辛い目は見なかったように思う。苛めに遭うもなにも、小学校一年生だ。
幼さゆえに、妹は俺よりもはるかにいろいろなことから守られていたのだろう。そして、俺よりはるかにお袋の記憶は薄いはずだ。五十前の、正真正銘の中年女になっているお袋を見ても、人に言われなければ自分の親だとはわからないに違いない。
しかし優子のことだ。いざご対面となったら、あとは泣くだけだろう。大きなお腹をして中学生みたいにおいおい泣き、それで通過儀礼は無事終了というわけだ。親父もほっとするに違いない。
これからまた家族として暮らしていくのだから、その前に一度会っておいた方がいいだろう、と言い出したのは親父だった。なにより、お袋の方で会おうという決心がついたから、こうして三人揃ってやってきたわけなのだが……。
お袋はずっと、俺と優子に会うことを頑なに拒んできた。お袋の母親と親父だけが会うことができた。お袋の代わりに俺と優子の面倒を見てくれたおばあちゃんは――親父の母親のことだが ――とうとう一度も会いに行かないまま五年前に乳癌で逝ってしまった。
まあ、実の娘じゃないんだし、おばあちゃんはお袋を心底恨んでいたようだから、それで正解だったのだ。初めの五年間ほど、お袋はしきりに離縁を口にしていたらしい。しかし親父は頑として受け付けなかった。
気持ちがほぐれてようやく親父の意向に添うような態度を見せ始めたのは、ここ三、四年のことらしい。お袋の中でどんな心境の変化があったのか知らないが、離縁云々は所詮、戯言(たわごと)だったのだろう。
世の現実がだんだんと迫ってきて、いよいよ決断が必要になったとき、恥ずかしげもなく真っ正直になった、というところではないのか。なんの庇護もなく独りでやっていくことなど、もともと本気で考えてなどいなかったのだ。
お袋、と俺は呼ぶ。昔からそうだったわけではない。子供の頃はかあさんと呼んでいた。しかしいつの頃からか、家族の前であの女のことを、お袋、と呼ぶようになった。かあさん、とはもう絶対に呼ばなかった。俺の中で、十三の年まで一日に何度も口にしていた〈かあさん〉は、もういない。