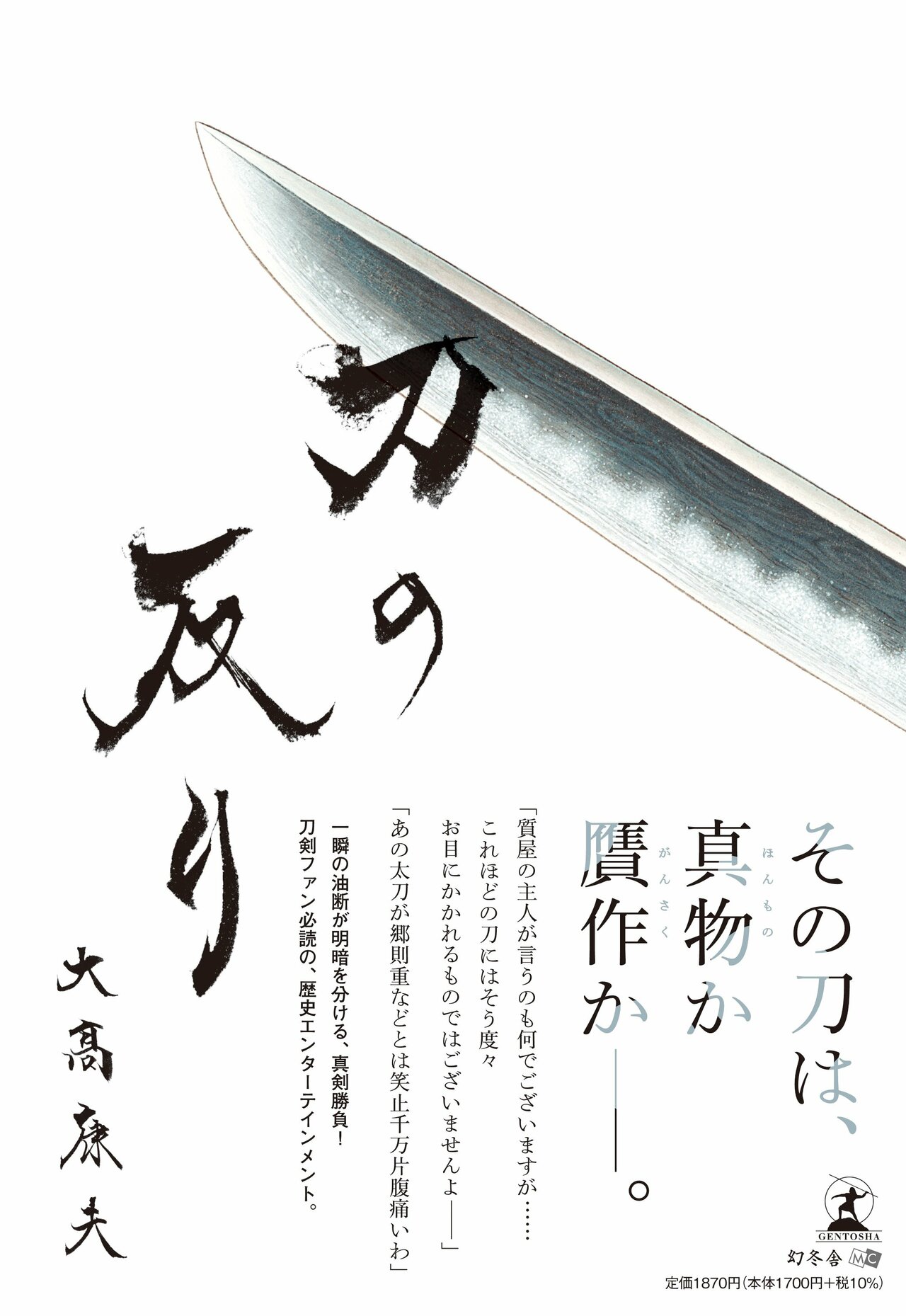「何だ、貴公……初めから己が勝つような言い種は気に入らんぞ。その言葉はそのままおぬしに返そう。ま……心配いたすな。それがしが勝とうが負けようが遺恨などというものはもたぬ。武士に二言はない」
その言葉が終わると猛之進は床に置いてあった防具を身に着け始めた。
この頃の猛之進としては武士に二言はないの言葉はかなり怪しいものである。
師範代の宗像が頷くと二人は道場の中央に立ち竹刀を構えて対峙した。
先に動いたのは猛之進であった。鋭い気合は道場の羽目板に跳ね返り、その場に端座する門弟たちの鬢(びん)を微かに揺らしたようだった。
剣尖(けんせん)は弥十郎の小手をめがけて素早い動きで伸びてくる。打ち込んだと思われた瞬間、弥十郎の竹刀は斜め下に引かれ猛之進は蹈鞴(たたら)を踏んで竹刀が空を切った。
その隙をついて弥十郎は切り返した竹刀を猛之進の胴に凄まじい勢いで叩き付けた。だが、猛之進の身体は軽々とした動きで斜め横へ跳躍したのだ。
道場通いから遠ざかってはいたが身体はまだ動きを覚えているようだった。猛之進と弥十郎、二人の互いの攻防を目の当たりにしてその場に感嘆の響(どよめ)きが湧いたが、その打ち込みを躱(かわ)したあと吐く息も苦しげに肩で息をしていた。
特に猛之進の方は息も絶え絶えといった風情は見るも無残であった。城勤めにより日頃からの鍛錬を怠っているのは明白であった。これはいかん早めに決着をつけなければならぬと猛之進は思ったのであろう。間を置かず床板を踏み鳴らして続けざまに打ち込んでいった。そのときである。