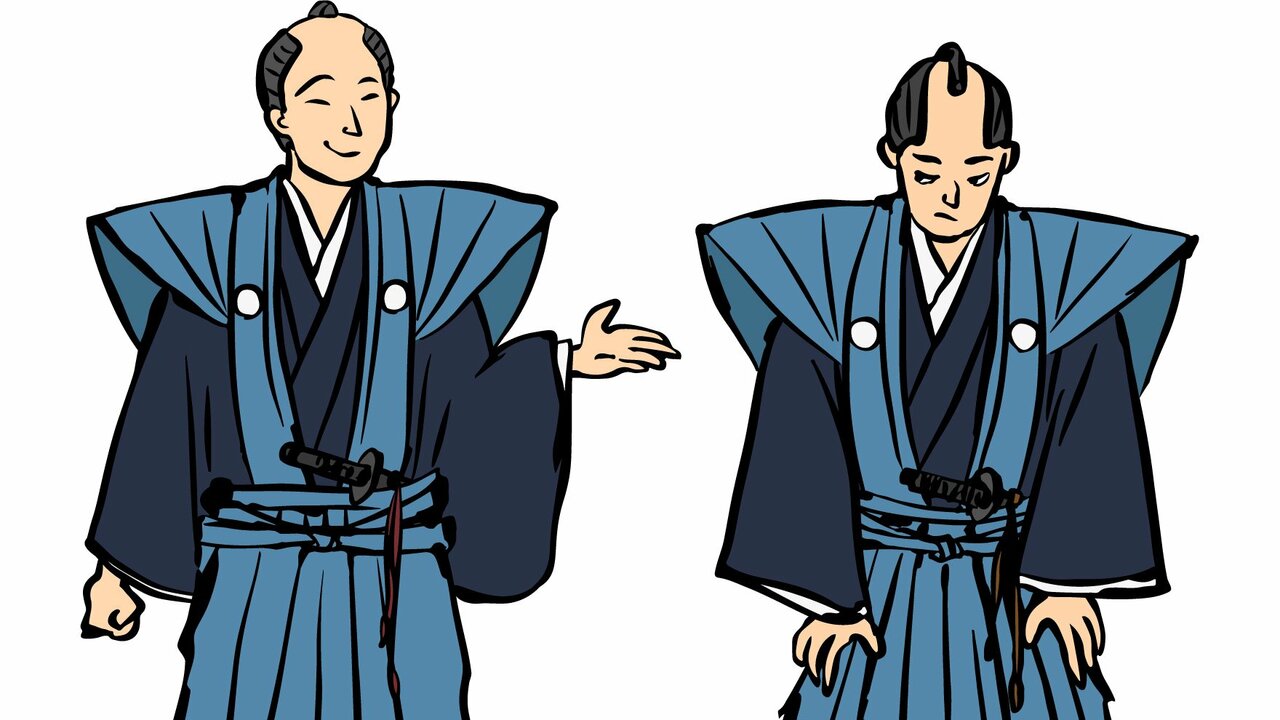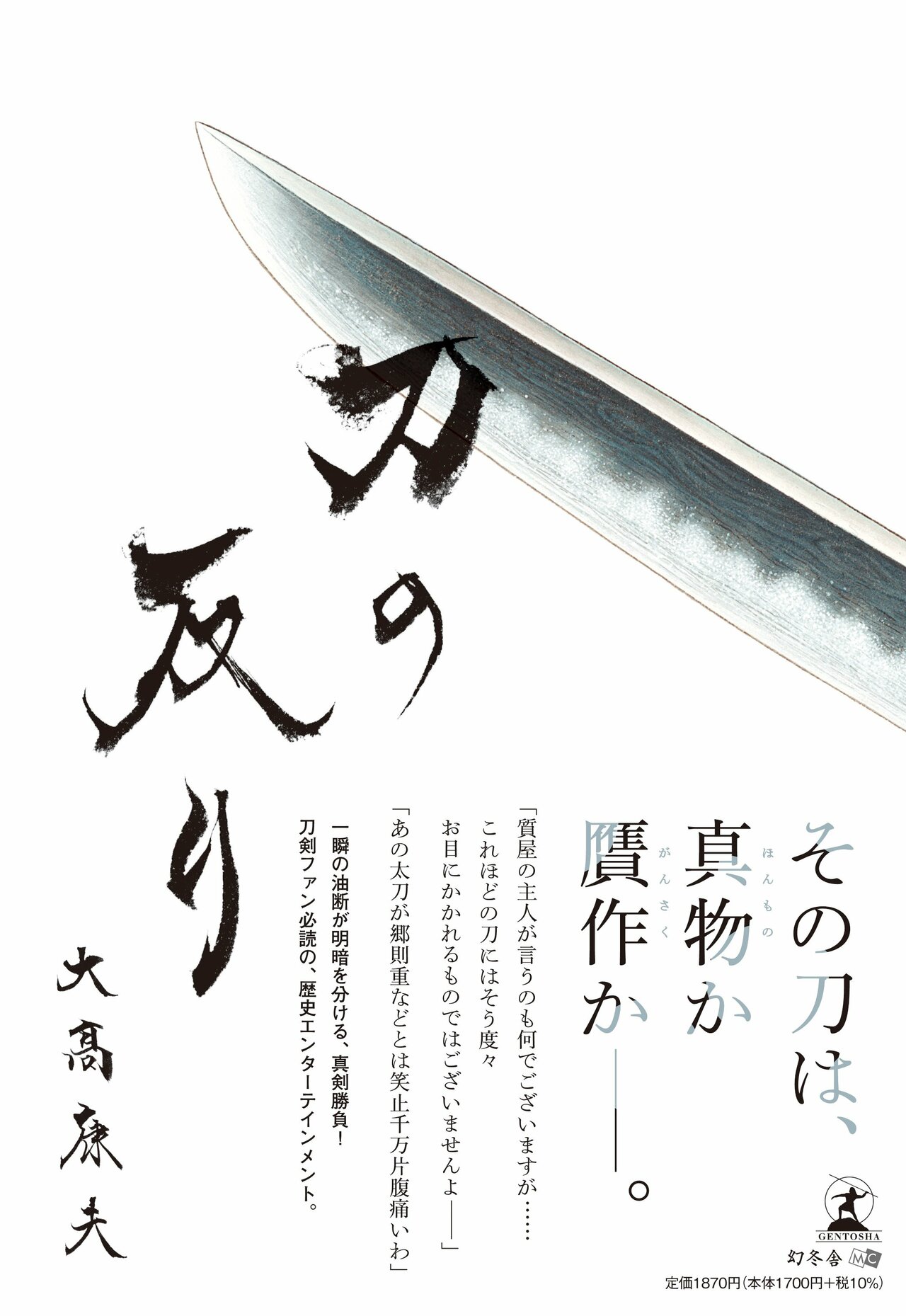命運
「まあ、待て……その様に直ぐに息むのはおぬしの悪い癖だ。そうは言ってはおらぬ。言ってはおらぬが、この目で見なければそれがしとしても確かなものだとは断言はできまい」
気色ばむ猛之進を制するように、弥十郎は右手を押し出すようにしてそう言った。
「ふむ……それほどまでに言うのなら見せてやっても良い。おぬしの目で真贋がわかるとでも申すのか」
「それがし、以前出府したおりのことだが……江戸屋敷に出入りの拵(こしら)え屋に自分の刀を研ぎに出したのだ。そのときに郷則重の太刀を目にする機会があってな。則重は短刀や薙刀を得意としており、現存している太刀が少ないからこそ価値があり逸品となるのだ」
小賢しい利いたふうな口を利きおって何を言うか、と猛之進は思った。
「そのようなことはおぬしの口から聞かなくとも知っておるわ」
「まあ、聞け。鍛えられた刀身は他の拵えとは違い独特な地肌は則重肌(のりしげはだ)とも言われかなり特徴がある。それにもう一つ……これは真物を目にした者でなければ気づかぬものがある」
「何だ、それは……」
「ふむ……この場では言えぬな。まずは郷則重にお目にかかってからのことだ」
こやつ何を言うかと思えば、我が家の家宝を見て愚弄する気だな。そのとき、猛之進の胸にある考えが浮かんだ。
「よかろう。このところおぬしも雨宮道場には足を向けておらぬであろう。どうだ、弥十郎。あの頃とまではいかぬだろうが互いに一汗掻くことにせぬか。そのときに家宝を携えて行くから見せてしんぜようではないか」
「わかった。おぬしと竹刀を交えるのも久方振りだ。で、いつにするのだ」
「そうだな。二日後ではどうだ。その日は確か、おぬしもそれがしも互いに非番であろう」
若かりし頃であるが、猛之進と弥十郎は雨宮道場で研鑽を積み、郷田の小天狗と持て囃されていた。藩内には雨宮道場の他に戸田道場が在る。郷田藩では武芸を奨励する戦国の世の気風が未だに残っており、武道を好む先は藩主茂貞の君命もあり二つの道場を構え家臣たちを競わせたのである。
その為、年に一度、在国中の藩主の前で御前試合を執り行い両道場から選ばれた数名の剣士が立ち合うのだが、雨宮道場には無論のこと戸田道場にも猛之進と弥十郎に敵う相手はいなかった。当時、二人が藩中で竜虎と目され最も技量の優れた剣士であることに疑いはなく、多少の性格の偏りはあれど門弟たちの憧憬の的であったのだ。
その日は朝から青雲相半 (せいうんあいなかば) する空模様で、風がある分少し肌寒さを覚える日和であった。