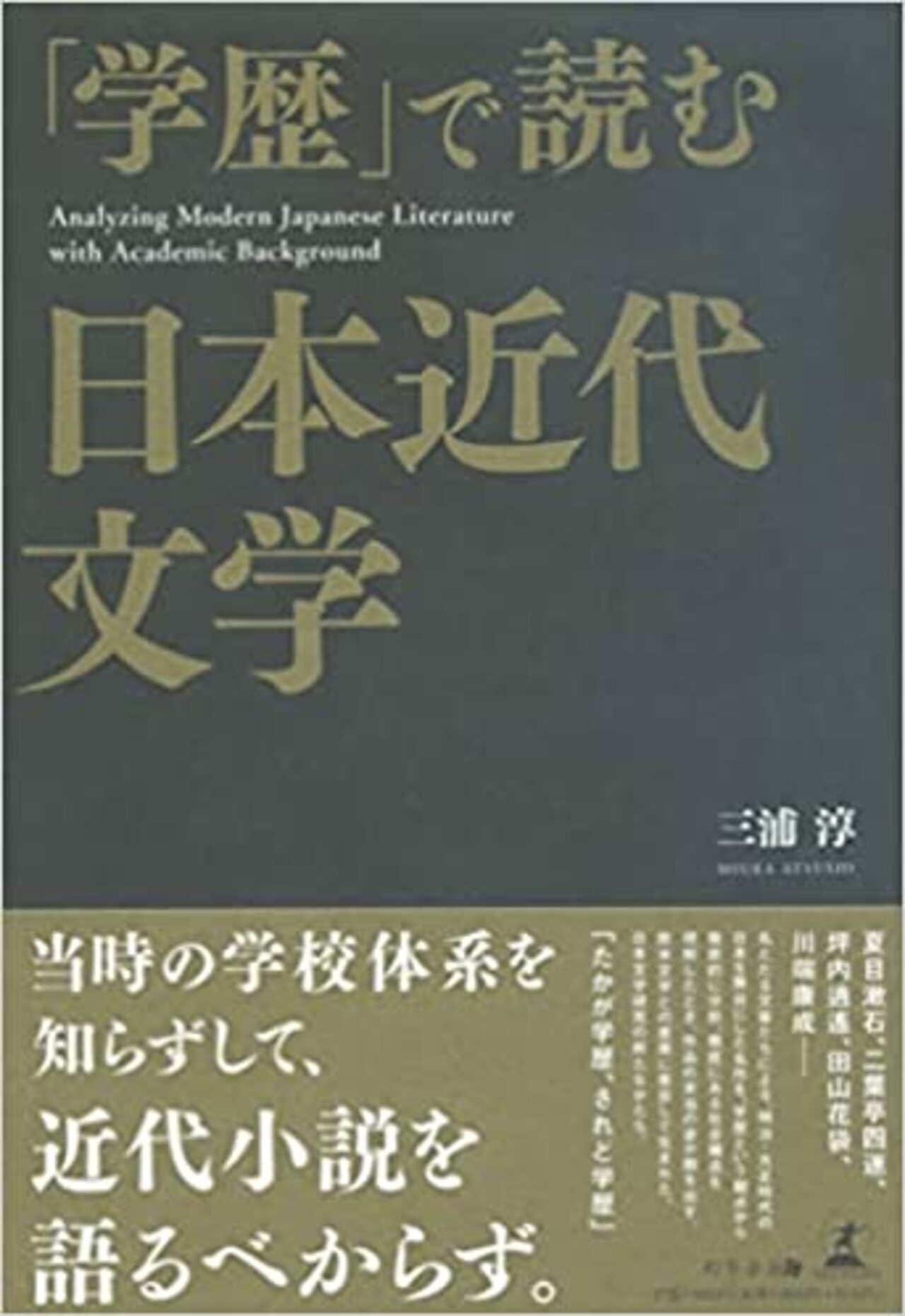第一章 日本近代文学の出発点に存在した学校と学歴――東京大学卒の坪内逍遙と東京外国語学校中退の二葉亭四迷
第二節 二葉亭四迷
■女子の学習熱
お勢は文三と二人きりで話をしているときに、自分の母に教育がないことに触れるのですが(第三回)、自分と同年配の人間でも必ずしも教育があるわけではないと言い始めて、
「私の朋友なんぞは、教育のあると言うほどありゃアしませんがネ、それでもマア普通の教育は享(う)けているんですよ、それでいて貴君(あなた)、西洋主義の解るものは、二十五人のうちにたった四人(よったり)しかないの。
その四人もネ、塾にいるうちだけで、ほかへ出てからはネ、口ほどにもなく両親に圧制せられて、みんなお嫁に往ッたりお婿を取ッたりしてしまいましたの。(…)このごろは貴君という親友が出来たから、アノー大変気丈夫になりましたわ」
と締めくくります。つまり、自分と文三は教育レベルにおいて近い位置にあるから話も合うし気も合うのだ、という含みのある発言ですね。教育は若い男女を接近させる道具でもあったわけです。
お勢が『女学雑誌』を読むシーンもあります。『女学雑誌』とは、明治一八年に創刊された日本初の本格的な女性雑誌で、明治期の女子教育者として著名な巌本善治が長らく編集人を務めました。(この人物については、野上弥生子の『森』を扱う第五章でまた触れます。)内村鑑三や北村透谷などが執筆したほか、小説などの文芸も多く掲載されました。
もっとも、お勢が新時代の学問や思想、或いは英語に真剣に取り組んでいるのかというと、やや疑問があります。後のほうではお勢が飽きっぽい性分だということが言われており、
「英語の稽古を初めた時も、(…)初めるまでは一日(いちじつ)をも争ッたが、初めてみれば、さほどに勉強もしない」と書かれているからです。(第十六回)
英語を教わることは明治時代、或る種の知的モードになっていたのでしょう。
先のほうに行くと、要領のいい本田昇が(日頃から課長に取り入っているのですが)課長の家に通って妻とその妹(課長からすれば義妹)に英語を教えていると報告するシーンも出てきます。
(なお本田は士族だとは書かれていますが、学歴については記されていません。先に引いたお勢の発言からすると、文三より高学歴とは考えられませんが、この時代に役所勤めをする人間として、一定の学歴はあったと推測されます。)