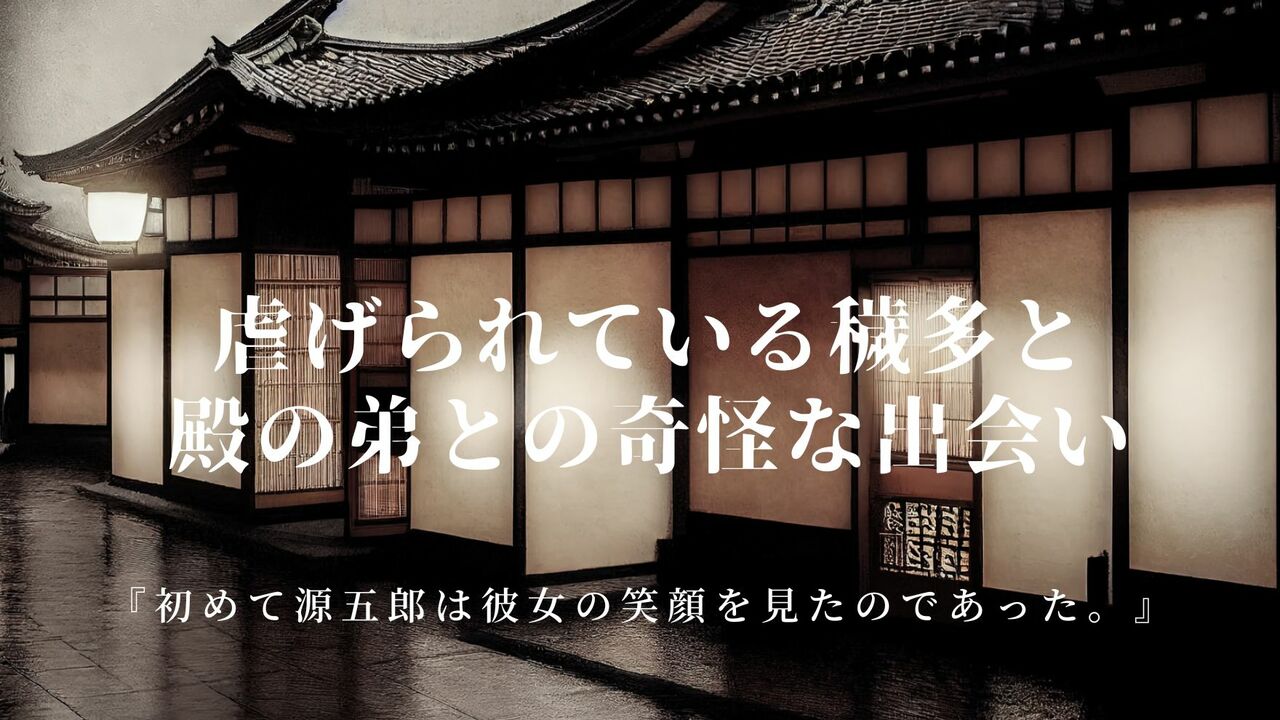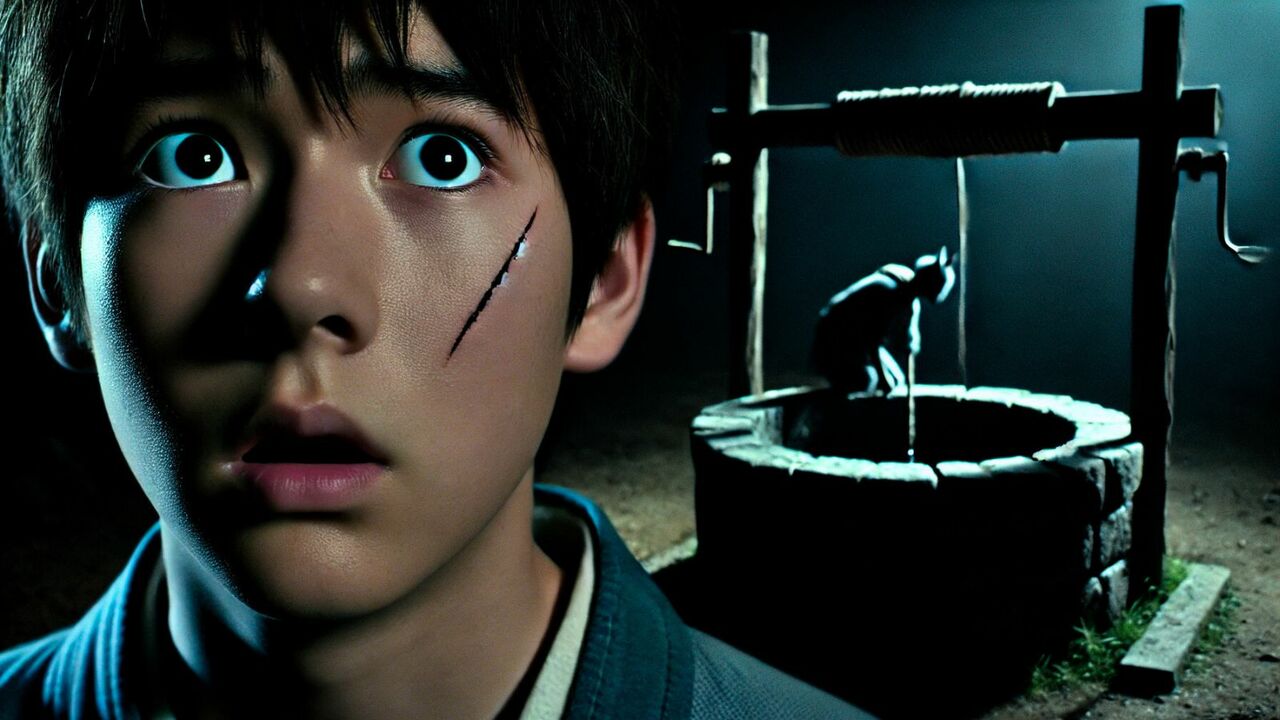【前回の記事を読む】「穢多だろうが非人であろうが、人である事に変わりあるまい」
穢多の女童
戦国時代、武士、貴族などには「官位」という肩書により、身分の上下に伴い立場や権利などに格差があったが、武士以外の百姓や漁民、商人や人足(にんそく)などの一般民衆に対しては、江戸時代のような職業による身分制度は定められておらず、職種による貴賤差別は無かったと言ってよい。
しかし穢多、非人、かわた、といった名で呼ばれている人達が存在していた。
穢れが多いと書いて穢多と呼ばれた人々は、その人達だけに許されている特殊な職業を生業として生きていた。
それは死んでしまった牛馬の解体や毛皮の加工、葬送、廃棄物処理といった血や死に関するものであるが、そのような「穢れ多い」人達に託された背景には、当時の人々が必要以上に「死」や「人知の及ばぬもの」に対して、畏れや畏敬の念を抱いていた事による。
ある家で誰かが死ねば、その家には「死の穢れ」がつき、反対に出産で新しい命が生まれれば出産の際に大量の出血が伴う為、胎児と共に母体から排出される胎盤を「胞衣」として手順を踏み、処理しなければならなかった。
この風習を「胞衣納め」と言う。
そのような死や出産で一旦穢れがつくと、それは伝染すると考えられていた為、外からも人を出入りさせる訳にもいかず、その穢れを家から持ち去ってくれたり、祓ったりしてくれる人が必要であった。
そういった神道の風習が、令和の現代でも残っている。
いわゆる「喪に服す」や「喪中はがき」「清めの塩」などである。
そのような儀式や祓いを怠れば、穢れが祓えず災難が降りかかると、本当に信じられていた時代である。
穢多は民衆から「穢れを祓い、浄めてくれる力を持つ専門家」、無くてはならない存在として必要とされる一方、その職制や皮革生成の際に発する臭いなどで、江戸時代以後の苛烈な差別はまだ無かったものの、この時代は畏怖と差別が混同する微妙な環境に、穢多の人々は置かれていたのである。
まゆを背負い歩いて来た源五郎は、河原から一段上がった場所にある集落を見つけた。
「あれか?」
「はい……」
と……源五郎達の姿を見つけた、両親と思われる二人が小屋の一つから駆け出してきた。
不思議そうな顔で源五郎に黙礼すると、頭から血を流していた娘に聞いた。
「まゆ、大丈夫かぇ?」
まゆは頷き応える。