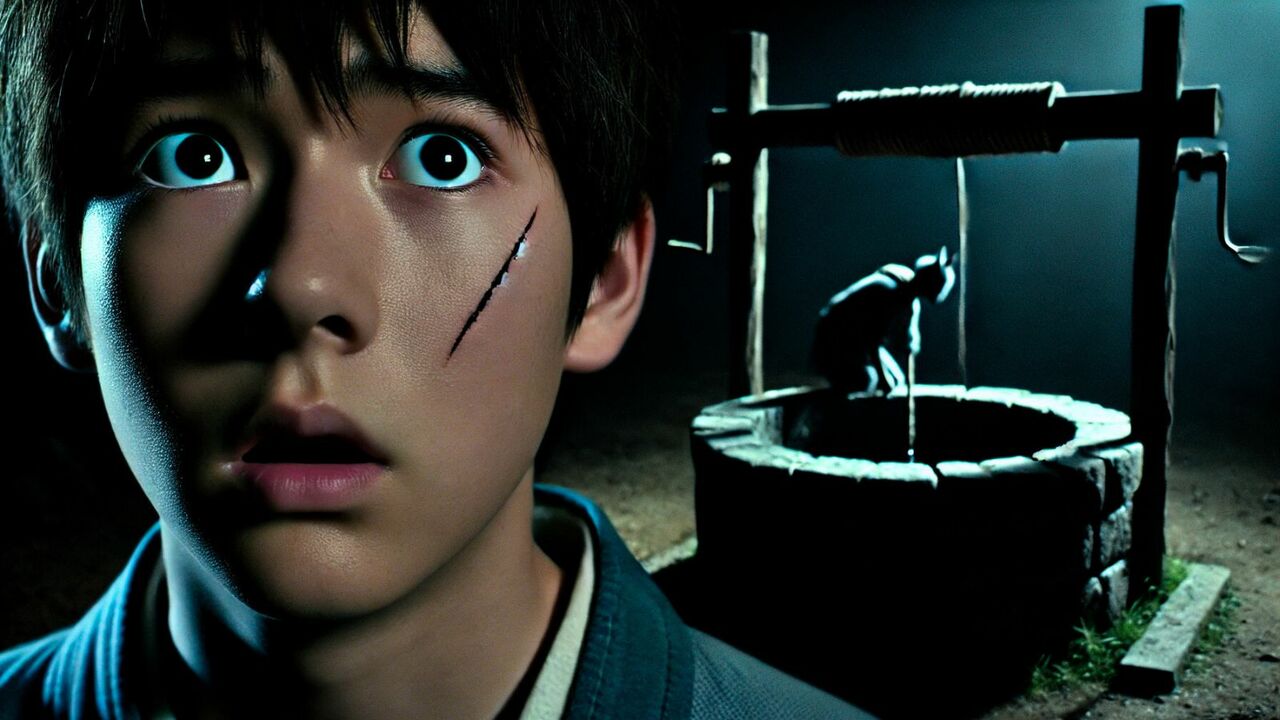【前回の記事を読む】殿である兄と対立してでも救いたい命「つき丸…頑張るのだ…」
湖上の城
翌朝、夜半に止んだ雨の雫が軒下に落ち、腰付障子から朝の光が臥所を照らしていた。顎をぺろぺろと舐められる感触で源五郎は目を覚ますと、つき丸が臥所の中で元気に尻尾を振っている。
「おぉ! 良くなったようだな、本当に良かった!」
つき丸はよたよたしながらも、自分の足で歩き臥所から這い出て来た。起き上がり胡坐をかいて座る源五郎の太腿に寄り添い、足を投げ出すように座った。その後ろ姿はどこか朦朧としていながらも、辺りを見渡している。
「精がつくように、粥へ刻んだ韮を入れてやろう」
源五郎はつき丸を抱きかかえ厨へと向かうと、くまが声をかけてきた。
「あれ、元気になりましたけ? ようござりましたな~」
「あぁ、これなれば大丈夫だろう。粥に韮を細かく刻み入れてやってくれ、まだ本調子では無い故、あまり入れぬようにな」
「へぇへぇ、分かっております」
支度を整え与えた粥を、のろのろとだが少しずつ食べるつき丸を見て、食欲の出た事に安心した源五郎は、優しく微笑みそれを見守っていた。
穢多の女童つき丸が源五郎の元に来てから数日が経ったある日。源五郎は鍛錬の為時折持ち歩いている木刀を手に、つき丸を連れ城の周りを散策していた。つき丸は仔犬の足で何とか源五郎に追いつこうと、一生懸命ついて来る。その愛らしい姿を振り返り確認しながら、気ままに歩を進めた。