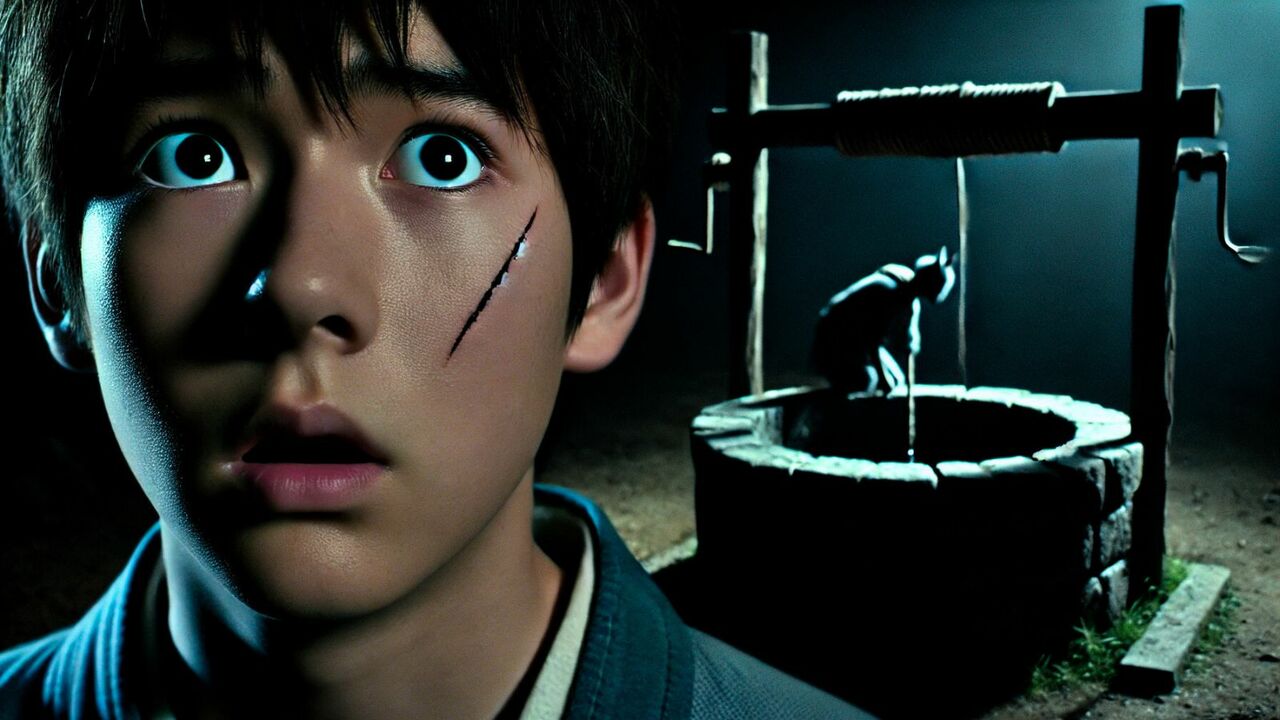湖上の城
突き抜けるような青空に大きな入道雲が浮かび、湿った生暖かい風には夏草の匂いが溶け込んでいる。見渡す限りに葦や蒲が生い茂り、巳の刻半の葦原を渡る風が優しく穂を揺らした時、微かに遠雷が聞こえた。
深藍の小袖に褐色の袴と、武家の出と分かる小童が湿地の一本道を歩いている。
鼻筋の通った意志の強そうな目元と眉が印象的な、一人歩くその小童の足取りはどこか寂しそうだった。その小童の足元を、まだ歩くのも覚束ない梅染色の仔犬が必死になってついて行く。
仔犬の足音に気が付いた小童が振り返ると、一間ほど空けて仔犬が足を投げ出すように座り、小童の目をじっと見て小首を傾げた。その姿からはまだ座る事すら慣れていない、仔犬のあどけなさが見て取れる。
「何だ? どこからついて来た? ……早く母の元へ帰れ」
小童はすげなく仔犬に言った。
しかし、小童が再び歩き出すと、仔犬はまた必死になってついて来る……。
足音でそれを感じていた小童は立ち止まり、青空を見上げ大きく溜息をついた後、しゃがみ込み仔犬に手を差し出した。仔犬は嬉しそうに尻尾を振りながら小童の手に身を預け、ペロペロと小さな舌で舐める。
本来であれば、母の乳をもらいコロコロとした愛らしいふくよかな姿になる筈だが、その仔犬はあばらが浮き、どこかフラフラしていた。
明らかに滋養が足りていない事が分かる。
「お前も母を亡くしたのか?」
小童は仔犬に話しかけた。
このままこの仔犬を見放しては、餓死してしまうだろう事は明らかだった。暫く仔犬をあやしていた小童は、母を亡くした同じ身の上のこの仔犬がとても不憫に思えてきて、放っておく事が出来なくなってしまった。
かなりの間考えていたが、何か吹っ切るように、「俺と共に行くか?」と言い、仔犬を抱きかかえると歩き出した。
仔犬は嬉しそうにパタパタと尻尾を振り、その小童の若々しい顎を舐めようとしている。そんな仕草に心癒されたものか、小童は笑顔になり蒲の黄色い雄穂を何気なく手に取ると匂いを嗅いだ。仔犬は何を嗅いでいるのか? と興味津々に首を伸ばし鼻面を寄せて来る。
「蒲の穂だ」
目元を緩めながら、まるで人のように話しかけた。
とその時……片手に仔犬をかかえていたせいか、小童は湿地に足を取られよろめき、蒲の林に倒れ込んでしまった。
蒲をなぎ倒す音が原に響いた時、蒲の原から多くの鴇が一斉に入道雲の空に飛び立った。
それは一瞬、夕陽を思わせるほど空全体を鴇羽色に染め上げ、その美しさと儚さに今は亡き母を思い出し、小童は暫くの間そのまま眺めていた。