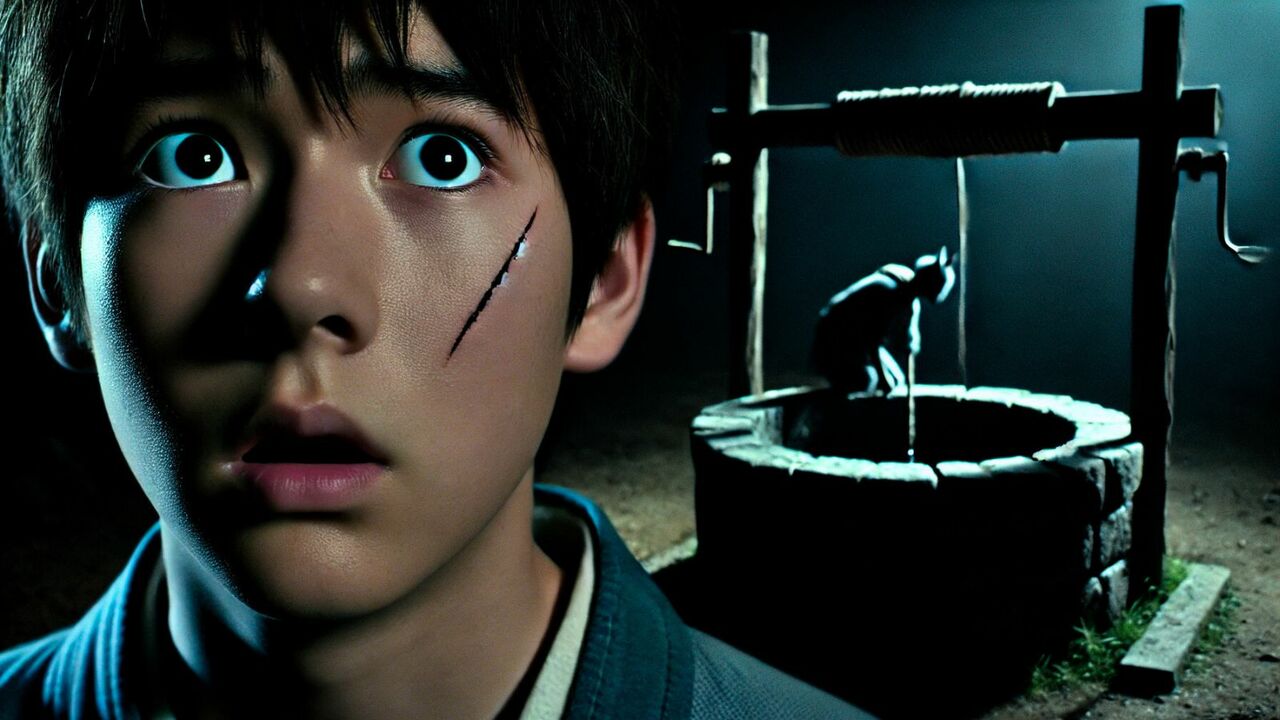「このお人が助けてくれました」
父親は源五郎のいでたちを見て、どこぞの武家の小童と察し、
「これはこれは、娘が難儀なところをお助け頂き、有難うございました……。父の善右衛門でございます」丁重に礼を言った。
「いや、礼には及ばぬ」と言いながら、まゆを背から降ろす源五郎と足元の彼になつくつき丸を見て、源五郎の人となりを想像できた母親が、
「みすぼらしい小屋なれど、どうぞお礼の一つでも差し上げたく存じます。お立ち寄り下さいませぬか?」と家に招いた。
「よいのか?」源五郎は初めて見た穢多の家に興味を持ち、立ち寄る事に決めた。
父親のほうも、娘を助けてもらった事をたいそう感謝している様子で言った。
「えぇ、是非ともお寄りになってくださいまし」
家の前には稲木を大きくしたような物があり、獣から剥いだであろう毛皮が干されている。
小屋の中は大きな土間と仕切りの無い板間があり、その板間の真ん中に囲炉裏があった。
板間の囲炉裏横に源五郎を招き入れると、吊るされた鍋から野菜汁らしき物をよそい、
「つまらない物ですが、よろしかったら……」すまなさそうに差し出した。
それは大根や菜っ葉、肉を入れ煮たものだった。
なんの躊躇もなく源五郎は一口すすり、
「美味い、これは猪の肉か?」
「へぇ、お口に合いますかどうか……」
「あぁ、美味い」屈託なく言う源五郎に安心したものか、人柄に好意を持ったものか、
「我らはこのような革作りを生業として生きております」と語り出した。
「あなた様はもしやすると……太田資顕様所縁(ゆかり)のお方でございますか?」
「あぁ、弟だ」
善右衛門は妻の「よし」と顔を見合わせると、
「これは……知らぬ事とはいえ、とんだ御無礼を致しました」まゆ共々土間に平伏する。
「やめてくれ、俺は太田の家では厄介者よ、そのようにするに及ばぬ」
「へぇ……」
「さぁ、みな上がってくれ」
源五郎が板間に上がるように促すと、善右衛門は恐る恐る板間に上がりながら、殿の弟君である源五郎の飼い犬、つき丸も板間に上げたものだ。
そのつき丸を、まゆが愛おしそうに抱いた。
可愛くてたまらない、といった感じだ。
つき丸も嬉しそうに尻尾を振りながら、まゆの顔を舐めようとしている。
その時、初めて源五郎は彼女の笑顔を見たのであった。