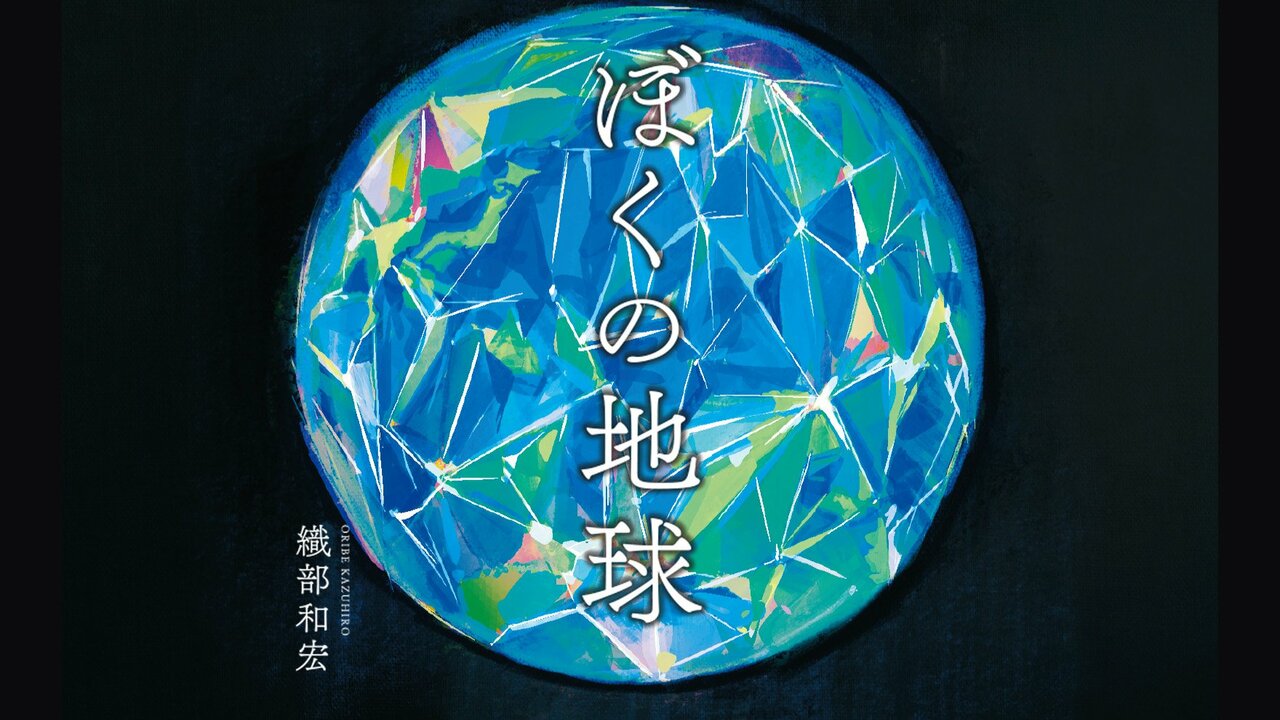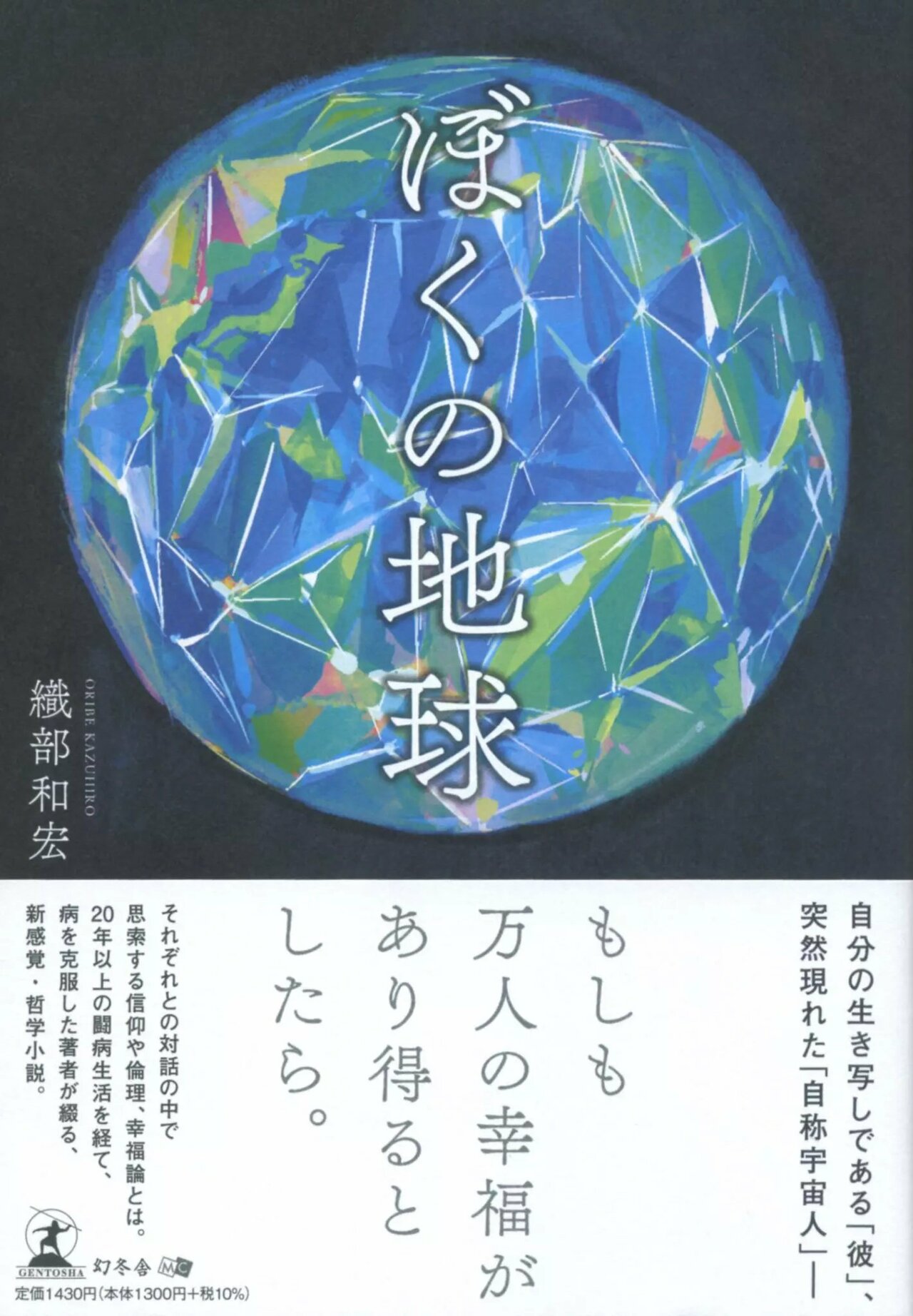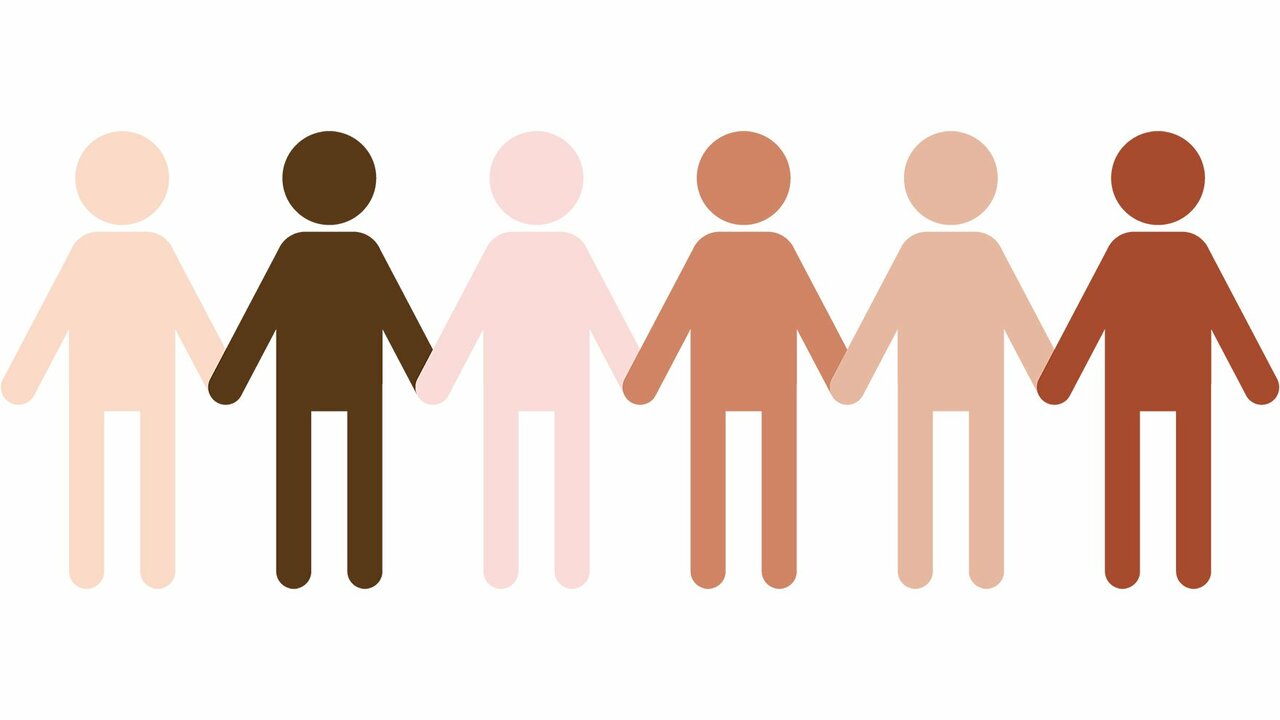ぼくの地球
第一章 目覚め 春
凪
彼が語る愛についてはまだここで触れる必要はあるまい。
その前にアイデンティティーについて語る必要があるのであろう。すでに、青春の第一の意義は、アイデンティティーを見つけることにあると書いたが、アイデンティティーは、個の確立という点でも決して外すことのできない概念である。そこでは、排他的な絶対自我が、社会の単一的基準という、本来個の人生の基準とは別物でしかないものに自己決定権を大幅に侵食されることに警鐘を鳴らしている。
ここは強調しておかなければならない場面であろう。彼は個性がそれに相応しい地位を得るには、善という要素を担保にして、社会の単一的基準、言ってみれば世間体のようなものに対抗しなければならないと考えているのである。すでに、個性とは存在のことだと書いた。
また彼は、一定の条件の下では瞬間は永遠とつながっており、今という瞬間を切り取り続けることが個の確立という点では不可欠である、と考えている。だが、それだけでは善が必ずしも担保されないので、この後述べる、私と彼との共通点が、彼を孤独であるにもかかわらず、その認識において社会の単一的基準に対する絶対優位性を、彼に確認させ続けているのである。
彼は言う。
─ぼくは特別な人間だ。
だから特別な責務を負うのである。彼のこの言葉は、言外に、明らかに、人類が抱える普遍的な問題と今を生きる人々だけが抱える局地的、及び時代的問題とのその両方に共通する部分を包含している、と断ずることができる。
彼は自身を絶対と見做すことで、迷いの極小化を常に図っている。ここは、理性の情念に対する優位性を不動のものにするうえでも欠かせない試みだが、ともすると排他的でしかない個の確立に善的な普遍性を持たせるためにも、彼は自身の行為に公共性を持たせようとしているようだ。ここでは「利他」をキーワードにすることもできるであろう。
個性を軽視し世間に埋没した場合、日常に溢れかえっている不都合はすべて意味を失う。彼はそれをひどく恐れているのだ。彼は、不都合のすべては肯定されるべきものであると考えている。だがそのためには、負はすべて意味を持つと見做さなければいけなくなる。負がすべて意味を持つならば、彼も私もその瞬間、後悔と逡巡から解放されることになる。ではそのために私たちは何をすればよいのであろうか?