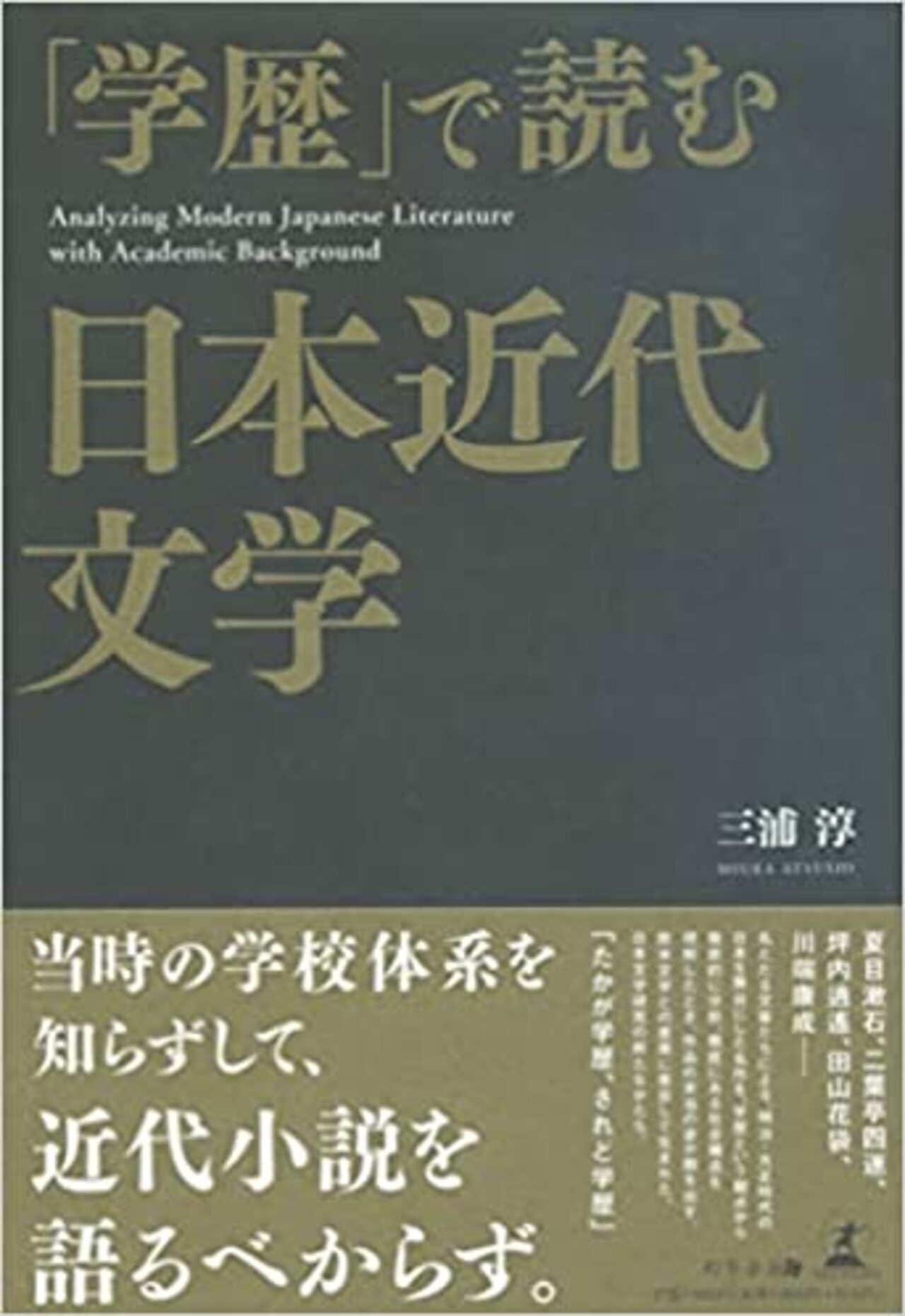■作中に出てくる東京大学以外の官立高等教育機関
作中、他校の話題も、先に引いた「東京大学にならってboat-raceでもはじめれば」以外に、わずかですが出てきます。第十一回で継原という学生が学校を退学になったという話が出て、退学後どうするつもりかが問題になるのですが、そこで小町田という学生が「工部へ入学とか言っていた。彼には工部は不適だ」と言う場面があります。
工部とは、工部大学校のことです。明治六年(一八七三年)、中央省庁の一つである工部省(現在の国土交通省)が技術者の養成を目的に工学校を設置しました。そして四年後の明治一〇年に工部大学校と名を改めます。授業は多く外国人の教員が担当し、ほとんどが英語で行われ、全寮制をとっていました。そして明治一八年(一八八五年)に工部省の廃止にともない文部省に移管され、翌明治一九年に東京大学と合併して帝国大学工科大学(現在の東大工学部)となるのです。
つまり『当世書生気質』の時代設定である明治一五年頃には工部大学校は東京大学などと並ぶ高等教育機関だったのであり、建築家の辰野金吾など、明治時代の日本を工学技術の面で支えた多数の人材を輩出しました。
面白いのは、工部省の学校を立ち上げるに際して助言を行った英国人教授は、もともとは母国のグラスゴー大学に工学部を設置しようと構想していたのが、実現せずに(グラスゴー大学に工学部ができたのは一九二三年。ただしそれ以前から工学教育はなされていたようです)、代わりに日本で実現したという経緯です。
欧米では長らく工学教育は理学や医学や法学などの学術とは異なる実用目的と見なされ、ユニヴァーシティ(総合大学)ではなく別の教育機関で行っていました。英国ならインスティチュートや(ユニヴァーシティの一部ではない高等教育機関としての)カレッジ、フランスならグランゼコール、ドイツならホーホシューレです。
米国の有名なMIT(マサチューセッツ・インスティチュート・オブ・テクノロジー)がユニヴァーシティではなくインスティチュートなのも同じ理由からです。明治一九年(一八八六年)という時点で総合大学の一部に工学部門が取り入れられた日本は、欧米先進国に追いつくためという目的からではありましたが、工学を医学や法学と同じレベルで遇する点で時代の先端を行っていたわけです。