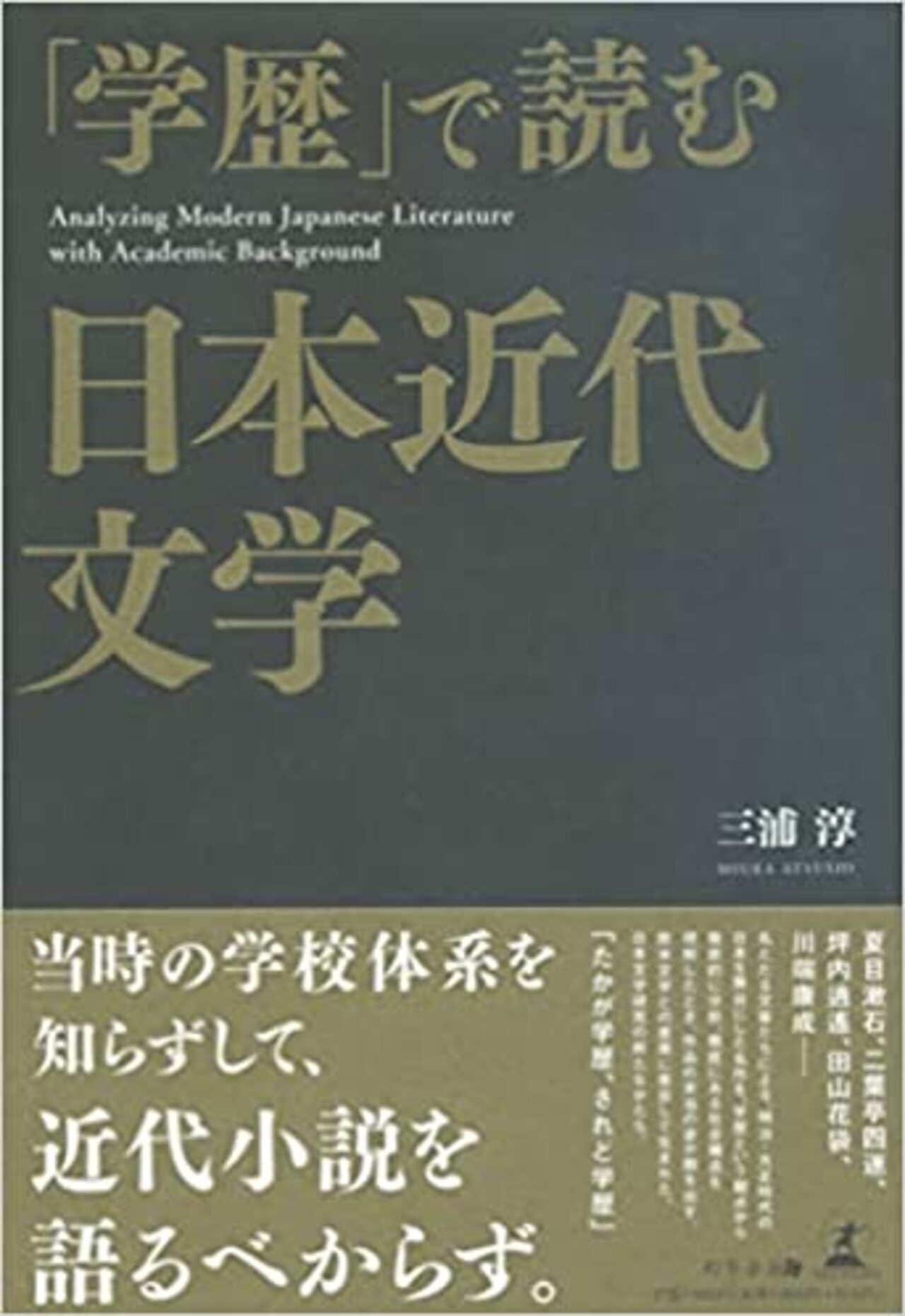【前回の記事を読む】東京大学と並ぶ高等教育機関であった工部大学校…立ち上げの経緯とは
第一章 日本近代文学の出発点に存在した学校と学歴――東京大学卒の坪内逍遙と東京外国語学校中退の二葉亭四迷
第一節 坪内逍遙
■作中に出てくる東京大学以外の官立高等教育機関
ついでに、明治初期に司法省の管轄だった法学校についても触れておきましょう。
明治四年(一八七一年)に司法省は明法寮を、フランス語とフランス法の教育研究を目的として設置しました。翌明治五年、第一期生が入学。明法寮は明治八年(一八七五年)に司法省管轄の法学校となります。教育はフランス人により行われました。翌明治九年に第一期生が卒業し、第二期生が入学します。つまり、第一期生が入学した後は学生をとらず、四年後に卒業した時点で新たに学生を入れているのです。
しかも、この明治九年に法学校は八年制となり、前半四年がフランス語など基礎教育、後半四年が専門教育となりました。ただし学生の入学は変わらず四年ごとで、第三期生は明治一三年に入学しています。明治一七年に文部省に移管されて東京法学校と改称し、さらに翌明治一八年に東京大学法学部仏法科となるのです。
■学校を描かない『当世書生気質』
話を『当世書生気質』に戻しましょう。この小説には細かく見ればたしかに明治期に生きる書生の風俗は描かれてはいます。しかし書生小説としてきわめて不十分と感じられるのは、肝心の学校がほとんど出てこないからなのです。学生が飲食店で議論をしたり、同級生の下宿に転がり込んで内密な話をする場面によってこの作品は構成されています。
勿論、学生がそうした行動をとること自体はいつの時代にもあることです。しかし「書生気質」というタイトルを持つ小説である以上、書生が通っている学校についての具体的な描写は欠かせないはずです。授業の模様や教授の外見や気質、試験、図書館での調べ物や自習、或いは講義室を離れての教授と学生の人間関係、授業料納入その他の必要から行う事務員との交渉などなどは、学校を舞台とする小説には必須のアイテムでしょう。ところがこうしたものがこの『当世書生気質』には出てこないのです。
この作品の根幹をなす筋書きは、生き別れになっていた兄(守山友芳)と妹(田の次・お芳)の再会という、言うならば江戸期の世話物めいた話なのです。他方、お芳と一時期恋仲になる小町田という学生も登場するのですが、遊興に溺れていると学校からは見なされ、休学扱いにされてしまいます。(第十一回)
それでどうなるかというと、結局自分の将来のためにならないというので、小町田はお芳と縁を切ることに決めるのです。第十七回では友人たちが二人の関係がどうあるべきかについて議論をする場面はありますが、肝心の小町田とお芳の二人がこの問題をどう考えているかについての詳しい描写はありません。
しかも肝心の二人の心理を描写するのではなく、友人たちが外側から見た二人の様子などにより話が進むのです。そういう技法を使う場面もあっていいでしょうが、近代小説と称するからには恋をする二人に直接肉薄するのでなければその実は達成されません。
以上の点からして、『当世書生気質』が近代小説としての特質を備えているとは到底言えないことは明らかでしょう。
むろん以上の批判は西洋近代小説やその後の日本近代文学の展開を心得た人間の視点によるものであり、逆に江戸期の文学から見れば、人物描写などには西洋から学んだ技法がそれなりに取り入れられているという見方もできるでしょう。
しかしちりばめられた西洋の書物名や人物名などの知識に比べて、人間関係やその描写が古色蒼然たるレベルにとどまっていることは、現代の人間にはもとより、おそらく大正期の人間から見ても明らかだったと思われるのです。