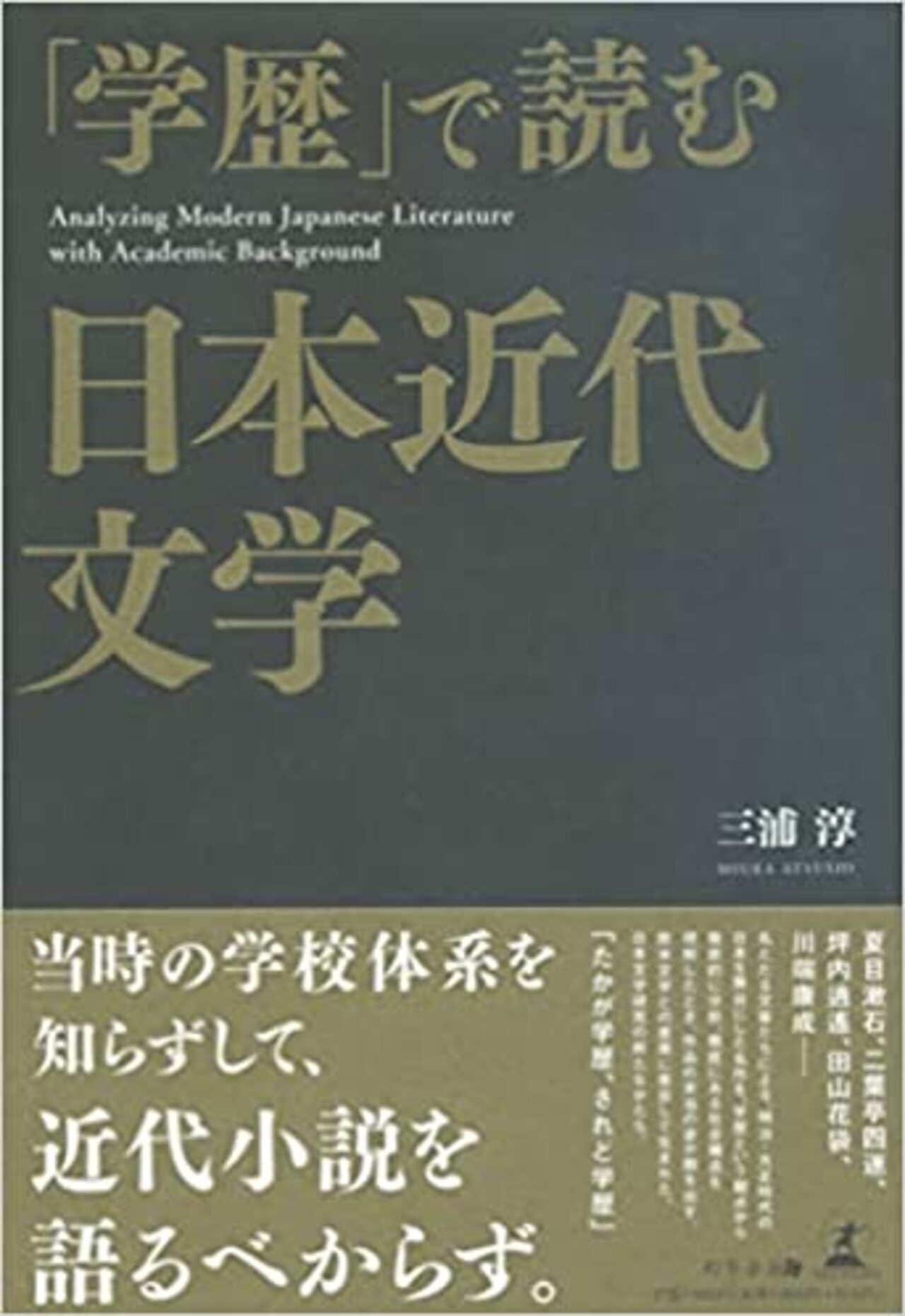■『当世書生気質』で今も読むに値する場面
この小説で最も学校というものに肉薄している箇所は、おそらく第十九回に登場する英国大学論でしょう。任那という学生が宮賀という学生に手紙を出して英国大学論をぶつのですが、その内容が読み上げられるという形で紹介されています。
任那はまず、東洋文明は西洋文明に比べてひどく遅れていると述べて、明治一五年頃の、つまり「文明開化」がモットーだった時代の日本人の認識をまず示します。その上で、大学にも彼我の差がかなりあるが、英国の大学にしても歴史が長いから立派になったのであり、東京の学校もあと二〇年か三〇年経てばそれなりのレベルになるだろうと述べるのです。
そして、英国のオックスフォード大学でも昔はひどかったということは、何冊かの本を読み学友の話を聞けば分かることだとして、以下のように英国大学の欠点を指摘します。
かつてのオックスフォード大は富裕な良家の子弟が多く、大学はそうした若者の集まるクラブのようなものだった。権勢のある富豪が息子をこの大学で学ばせるのは立身出世の便宜となる人脈ができるからなのだ。たまたま貧しい生まれの者がこの大学に入ると貴公子の玩具となり、嘲侮されることも多いらしい。富裕な学生と貧乏な学生とは食べるものも服装も異なっている。学生と女性との情事も珍しくなく、田舎の別荘に妾を囲っておく者までいた。
スポーツが盛んなのはいいが、そのために勉学がおろそかになりがちで、或る博学な人物がオックスフォード大を訪れて学生を観察し、この学校が哲学人をあまり生み出さないのは、食物を大量に喰らって筋肉をつけることばかりに意を用いているからだろうと指摘した。