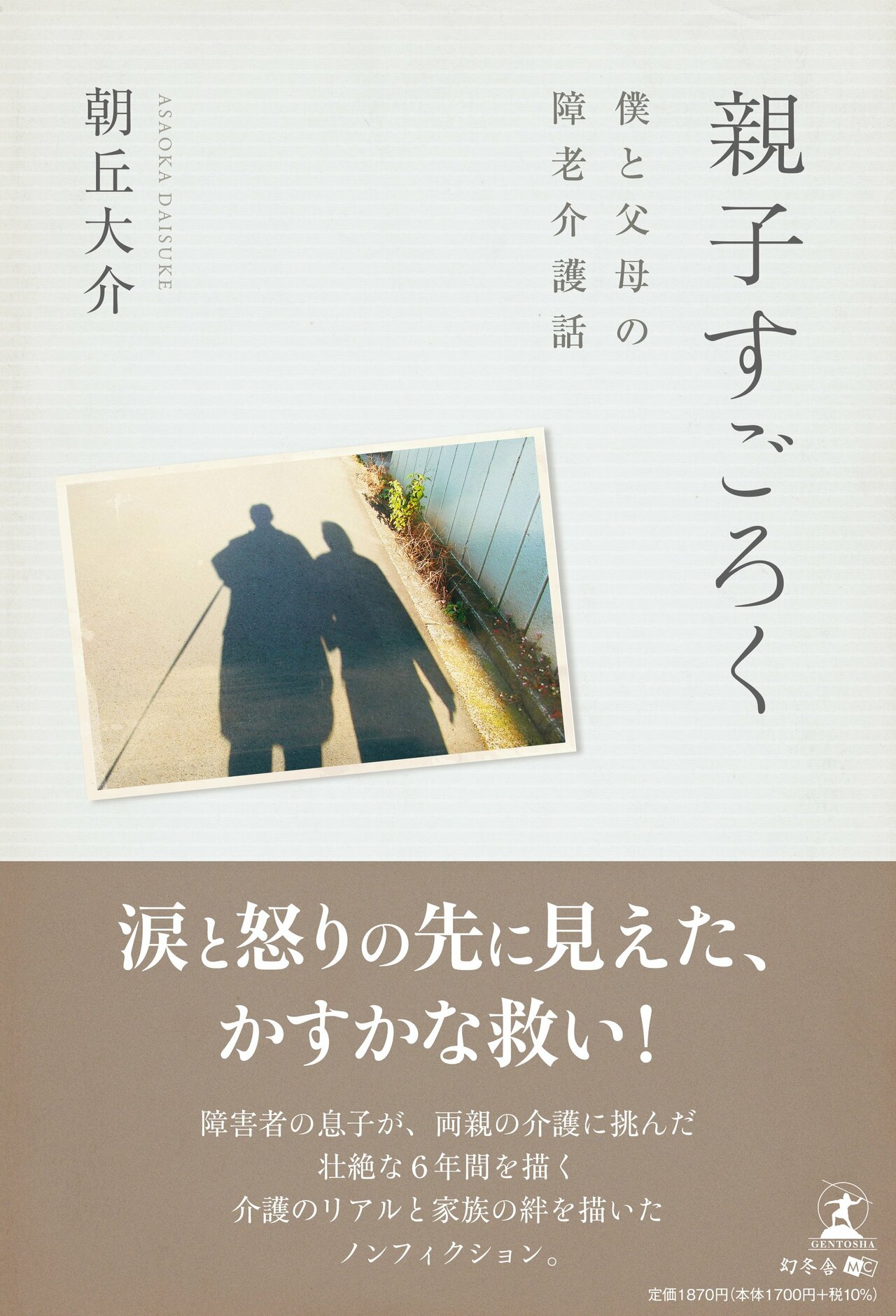リセット
それまでは、
「年とっても絶対若いままだね」
と、僕は人に言われてきた。精神年齢が幼かったせいか、年相応の威厳がないせいか、いずれにせよ童顔の僕は、三十代に入ってからも二十代前半と間違われ、実年齢を言うと驚かれた。
キたのは、昨年の四月からだ。僕は、横浜の小さなクリニックで理学療法士をしていたが、あるとき、同じ病院施設グループのパーティーで他所の事務長から話があった。今度、新たに老人保健施設を立ち上げるから来てほしいという。百五十床という規模の施設だが、リハビリに関しては、僕のほかに作業療法士が二人入るというので、僕は話を受けることにした。
ところがいざ契約をすませ、現場へ行ってみると、作業療法士の姿はなく、代わりに来ていたのは言語聴覚士二人のみ。病院ならまだしも、そこの施設では、言語聴覚療法の対象者は三十人にも満たず、残りの入所者と通所利用者を実質一人でみろと言っているようなものだった。冷静に考えて、不可能なことだった。事務長に相談しても、
「だってオレ、リハビリのことはわかんねーもん」
と耳を貸そうとはせず、それでも折衝の末、週に三回、救援スタッフが来ることになった。
いざ施設がオープンすると、事務サイドは、わずか一か月で百五十床を満床にすることを現場に要求してきた。普通、百五十床ともなれば半年ぐらいかけて満床にするものだが、施設の新記録をつくるのだと、看護度の高い患者を次々と入所させていった。
朝昼晩フル稼働。言語聴覚士たちが涼しい顔で夕方六時に帰るのを尻目に、僕は毎晩夜が更けるまで働いた。施設にとって何もかもが初めてだったので、まずはカルテの記載フォームや必要な小道具から作成し、リハビリ器具の選択や設置位置、利用者をどの順番で訓練していくかといった取り決めから行っていった。
勝手にリハビリ委員の委員長にされ、他所の施設の評判を気にする看護部長の命令で、いやいや勉強会を開かされた。
「この忙しいときに勉強会なんて、超うざい」
「やだよ面倒くさい」
「リハなんて、いらない」
「なんで、アタシたちがこんなことにつき合わなくちゃいけないわけ?」