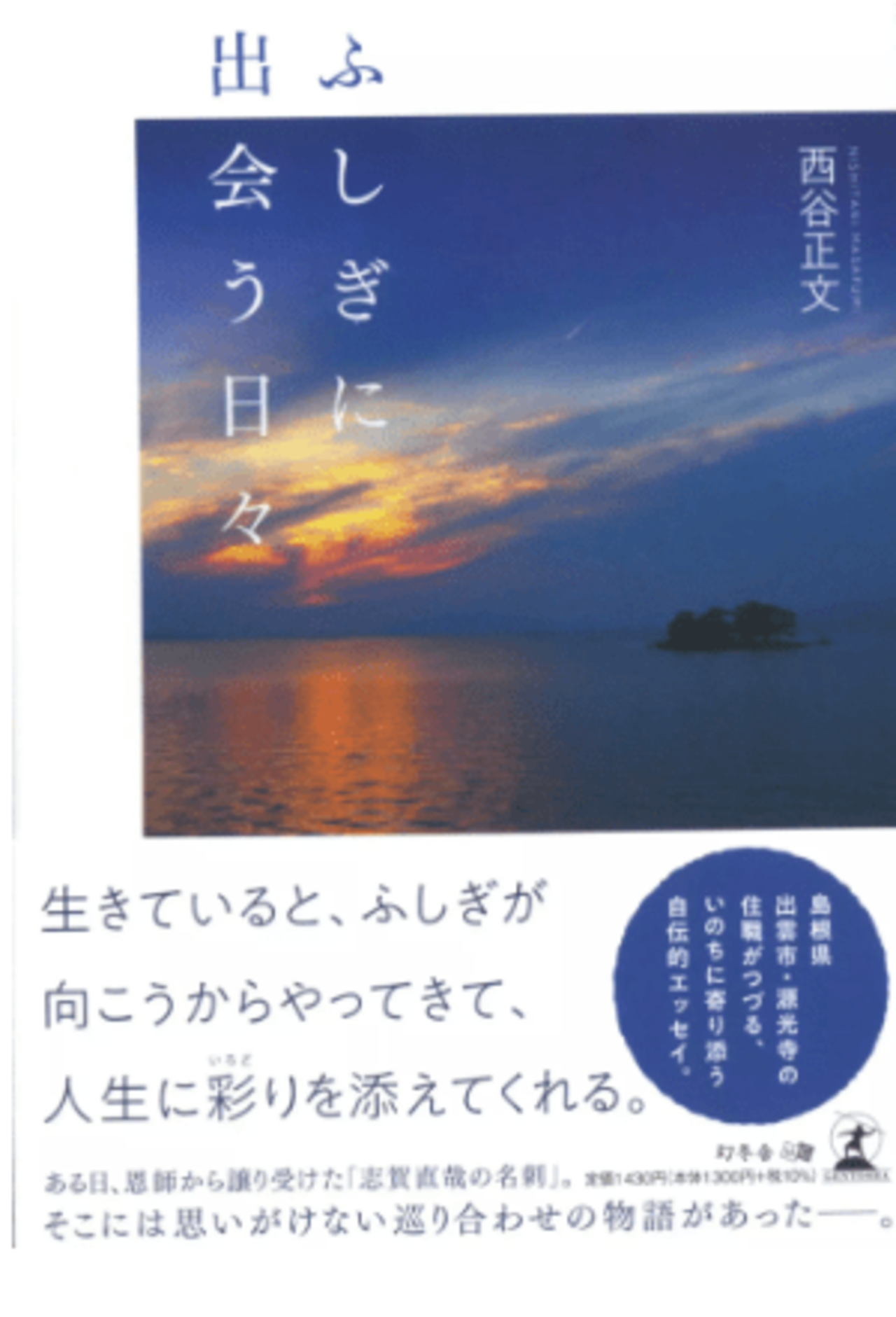宍道湖岸に面した松江市の東隣に安来市があり、島根から県境を越えて鳥取に入ってさらに南東に進むと、中国地方では最高峰の大山の裾野が広がっていた。大山は、志賀の唯一の長編小説『暗夜行路』最後の舞台で、先生からは、この小説が大好きだ、と聞いていた。主人公の時任謙作が夜間、大山の頂上を目指す途中で体力を消耗し、半覚醒の状態にあったところで、こんな情景描写がある。
彼は膝に臂を突いたまま、どれだけの間か眠ったらしく、不図、眼を開いた時には何時か、四辺は青味勝ちの夜明けになっていた。星はまだ姿を隠さず、数だけが少くなっていた。空が柔かい青味を帯びていた。それを彼は慈愛を含んだ色だと云う風に感じた。
山裾の靄は晴れ、麓の村々の電燈が、まばらに眺められた。米子の灯も見え、遠く夜見ケ浜の突先にある境港の灯も見えた。或る時間を置いて、時々強く光るのは美保の関の燈台に違いなかった、湖のような中の海はこの山の陰になっている為め未だ暗かったが、外海の方はもう海面に鼠色の光を持っていた。
時間帯は違ったが、これと同じ景色を眺めることができるような場所にお連れして、ゆっくりとご覧いただいた。先生は日本山岳会の会員でもあるアルピニストで、抱影と同様に山が大好きだった。
翌日はきれいに晴れあがっていた。大山は姿がきれいだといって、スケッチもしていただいた。その間、私は少し離れた草むらに腰をおろし、浮かんでいる雲を眺めていた。
「お~い、雲!」
と呼びかけるヘルマン・ヘッセの詩を思い出しながら、至福の時を過ごした。
先生は絵心ももち合わせていて、個展を開くほどの腕前があった。大学公式発行の三田キャンパス内の建物を描いた絵葉書も、先生の手によるものだった。志賀、(豆子)、抱影、先生、そして私が絡まりあった時間と空間を過ごすことができた。一枚の名刺は、このときの記念として、ありがたくいただくことにした。
私も一枚の名刺のわき役になることができたのだった。主役は、なにも人間だけがなるのではない。一本の木が主役だったり、一匹の犬が主役だったり、小さな石ころが主役だったりすることもある。そこにわき役が絡まってきて、一つの物語ができあがってくる。生きるとは、ふしぎが紡いでくれるドラマだと、味わうことができる。
註
第一章をご理解いただくためには、石田五郎著『星の文人野尻抱影伝』(中公文庫)と野尻抱影著『星まんだら』(徳間文庫)をぜひご一読いただきたい。
もう一つ、志賀直哉の生涯を知るうえでは、阿川弘之著『志賀直哉上・下』(阿川弘之全集第十四巻・第十五巻新潮社)を参考にした。私は志賀と抱影はとても親しく交際していたと受けとめているのだが、この評伝のなかには、抱影の姿が出てこない。
ただ一か所、本文でも紹介したように、抱影が志賀に伝えた話が「いたづら」という小説になり、さらに映画にもなっていて、この映画についての「『いたづら』を語る」座談会が開かれ、そこに出席した者の一人として野尻抱影の名前が記載されているのみである。志賀の門人であった阿川にとって、抱影はそれほど重要な人物ではなかったのかもしれない。