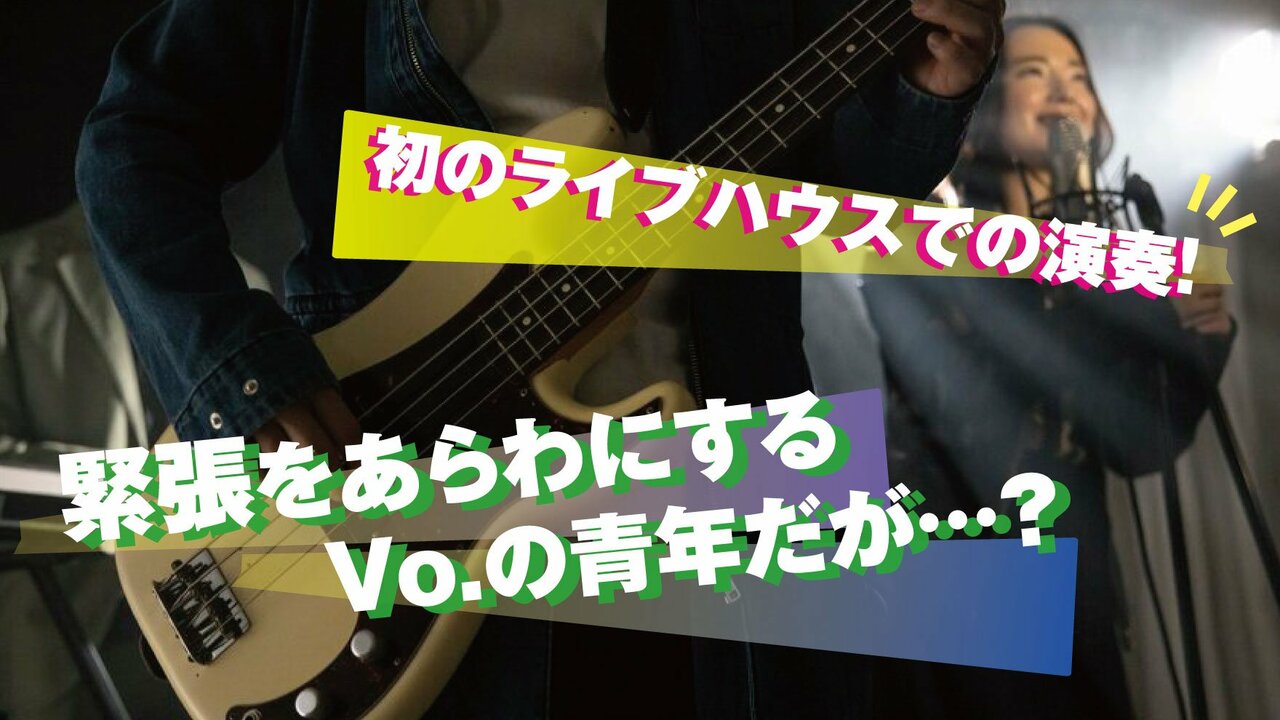11 艶麗
まどかな日の光に紫君子蘭が風にたゆたい、渡ってきたばかりのオオルリやメジロの囀ずりが、街にもそこはかとなく艶麗に響き、小気味良く感じる5月、サヤカはいつものように最寄駅に向かって歩いていた。サヤカのなかでは、凡庸とした心持ちの今日であった。
サヤカはルックスもそうであるが、醸し出している雰囲気や発しているオーラのようなものが人目を惹くほどに、瀟洒なのである。カジュアルからはじまり、コンサバ、トラッド、モード、フェミニン、マニッシュ、ビッグシルエット、ノームコア、ミニマルなど気分に応じて、何でも着てしまうし、頓着がないサヤカではあるが、どんなスタイルでも着こなすことができてしまう。
サヤカ自身としては、そのときの自分に、素直に、正直にファッションを楽しみたいだけで、別段そこまでのこだわりを有していない。街を歩けば、ファッション誌からもモデルのオファーが幾度となくあったが、全てこのようなことを言って断ってきた。
「ありがとうございます。お気持ちは嬉しいのですが、わたしには、わたしなりのモットーやタイミングがありますので」
そうしてサヤカは街のなかを颯爽と立ち去っていく。
サヤカの最寄駅は大学に近く、スグルにとっては途中駅であり、スグルが途中下車をして、改札口まで向かい、合流することも少なくない。サヤカはいつも少し早めに出発し、駅カフェを利用して、そこで授業の予習をしたり、軽くネットサーフィンをしたり、何かと将来の為の勉強をしている。
サヤカは漠然として、将来何か、全身全霊で尽くせる職業に就きたいとは思っているが、これといった明確な目標が立っていない。それを探しに大学の4年間を過ごすつもりでもある。
もちろん、高校までやっていたダンスという選択肢もあるが、あえて違うベクトルを持って、せっかく生まれてきた世界というものを見たくなったのだ。
しかも、ダンスはもう魂にその楔が打ち込まれているから、何をやっていても、何をやっていなくても、自然とサヤカのなかで、生きて根付いたものとなっている。これは、良い意味で、今世のサヤカのアイデンティティーやスブスタンティアとなり、財産となっている。
ダンスを行うという段階から、ダンスの生活習慣へのアプローチの段階まで到達している為、ある意味で高度な技術なのかもしれない。そういう意味では、何をしているときでも、ダンスの延長線上であるが、なるべく、それすらも忘れて没頭できるもの、無我夢中になれるもの、ダンスが表だとしたならば、その裏側にあるものを探しているのだ。