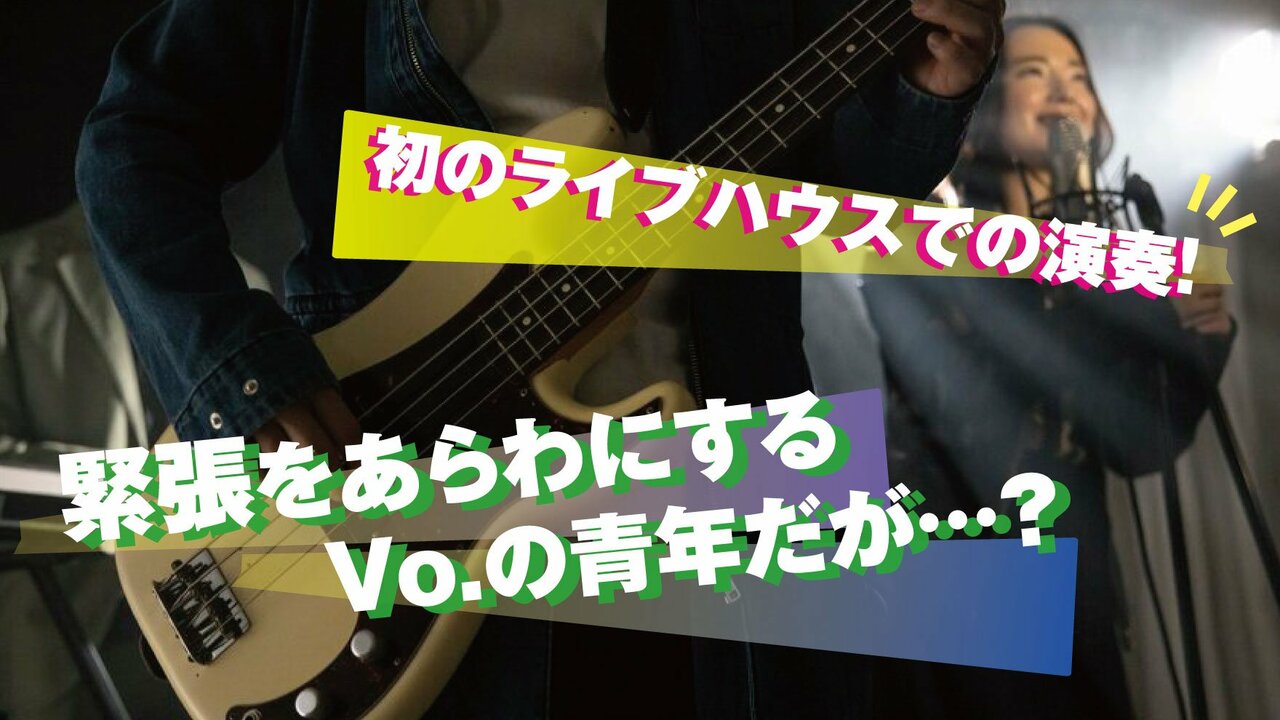1 的皪
「ねえ、ちょっとこっちにおいでよ」
「お、お、」
「音がするの」
「何の?」
「マカロンマカロン」
「へ、」
「嘘、パープルメロン」
的皪(てきれき)とした日が差し込む庭で真珠のような光が散らばり、その一つ一つが天地にあらせられる色彩美というべきか、そのような力を帯びて、相互に反射し合っている。雨がそこかしこでぱらぱらぱらと降っているなか、サヤカはスグルを手招いている。スグルは少しばかり、もう命は亡くなってしまいそうな気がしていたのだが、そういった事をサヤカの執拗(しつよう)なまでに感じてしまう天真爛漫さで、一時的に救われるような気持ちになった。
「あ、じゃあ」
「ほら、もっとこっちこっち」
「うお」
「ね、もう濡れてしまえば、こっちのものよ」
雨やどりをしていたはずのスグルはあっけらかんとなって、新しく買ったパーカーを濡らし、綺麗に使っていたスニーカーを黄色、緑の草の色や泥で染めていった。小さなことに囚われ過ぎていたのかもしれない。木の梢ばかりを見つめていて、薫りを楽しんでいたつもりだったけれども、一度、もはや大海のような森というものを見つめてしまっても、いいのではないだろうか。
泥んこ。元々、器用ではないのだけれども。それにしても、この柔らかな手の温もりはなんな・ん・だ!
「膝をもっと上げて、そうしたら、自然とこのダンスに調子が出るわ」
サヤカは燐光(りんこう)さえ発し、蝶々のように定めなく飛翔していくかのようであるが、それがイニシアティブというものを持ってしまったのだから、スグルはもはや敬虔なまでに風に吹かれて飛ばされている、かのビニール袋である、乱舞、いや、乱。
サヤカはそれはもう雅やかに回転をしてジャンパースカートを遊ばせたり、突然スキップをし、ときには、胸元さえも押し当ててくる。フォッサマグナはこうして生じるのであろうか、この人は、一体何者なのであろう?
このようなことが脳裏によぎろうとするが、稲光のようなサヤカの即興が、不安や恐れ、あるいは猜疑心というものを弾き飛ばし、引っ張っていくのであった。もしかすると、これは、世俗には虚しいが、子供の頃に抱いていた、憧れという、最も清らかな心情のひとつかもしれない。
「スグル! 今何を感じているか言って」
スグルは次第になんだか溌剌と静寂を持て余しているような感覚になってきた。つまり、贅沢というものである。スグルはぐるんぐるんと繋げるように言った。
「サヤカサヤカサヤカサヤカサヤカサヤカ」
「何、それ」
「ハハハッ! アハハハハッ!!」