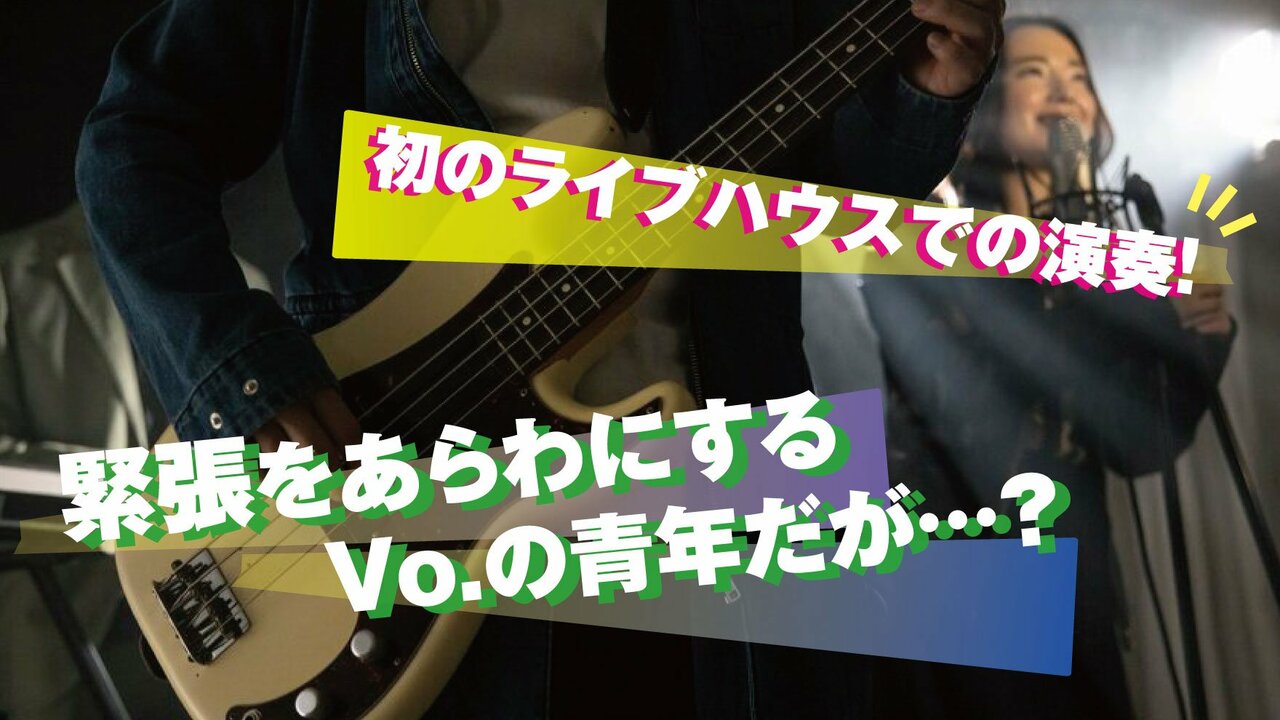3 天稟
駅の改札口の前には、あの子がいる。ゑ、正直言って、かわいい。それは、もったいないほどの事実である。いかにして、あの子は、生きてきたのか。
おや、突然鳥が鳴いた。その鳥は、人間に嫌われてしまっている哀れな黒い鳥である。なんだろうか、先んじて苦手に感じてしまう、全身に迸るほどの感覚や感情というものに、あまりにも、人々は敏感で振り回されているのではないだろうか。謂わば、アストラルトラップや錯覚というものも含まれているのであろう。
そんな頼りないものをあの子は、それも繋がれてきた愛なんだよと、鮮明にしたり、新たな色づけをしたり、たまに、忘れさせてくれているのかもしれない。
「おはよう! スグル」
「おはよう」
「今日の労働経済学の授業が終わったら、また、あの食堂近くの、ベンチで待ってるからね」
「おお、うん」
「あ、後ろ髪がまた立ってる」
サヤカは楽しそうに、スグルの後ろ髪をつっついた。スグルはなんだか、照れてしまって、上手く体や指先が動かない。
二人は、スマホを改札にタッチして、LEDに照らされた影を歩く度に縮めていく。駅構内のタイルからは、多くのコツコツとした足音が映画やドラマのワンシーンのようにも聞こえてくるが、時間帯としては、少々慌ただしい。
「そういえば昨日UPされていた○○チャンネル観た? 」
「観た観た。ゲストの扱い方が上手かったよ」
「そうそう。やっぱりああいうことができる人だから、バズる力も持ってるのよね」
「うん。そういうことだろうね」
「スグルもやってみれば」
「え!? 」
「わたしが第一号のチャンネル登録者になってあげる」
「おお、それはそれは」
「本当なんだから! 」
このように、たわいもない会話をしている二人や十人十色と言われているが、まさに様々な事情やバイオリズムを有している人々を今日も電車は、安全に運んでいく。あえて書かせてもらってばかりだが、このように茶を飲んでいるような日常が、突然金のように、胸に迫ってきて、あなたにも多感な情緒の成熟が促されることが、よくあることでしょう。定めなく、ビルや街並みが通り過ぎていくが、そういったものを会話の種にしたりと、青年は、話しを進めていくのであった。
「サヤカがはじめればいいんじゃない? 」
「わたしはまだ早いわ」
「どうして? 」
「それは、ヒ・ミ・ツ」
スグルは、この子がまだどんな子なのかは分からないが、この子の明るさの天稟みたいなものを、守らなければならないような気がしたのは、確かだった。