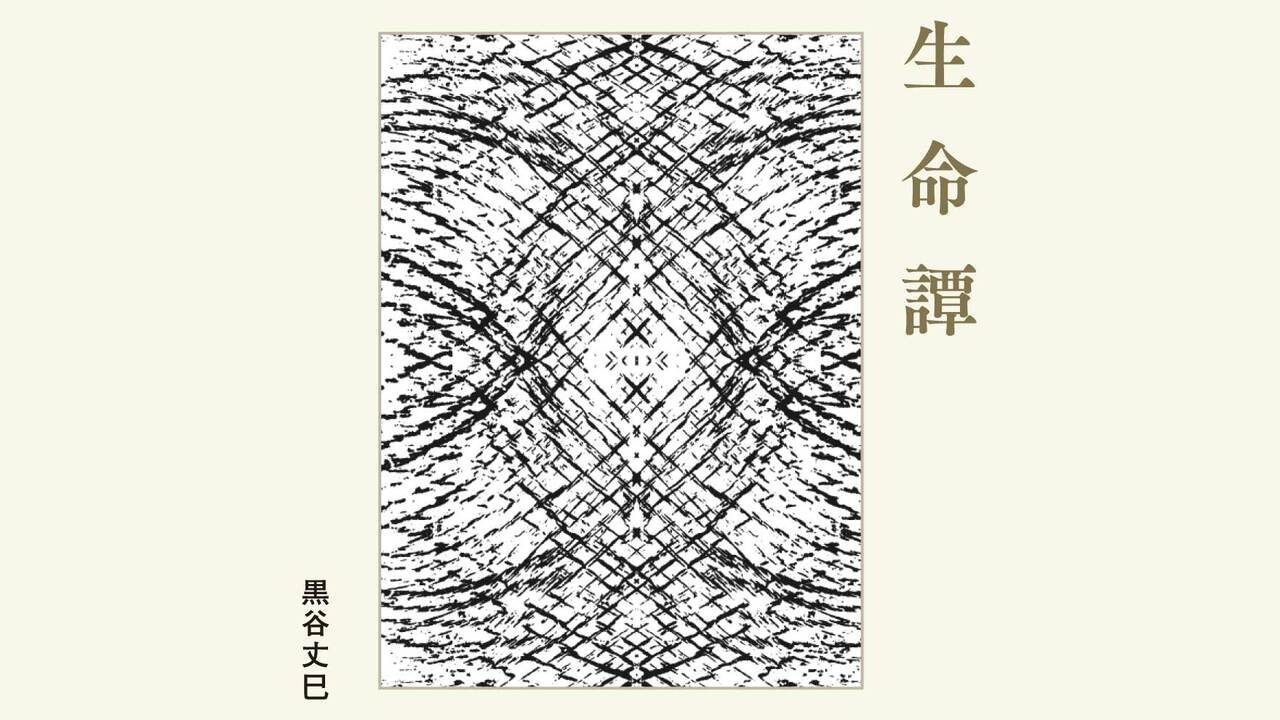一九八九年 春 ―京都―
「純平、飯食いに行こうや」
同学年の相国寺隆弘が話し掛けてきた。同じく四回生の城戸朋彦が隣にいる。セッターの純平は、キャプテンを務めている。身長一八五センチの相国寺はレフトを打つエース、城戸はセンターブロッカーである。三人とも二回生の秋からレギュラーとして試合に出ており、最上級生となった今年の春は、洛北大にとって八年ぶりとなる一部昇格のチャンスだと捉えていた。
二部四位だった昨年秋のレギュラーからは補助スパイカー一枚が抜けただけであり、新たにそのポジションを埋めた三回生は冬場に大きく成長してくれたため、間違いなくチーム力は向上した状態だったからである。
洛北大は京都では京大に次ぐ偏差値の大学であり、スポーツ推薦の入学者は皆無である。その環境で、セレクションによって高校の有力選手を集めた他大学と互角に競うことが純平たち洛北大バレーボール部のプライドであった。高校時代の球歴差を埋めるため、練習の量と質は絶対に他大学に負けていないと自負している。
一部リーグへの昇格は、洛北大が持つプライドの最大の証明手段なのである。
「今日のことはしゃあない。俺らが先頭に立って切り替えて、難波工大戦に集中せな」
「せやな、すんなり全勝で上がれるほど一部の壁は低うはないちゅうこっちゃ。ええやんけ、来週勝てばそれで問題ないんやから」
言葉の威勢の良さほどに二人が今日の敗戦から立ち直れているとは思わない。自分と同じように、だ。だが、相国寺の言う通り、最上級生でありチームの中心である俺たち三人が元気を出さねば、チームは悪い雰囲気を引きずってしまう。特に自分はキャプテンなんだから。純平は二人の頼もしい同期の顔を見つめた。
「ほなどこに行こか。あんまし高いとこはあかんで」
「飯だけ食っても仕方ないやろ。明日は練習休みなんやから、ちょっと飲んで帰ろ」
「俺らが安心して飲み食いできるとこいうたら決まっとんな」
「『福狸』やな」
「こっからやと、ちょっと歩くけどな。ま、そうしようや」
「福狸」は真如堂の近くにある赤提灯の飲み屋である。洛北大にもほど近く、バレー部は昔からこの店には世話になっている。コンパの二次会もこの店に来ることが多い。自分たちの両親とほぼ同年齢だと思われる無口なおっちゃんと陽気なおばちゃん、その娘が三人でやっている店で、純平たち三人もこの店で酒の飲み方を教わったと言っていいだろう。