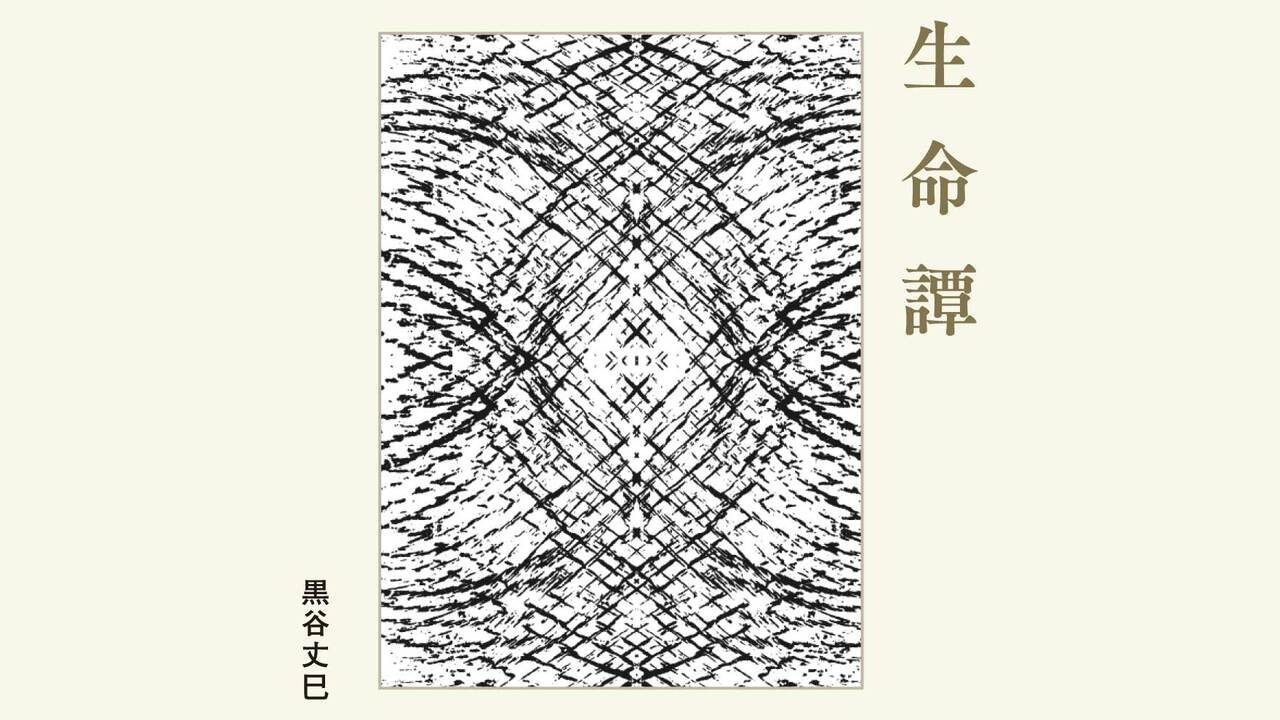二〇一六年 秋 ─大分─
日の入り時刻が近づいたようで、カーテンを閉めていない、西側の壁の面積の半分ほども占める二枚の大きな窓から西陽が差し込み、部屋の中をオレンジ色に染めている。今はまだ陰になっている淑子の顔も、もうじき直接陽が当たることになりそうだ。純平は立ち上がると、カーテンを閉めようと窓に近づいた。その時である。二枚の窓のうち右側の一枚が、カタカタと小さな音を出して震え始めた。
「風か?」
修治が訊く。窓からは、病院正門近くにある大きな欅けやきの木がよく見える。その木の枝も、欅から少し離れて植えられている低木の並木も、別にそんなひどく揺れている様子はない。
「いや、そんな強い風は吹いちゃおらんけどなあ」
純平は右手で震える窓を押さえた。カタカタと鳴るのは止まった。手を離す。するとまた鳴る。生死の狭間にある母親が静かに横になっている病室では、小さな音ではあってもこの雑音は気になる。
純平は思い立って、サイドテーブルの上にある新聞紙を手に取った。修治が今朝、売店で買ってきたものだろう。純平は新聞紙を折り畳むと、右側の窓枠の隙間に差し込んだ。
音は消えた。アルミサッシの窓が少々の風で鳴るもんなんかなあ、と言い掛けて、純平はその口を閉じた。右側の窓が鳴るのは止まったのだが、今度は左側が鳴り始めたのである。
カタカタカタ……小さな音ではあるが、間違いなく鳴っている。窓の外の木々の枝は、やはりそれほど揺れているわけでもない。風のせいではない。純平は黙って窓をじっと見つめた。淑子の枕元に座っている修治も黙ったままである。
――父さんは、俺と同じことを考えているんじゃないか。純平は何も言わず、カタカタと鳴る窓を開けた。数秒間開けたままにして、そしてゆっくりと閉める。先ほど右側の窓枠に差し込んだ新聞紙を取り去る。窓は鳴らない。修治と純平と、意識のない淑子と、親子三人だけがいる病室。しかし……。
「父さん」
「ん?」
「ばあちゃんかな……」
「……」
純平は別に霊魂の存在を大真面目に信じているわけではない。だが彼には、今の現象は、二年前に亡くなった祖母―淑子の母親。娘が自分より先に死んでしまうのではないかということを強く心配していた母親―が病室に入ってきたのだという気がした。
もしも霊魂なら、物理的な存在などではないのだから、窓を揺らしたりせず、壁でも窓でもお構いなしに通り抜けて入ってこられるだろうに。
いや、違う。ばあちゃんは、敢えて窓を鳴らしたんだ。父さんと俺に、自分が来たことを知らせたんだ。淑子を迎えに来たよ、と。父さん、父さんもそんな気がしたんじゃないか。
「……婆さんやったかも知れんのう、今のは」
真面目なのか茶化しているのか、純平には判断のつかない表情で修治がぽつりと返した。純平はカーテンを閉めると、向き直って淑子を見下ろした。ベッドの脇に導尿カテーテルのチューブを垂らして、淑子は微動だにしない。
日付が変わる頃、夫と息子に看取られて淑子は静かに息を引き取った。