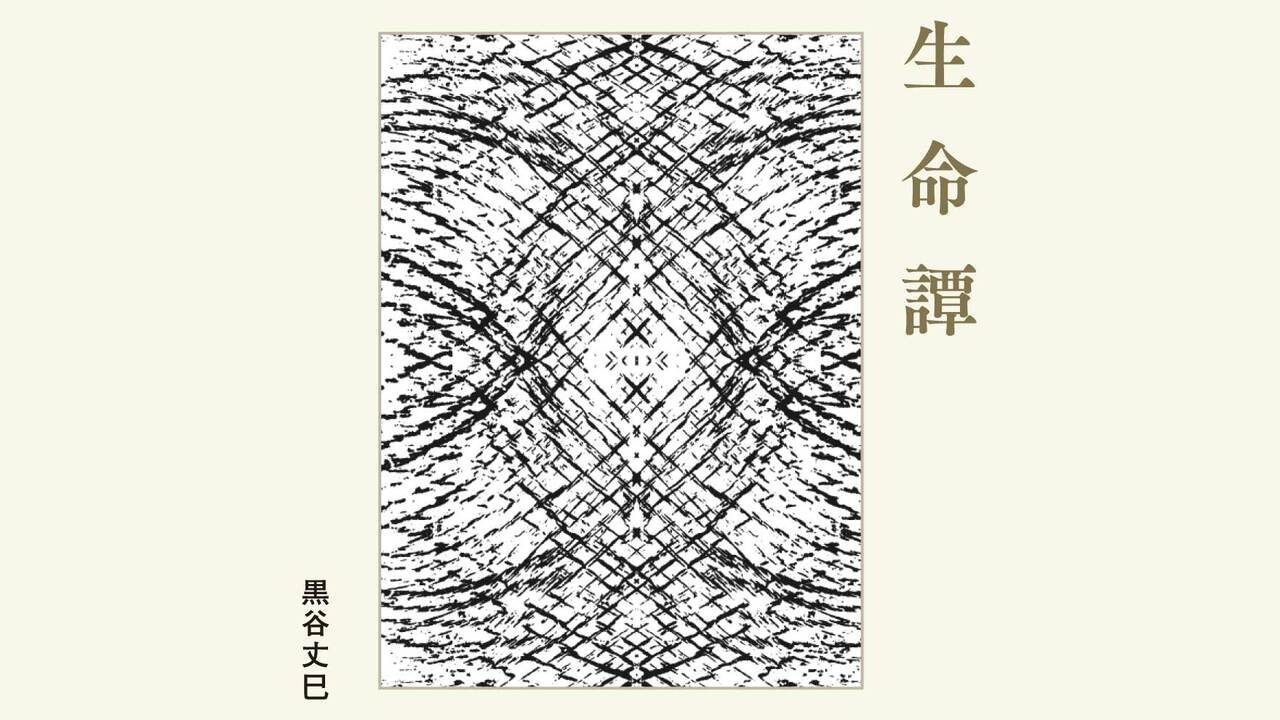一九八九年 春 ―京都―
あの日、「福狸」を出た後、相国寺は純平と城戸に告げた。
「この薬、ほんまもんなんかいい加減なものなんかはわからん。せやけど、もし、もしほんまに効果があるんやったら、これ飲むのがいちばん役に立つのはレフトの俺や。打数が多いし、追いトスで点を取りに行くのも俺の役目や。せやから、これ、俺が預かる。飲むも飲まんも、俺が決める。それでええな」
純平も城戸も異論は唱えなかった。研究室に持参することを一度は提案した城戸も、薬の信憑性があやふやな中でそう主張し続けることはなかった。酒も入っていた。そして相国寺の言う通り、試合に勝つためには相国寺の決定率が上がることが得策であることは確かだったからだ。
寿命が縮むという副作用が、二十一歳の三人にとってはまだぴんと来なかったということもある。八十歳が寿命だったとして、七十九歳と半年で人生が終わってしまうこととの差を実感として持つことはできなかった。それで、相国寺に判断を任せた。
公式練習を終え、ベンチ前に集まる。主将の純平は、皆が部旗を握って血走った目を向ける円陣の中、檄を飛ばす。
「ええか、この試合に勝つために今までやってきたんや。練習は嘘つかへん。自信持って、思い切って行くぞ。で、絶対に勝つ!」
チーム全員でウオオオー……と声を掛け合った後、スタメンの六人がコートのエンドラインに並ぶ。純平は、隣の相国寺に短く囁く。
「お前、ほんまに飲んだんやな」
「ああ。純平、あれ、間違いなく効果があるぞ。今日の俺は、打点もパワーもスピードも違う。どんどん持ってこい」
相国寺を挟んで純平とは反対側に並ぶ城戸にも、このやり取りは聞こえたはずだ。一瞬、三人の視線が交差する。
「よし、やるぞ」
「おう」