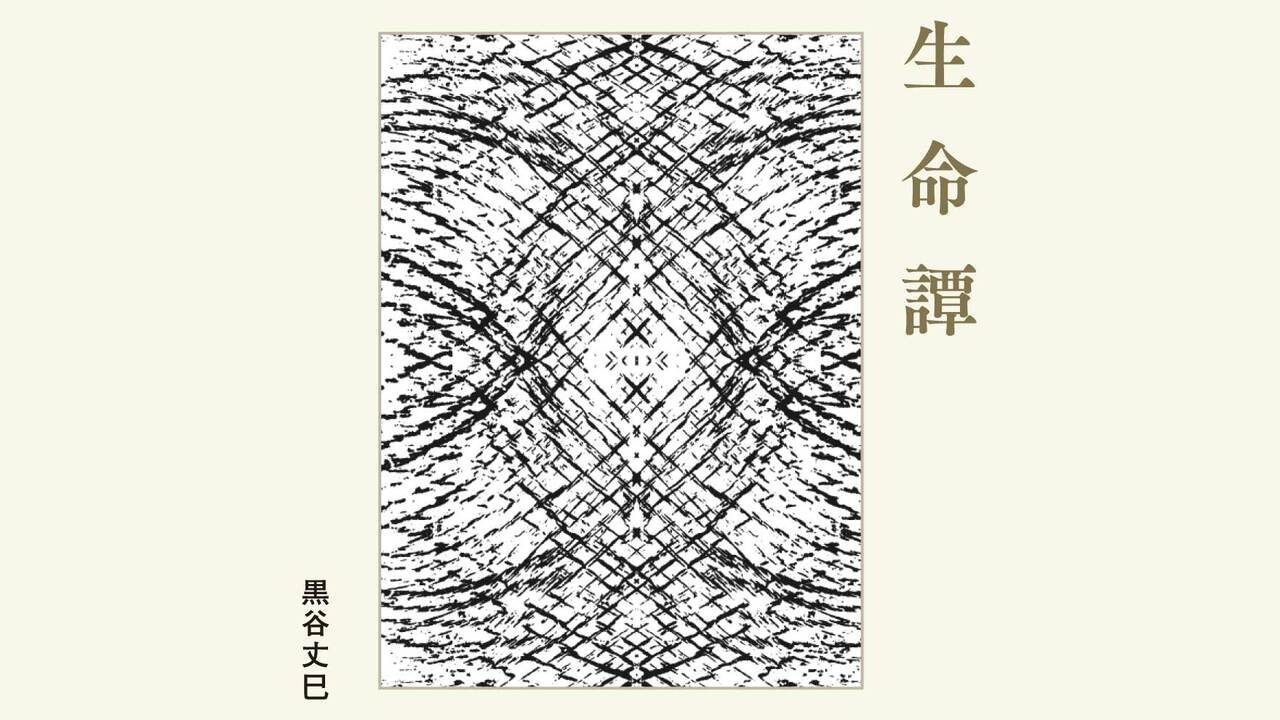一九八九年 春 ―京都―
純平たちも倉元とは逆方向に歩き始めた。福狸のおっちゃん、おばちゃんにいい土産話ができた。試合に負けたと愚痴って慰められるよりも、楽しく過ごせそうである。
「おもろいおっちゃんやったな。どこまでホントの話なんやろ」
「ほんまの話やったら、お前どうする? 十センチのジャンプ力アップで難波工大戦に臨める代わり、寿命が幾らか縮む言うんやで」
「おい、真面目にやな、まず研究室に持ち込んで調べてもろたらどや。万が一にもほんまやったら、えらいことやで」
「いや、これは洒落で済ますべき話とちゃうか」
電車を降りるまでの重苦しい雰囲気から一変して軽口を叩けるようになった三人だったが、城戸がふと振り向いて言った。
「おい、倉元のおっちゃん、もう見えへんぞ」
純平と相国寺も振り向いた。見渡す限り、河原に倉元の姿はない。ついさっき向こう側に歩き始めたばかりなのに。
「もう河原町通りに上がったんやろな。あの様子やったら、また飲み直すつもりやで」
「それやったらええけど、まさか水にはまったんとちゃうやろな。もう面倒見切れへんぞ」
「いやいや、案外あのおっちゃん、仙人かなんかで、もう消えてしもたんかも知らんで」
「浮世離れしとったもんなあ。でも実際にこうやって薬瓶が手元に残ってるからな。少なくとも伏見稲荷の狐に化かされたとか、そういうことやなさそうや」
じゃれ合いながら夜の鴨川の河原を歩く学生三人組。学生の多い京都らしい景色ではある。その京都は、修験道の開祖である役小角や多くの陰陽師と縁の深い土地でもある。倉元がそういう類の存在だったとしても、この場所ならば不思議はないのかも知れないという思いが純平の頭をかすめた。そう言えば、風貌もいかにもそれらしかったじゃないか。