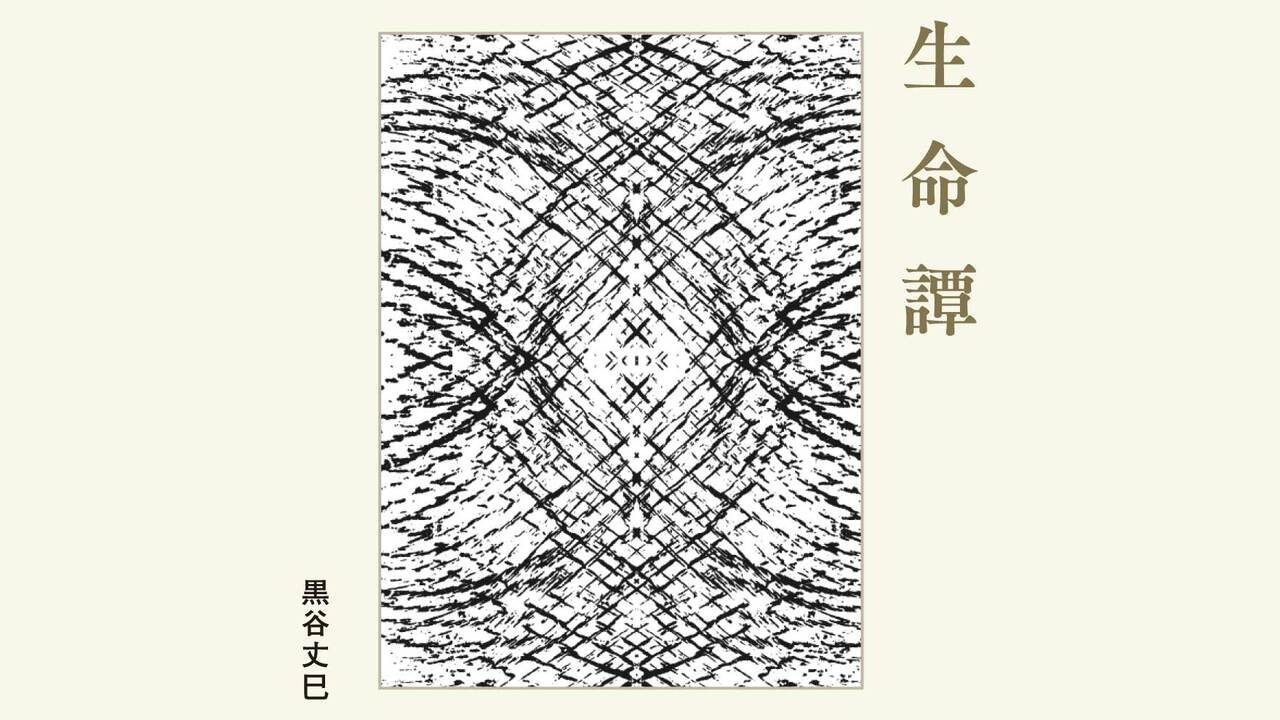一九八九年 春 ―京都―
やっぱり酔っ払いのでまかせやったな。純平にも笑みが浮かぶ。まあ面白い話聞かせてもろたで。
「とにかくやな、偶然にせよわしの生涯最大の発明品や。せやからこうしていつも携帯しとる。せやけど、使い途があらへん」
「製薬会社とか大学の研究室とかに持ち込んで調べてもろたらええんやないですか? そしたらまた作れるようになるやろし、商品開発もでけるんとちゃいますか? なんでそうせえへんのですか」
城戸はあくまで真面目な対応である。こいつは、偉い。
「製薬会社? 大学の研究室?」
倉元は露骨に表情を歪めた。
「今さらそんなとこに行く気はないわい。ああいうやつらとは、同じ空気吸うのもいやじゃ」
倉元の言うことがどこまで本当なのかはわからないが、とにかく過去に大学なり企業なりとの間でトラブルがあった結果が、この男の今の姿なのだろうとは見当がつく。
「別にの、こんなドーピング薬、あっても無うても世の中には大した影響あらへんのや。そやさけ、わしが墓場まで持っていくつもりやった」
「それを、学生スポーツやってるいうことで、袖振り合うた俺らにくれるいうことか、倉元のおっちゃん」
「そや。全日本クラスならともかく、普通の学生スポーツにドーピング検査なんかないやろ。ま、仮に検査されたとしても登録されてる禁止薬物は出てけえへんから何の問題もないけどな。これ使うたら、兄ちゃんたちのチームはとんでものう強うなるで」
「話半分としても面白いなあ、それは」
「半分やあらへん。全部ほんまのことや。まあ飲むまで納得はせえへんわな。ジャンプ力が十センチ伸びるとか言われてもな。な、兄ちゃん」
「そんなこと言うて、まさか毒物なんやないやろな」
倉元が、にやりと笑った。
「毒やない。これも信じて貰うしかないなあ。そもそも人体の害になるような原料は使うてへん。ただな、毒やないけど……」
「ないけど?」
「副作用はあるんや。それだけは覚悟して貰わんといかん」
「そんなことやろうと思うたで。それが話のオチかいな。副作用の話聞いた俺らが、そんな恐ろしい薬なんやったらよう使わん、おっちゃん、その薬は要らんわ、そうか、それやったらしゃあないな、ほなさいなら、いうことなんやな」
「兄ちゃんたちが要らん言うほどの副作用やとは、わしは思わんのやけどな。まあ、人によって判断は違うやろな」
「えらい思わせぶりやな。具体的にはどんな副作用やねん。そこまで聞かな、この話は終わらんやんか」
「寿命がな、縮む」