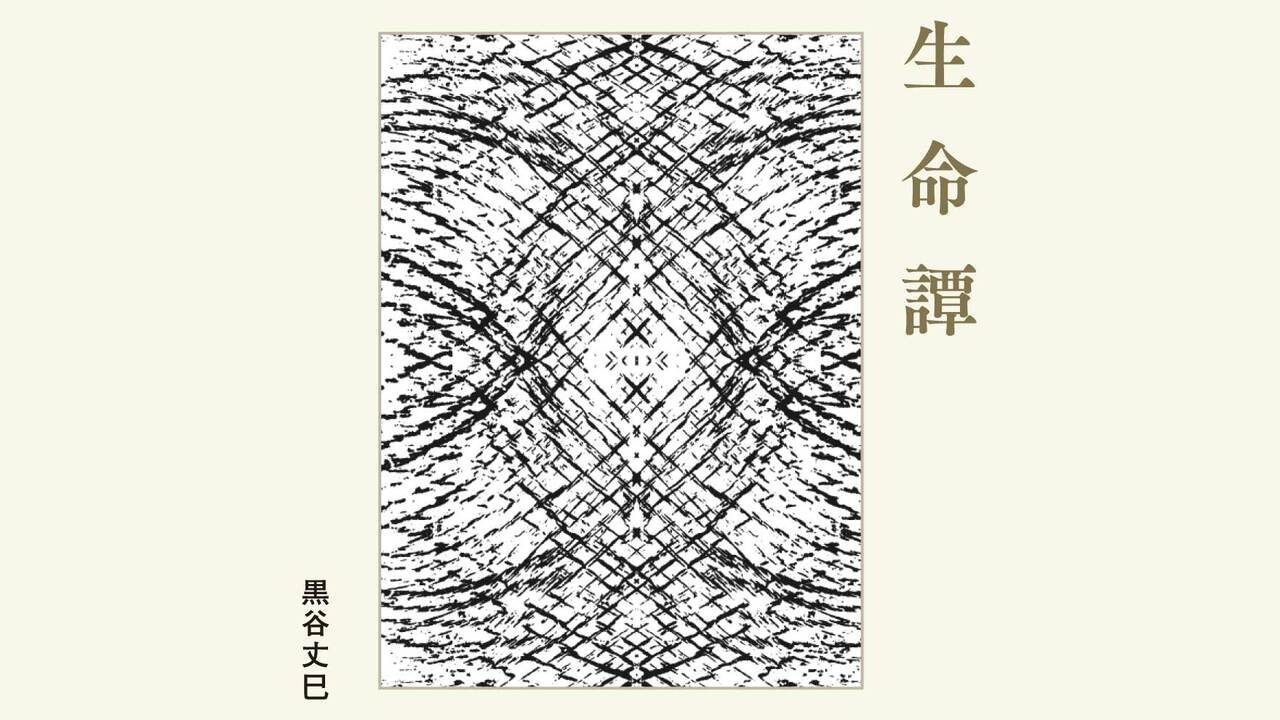一九八九年 春 ―京都―
上着の袖で口を拭って、男が口を開いた。
「ああ、兄ちゃんたち、おおきに。すまんかったな、もう大丈夫やで。いや、そんな酔うてたわけやあらへんのやで」
「おじさん、大丈夫ですか。歩けますか」
相国寺と違い、城戸の口調は丁寧である。
「わし、膝が悪うてやな。大して酔うてへんのやけど、膝がいうこと聞かへんかったんや。せやけどほんまや、もう心配あらへんで。兄ちゃんたちに声掛けてもろて、膝もしゃんとしたわ」
「そら良かったな。ならな、おっちゃん、気ィつけて帰りや」
そう言い置いて相国寺が歩き出す。純平も城戸と一緒に相国寺の後を追おうとした。
「兄ちゃんたち、ちょっと待ちいや」
酔っ払い男が声を掛けてきた。なんや、面倒なやつやな……せっかくやから一緒に飲もうやとか言うてもあかんぞ……純平は警戒する。
「兄ちゃんたち、その格好、学生のスポーツマンやねんな。洛北大か」
確かに三人は、大学のロゴ入りのウィンドブレーカーにジャージ、手にはスポーツバッグとくれば、誰でも洛北大のスポーツ選手だと見当がつく姿である。
「助けてもろて、ほなさいならいうわけにもいかんやろ。幸いな、わし、今の自分には何の役にも立たへんけど、兄ちゃんたちの役には立つかも知れんものを持っとるんや」
酔っ払いが妙なことを言い出したなと思いつつ、三人は振り返った。
「こんな酔っ払いの爺いが何をでまかせ言うてるんやと思うやろな。ふ、無理もないわ。そやけどな、兄ちゃんたちが信じようが信じまいが勝手やが、今はこんな汚い爺いやけどな、わしはこれでもな、関西医薬大の薬学博士号を持つ化学者なんやで。名乗っとこうか。倉元や」
相手にするな、早く行こうやと城戸が相国寺の袖を引っ張るが、相国寺は面白がっている。
「へええ、おっちゃん、化学者なんか。医薬大出身の立派な先生がなんでそんな格好で酔い潰れるようなことになったんか興味あるけど、そこまで立ち入った話聞いてる暇はないな。んで、おっちゃん、何を持ってる言うんや」
「ふん、そらあな、いろいろあるんや。それこそ兄ちゃんたちの乏しい人生経験じゃとても理解でけへん事情がな。世の中っちゅうのはな、わからんちんだらけなんやが、わしも学生相手にそんな話するほどのあほやない。とにかくここで、運動部の学生に縁ができたいうのも運命や。わしが持っとるのはな……」
倉元と名乗った男は、上着の内ポケットから小さな瓶を取り出した。
「これはな、わしの最高傑作や。ただし、決して売り物にはなれへん」
「薬ですか。なんで売り物にならへんのですか」
純平は「酔っ払いの戯言」だとしか捉えていないのだが、城戸は真面目に興味を示す。性格のいい男だな、と純平は思う。
「効能がな、要するにドーピングなんや」