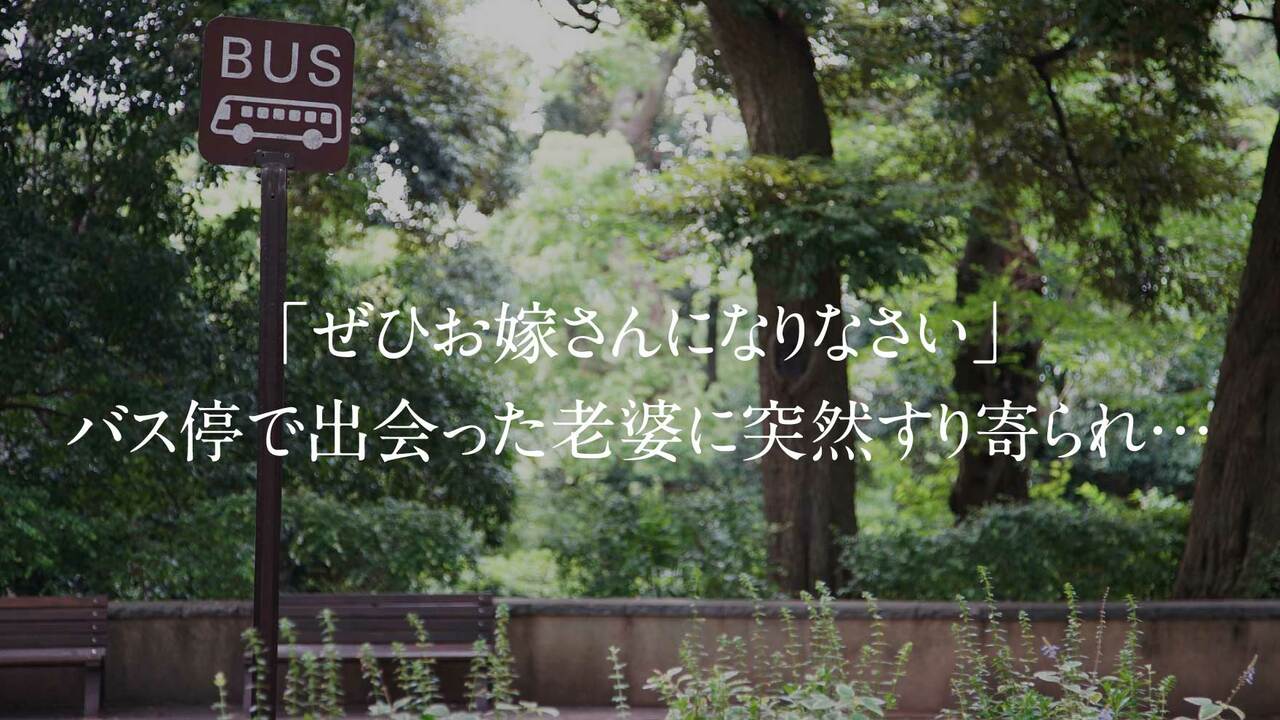フランクル『夜と霧』への旅
それは春の日のことだった。
図書館で何気なく手にした一冊の本。河原理子著『フランクル『夜と霧』への旅』のまえがき。「フランクルになぜこんなにはまったのだろう。『はまる』というより『浸る』という感覚が近い」という文章を読んだ途端、涙が止まらなくなった。
ストレスが溜まると爪を噛む癖の長男の手が浮かび、次男の「お母さんが死んだらうちは一家離散だなぁ」の言葉が浮かび、新潟の万台橋の近くで、車に飛び込もうとした私の手を強引に引っ張った夫。「死ぬんだ!」と叫んで木にしがみついてわめき続けた私の異様な日が、突然走馬灯のように浮かんだから。
その本を棚に戻し、それから市内を車で走り続けた。なかったことにできない日々を思い出しながら、訳のわからない涙ばかりが流れた。
その三ヶ月ほど前、私はフランクルの『夜と霧』を読み、あの収容所体験が、私のうつ病体験と似ている気がして驚いたばかりだった。
それからしばらくして、もう一度『夜と霧』を読み返すことにした。
なぜか、そんな思いに駆られた。
「経験など語りたくない。収容所にいた人には説明するまでもないし、収容所にいたことのない人には、わかってもらえるように話すなど、到底無理だからだ。私たちがどんな気持ちでいたのか、今どんな気持ちでいるのかも」
こんな文章が響いてきた。
フランクルは、この本を実名ではなく、被収容者番号で公表するつもりだったこと。第二次大戦後、経験者の露出趣味に抵抗を覚えながらも、匿名で公表されたものは価値が劣る、名乗る勇気は認識の価値を高めることである。そして、自分を曝け出す恥を乗り越え、勇気をふるって、実名で自分自身を売り渡したと述べている。
この心理学者の崇高な勇気を凄いことだと思った。
私は心理学者ではないし、ロゴセラピーの問題は難しすぎる。そこで私自身に起こった精神病理的なものと重なる部分だけを拾ってみることにした。
二〇〇七年十一月、秋も終わり冬が訪れようとしていた季節だった。その日は快晴で、私は朝から義理の妹が届けてくれたたくさんの大根で切り干し大根作りに夢中になっていた。
何気ない日常が過ぎたはずなのに、夜中、腰の激痛に襲われ、目が覚めた。寝返りをしようとしても、痛くてできなかった。一体私の体はどうなってしまったのだろう……と不吉な予感に駆られたが、春からギックリ腰を繰り返していたので、今度は酷いギックリ腰だなぁと思った。
でも朝方、起き上がることができないほどの激痛に襲われ、トイレに行くためにベッドを離れようとしたのだが、かなり困難だった。後に、たぶん、一日で身長が七センチ縮んだ圧迫骨折を起こしていたことを知ることになるのだが、そんなことは思いもよらなかった。私の体は、その日から歩くこともやっとで、座ることがままならない体になっていた。
それは、東北大学病院で膠原病と宣告された時とは違う、絶望感のない奇妙な明るさで、事態はそう悪くならないと思った。なぜか病院にも行かなかった。当時リレー形式で、福島民報社にエッセイを連載させて頂いていたので、本を読んだり、文章を書くのに絶好のチャンスなどとも考え、枕元に本を重ねたり寝ながら文章を書いたりしていたのだが、長続きしなかった。