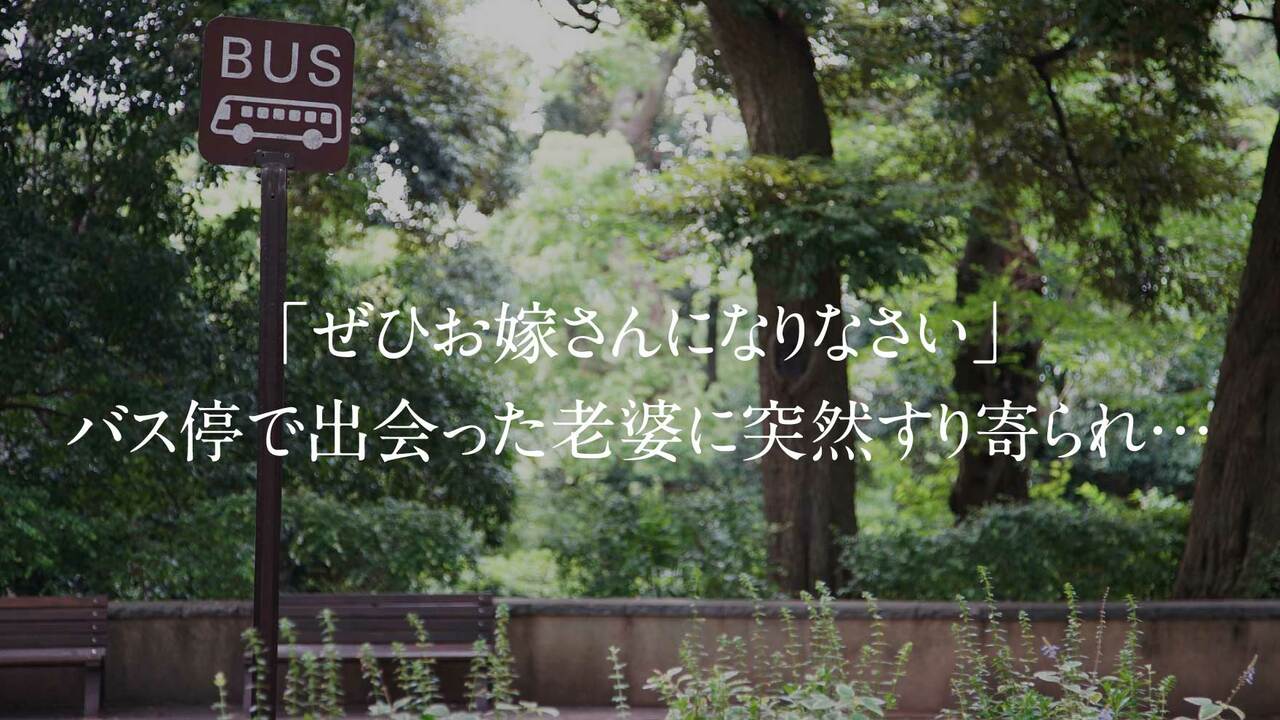序章
二〇二〇年・八月十六日。仙台で暮らす夫を見送った。夫も次男も妹が作ってくれる角煮が大好物で、角煮が届くとその嬉しさが私にも伝わってくる。私は角煮が作れない。なぜなら圧力鍋を使うのが苦手で、長い間避けてきたからだ。つい最近、電気を使用した圧力鍋の存在を知った。何とか私にも使いこなせそうで、その鍋を購入した。
初めての角煮と惣菜を持たせ、夫を見送りベッドに横になった。少し疲れたらしい。
残暑が続いているにもかかわらず、窓から柔らかな微風が吹いてくる。でも庭の紅葉の葉は揺れてはいない。お盆が過ぎる頃から、会津の秋は確実にやって来る。約束を守るかのような移りゆく季節の気配。この風は子どもの頃から感じた風だと思った。
目には見えないけれど、私には小さい頃から風の記憶が幾つかある。
それだけでなく、時々古代人じゃないかと思うときがある。実家に帰る途中に、晴れた日にはキラキラ輝くゆるやかな川が見えてきて、その場所に来ると決まってスサノオノミコトの「八雲立つ出雲八重垣……」の歌が浮かんでくる。
秋の黄金色に実った稲葉を見ると、やはり古代人じゃないかと思ってしまう。
この持てあまし気味の古代人の感覚を、日本の近代史に大きな影響を与えた詩人、西脇順三郎の『旅人かへらず』の中で見つけたときは、驚きとともにこんな感覚で生きている人がいたことが嬉しくて仕方がなかった。
詩人は「原始人」という表現をされているが同類のように思われた。そして「自分の中にもう一人の人間がひそむ。これは生命の神秘、宇宙永劫の神秘に属するものか、通常の理知や情念では解決できない割り切れない人間がいる。これを自分は『幻影の人』と呼びまた永劫の旅人とも考える」と書いておられる。
そこに共感する私がいた。