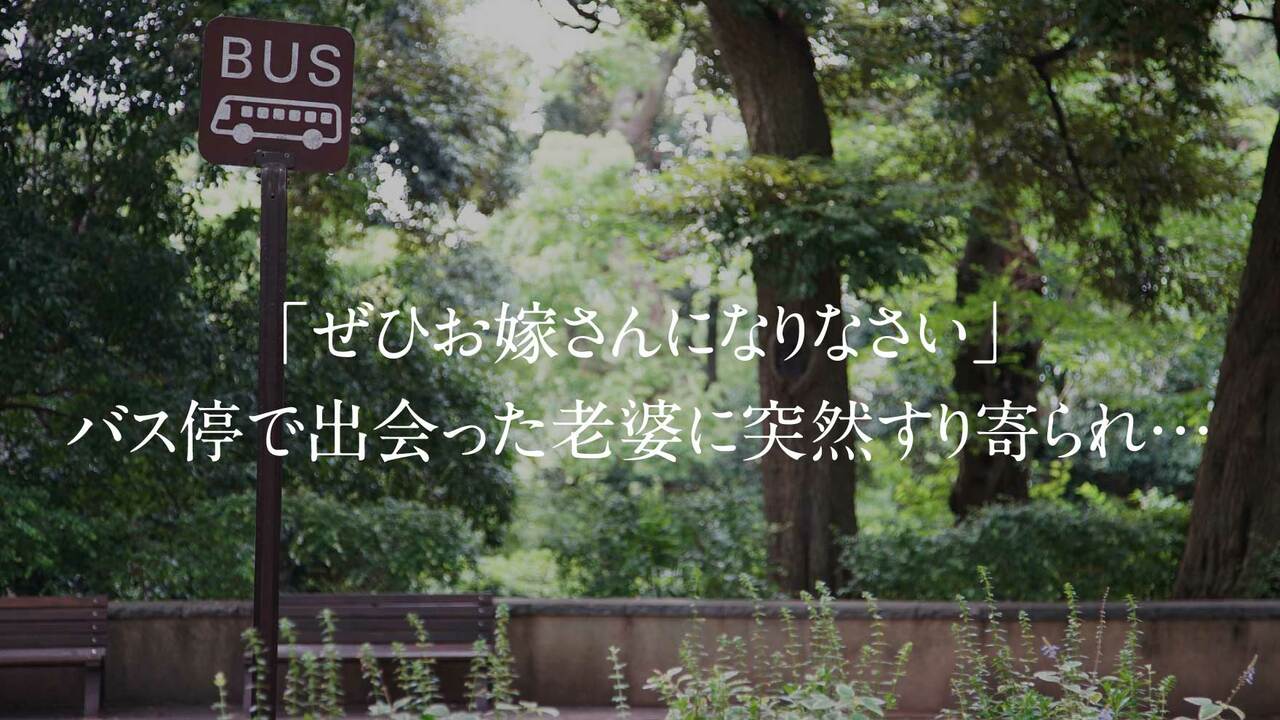【前回の記事を読む】「なかったことにできない日々」思い出させた一冊の本とは
フランクル『夜と霧』への旅
その年の会津は例年になく大雪で、十二月に入って間もなく雪が降り始めた。
その白い雪が、死の世界のような、恐怖が私を襲い、心が違う世界に引き込まれていくように思われた。私はもうその頃から病んでいたのかもしれない。
そんなある日、「水晶に向かって祈りなさい」という声がどこからか聞えたような気がした。暗示のような、不思議な出来事だった。
この行為は、フランクルが語る「降霊術」のようなものだったのだろうか?
違うかもしれない。病む者は、いや私は弱い人間なので一生治らない膠原病を発症してから、東洋医学の本を読み漁り、新興宗教にすがった経験を持っていた。
体に身に着けていれば、運命が好転して奇跡が起こるというキャッチコピーに惹かれ、中国産だという黄水晶のブレスレットを購入したことがあった。タンスの奥にしまい込んでいたブレスレットを思い出し、棚に飾った。
それから脳(どこか)から、頻繁に指令が来るようになった。「ブレスレットを祈りなさい」と。
ベッドに寝ていると指令が来るのだ。右手を上げなさいと指令が来ると、操り人形みたいに、右手は勝手に上がっていた。ベッドから起き上がるのが一番大変だったのだが、「右足を上げなさい。その足を横に伸ばしなさい」などと指令が来ると、勝手に足が動いていた。まるでカルトの信者のようだった。
私は一日中、ブレスレットに向かって祈る行動を繰り返すようになった。でも夫が帰って来ると、この奇妙な行動は止めていたので、完璧に狂っていたわけではなかったと思う。
エッセイの連載は、何も浮かばず、新聞社に断わりの電話を入れたのは二○○八年二月だった。
最後のエッセイを書き終えた時、私の中で、ガタガタと何かが崩れ落ちたような気がした。それ以来、泣くということはなかった。そして活字も音楽もまったく駄目になった。
本当にそうなのだ。内面がじわじわ死んでいくのだ。あの頃の食事は、外に出られないので買い物は夫に頼んでいたと思うのだが、夫のお弁当は作れなくなっていた。朝夕の食事は作り続け、私自身は台所で立って食べた。