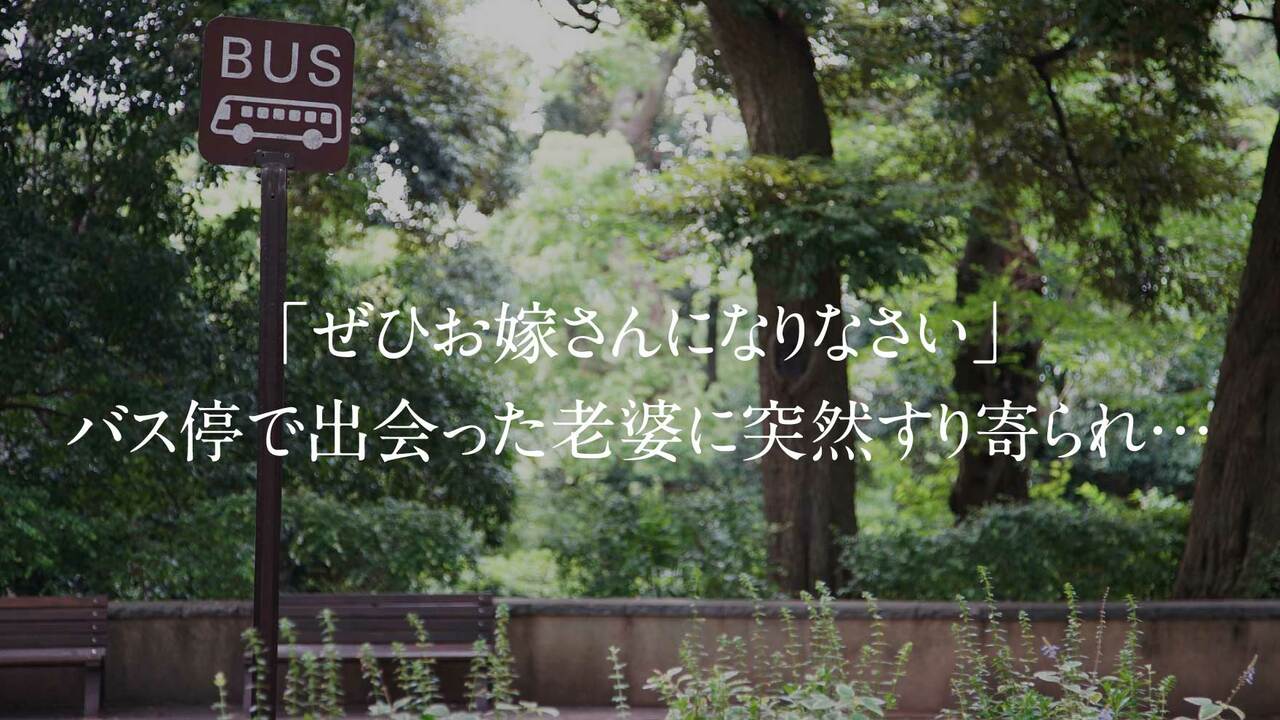【前回の記事を読む】脳に指令が…ブレスレットに祈るようになって起きた壮絶な体験
フランクル『夜と霧』への旅
我が家は団地の一番奥の少し高台にあり、普段でもあまり人の声がしない所なので、その冬の音のない寝たきりの一日の生活は、冷酷以外の何ものでもなかった。
苦しくて何もかも駄目だった。何もする気になれず奇行を繰り返した。
ある日、近所の人が突然訪ねて来たとき、私は怖くて怖くて仕方がなかった。
そんなある日、あまりの寂しさにリビングの窓を開けてみた。外は雪景色だったが、庭のナナカマドに小鳥が数羽飛んできて、「チチチチ……」と鳴いてくれた。
「大丈夫、大丈夫。私はここにいますよ。そんなに嘆かないで、悲しまないで」といったふうに、まるで慈悲の音色を奏でるように聞えてきて、私の心を温めてくれた。鳴き声が(ここにいるよ)と聞こえてくるのだ。
遠い彼方から、私を救ってくれる深い祈りにも似た鳴き声のようにも思われ、私を慰めてくれた。
でも小鳥たちは、毎日は来てくれなかった。夫にベッドを窓側に移してもらい、私は毎日待ちわびた。すると小鳥たちはまたやって来て、「チチチチ…」と鳴いてくれた。鳥が奏でるメロディーは今まで聴いたことのない最高の音楽だったように思われた。
悲しむ私を包み込むような、もっと悲しい鳴き声のようにも思われ、春まで続いた鳥たちとの交感が、後に「悲しみこそが人生、悲しみこそが力」という思いに私を運んでくれた。そして、いつの間にか義母の写真に祈ることを止めていたのだから、人間(私)の精神のメカニズムがどのようになっていたのか、不思議でたまらない。
後に、あの鳴き声を聞かなかったら、もっと重症の、または完治することのない別の精神疾患を患っていたに違いないと思うようになった。何となく直感でわかるのだ。私はギリギリの状態で救われたのだと。私にとって、あの鳴き声は宗教的なもののように感じられた。
春が近くなったある日、白内障の手術をすることになった。これもステロイドの副作用で、両眼ともかすんでしまい、物がよく見えなくなった。健康な人なら日帰りが可能なのだが、私の場合は二泊三日の入院が必要だった。私はこの入院が怖くて仕方がなかった。
入院中、音が怖くてたまらないという事件が起きた。私にとってはやはり事件だった。前のベッドのおばあさんの家族が夕方やって来て、テレビで七時のニュースを見るのだが、その時間が来ると、体が震えて布団をかぶり耳を塞いだ。夫は何度か精神科に行ってみようと勧めたが、自分が病んでいるなんて思ってもみなかったので、私は頑なに拒み続けた。
でも、今回はさすがに自分でもおかしいと気がついた。そして精神科を受診してみようと思った。
その場所は別棟にあり、看護師さんに付き添われ、薄暗い廊下を歩きながら、私はこの場所の住人になるのだろうと思ったことは覚えている。そして、うつ病ですと診断された。
圧迫骨折の次はうつ病か。私はどこまで堕ちていくのだろう。一瞬心のどこかでそんな思いがよぎったが、その頃は何の感情も失っていたので、先生の言葉は風のように、私の中を通り過ぎただけだった。