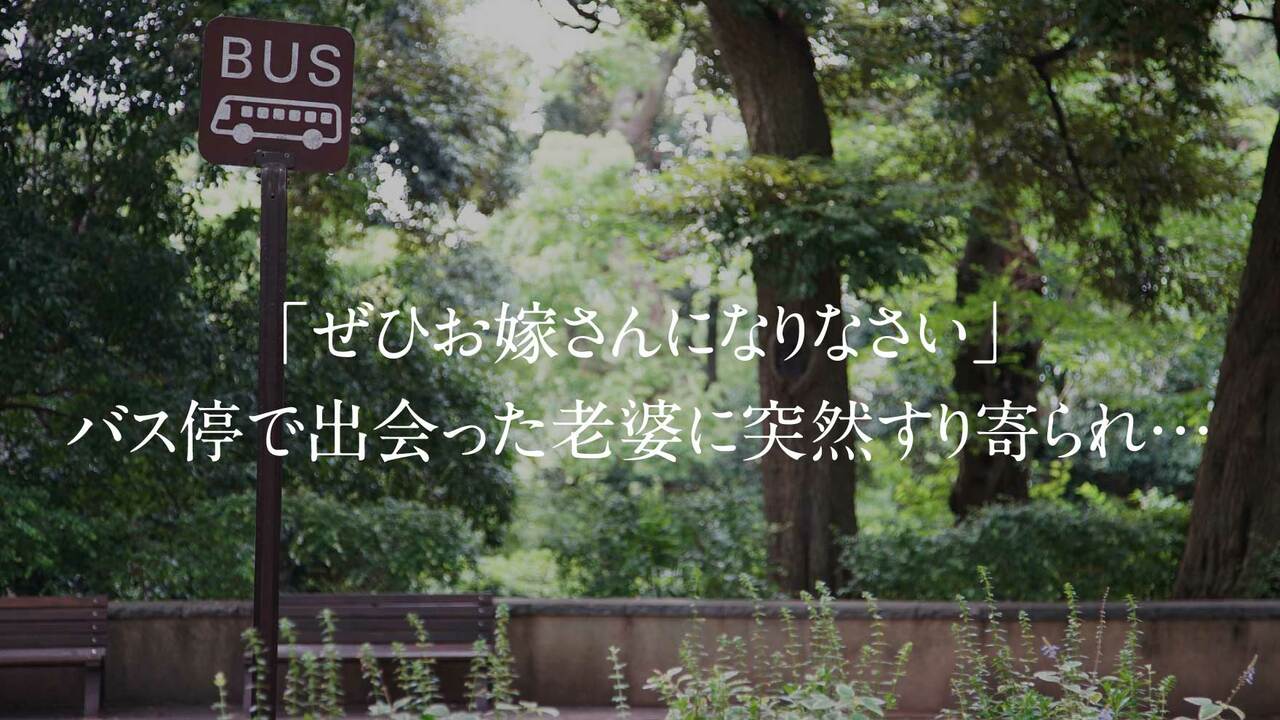年の瀬がやって来た。最初帰省した次男に、「お母さんが今こうしているのは、ブレスレットのおかげだから、お前も祈ってほしい」と私は言った。次男は黙ったまま、手を合わせてくれた。
大晦日に帰省した長男と家族三人、妹が送ってくれたおせち料理を食べながら紅白歌合戦を見ていたのだが、私はリビングに移したベッドに横たわっていた。
そして起き上がり、ブレスレットに向かって何度も祈り、「治った!」と大声を張り上げた。
今では我が家の笑い話になっているのだが、誰もがその時だけシーンとなった。そっとしておくしかないと思ったらしい。夫の記憶によると奇声をあげたり、「神がいる」などと叫んだりしていたらしい。
今となっては、家族が私の精神異常に深入りせず見守っていてくれたことは有り難かった。夫は協力を惜しまなかった。
痛みにはプラセンタが効くことを知り、毎週のように白河の病院に注射を打ちに連れて行ってくれた。
私は車の後部座席に布団を敷いて横たわっているのだが、冬の鉛色の空は、フランクルが書いているように、「まるで自分がすでに死んでいて、死者としてあの世から、この幽霊じみた町を幽霊になって見下ろしているような」気がした。
これは本当に生々しい感覚で、この文章が『夜と霧』の中で一番リアルに響いた。生きているのが怖くて仕方なかった記憶が残っている。
また、南雲直二著『身体障害の心理学』によると、「全面降伏とは生きる意志を失った状態のことである。生きながらの死者である。心的外傷は人から生きる意志を奪い去り、人を全面降伏の状態に追い込むことがある」ということだったのか。また、フランクルの語る「精神の崩壊現象」だったのか、本当のことはわからない。
そして、ブレスレットはいつしか、義理の母親の写真に変わっていた。大学二年で母親を亡くしている夫は、困ったことがあると「おふくろが守ってくれる」が口癖で、その影響があったのだろうか。義母の写真の前に行くまでに、ブレスレットの時よりも、もっと具体的な指令が来るようになった。
「三歩歩きなさい。そこで一礼しなさい。拍手を三度打ちなさい。手を合わせて祈りなさい」といった指令が来て、私はその通りに行動し、一日中、何度も繰り返した。この一連の異常行動は、「異常な状況では、異常な反応を示すのが正常なのだ」という、フランクルが語る典型的な感動の消滅(アパシー)だったのだろうか。
十日以上お風呂に入らなくても平気だったし、顔を洗うことも歯を磨くこともしなかった。一方で、腰に悪魔がいるような気がして、何度も腰を洗い続けたりもした。
その年の冬は、パジャマに着替えるのも面倒くさくて、同じセーターとジャージのズボンで過ごした。私自身が汚いのに、汚いという感覚も失っていた。もうどうでも良かった。
当時の写真が一枚だけ残っているのだが、私自身が驚くほど表情をなくした、のっぺらぼうのお化けのような顔が写っている。
いつだったか、記憶は定かでないが、内科の検診に出かけた。
主治医の先生に腰が痛いと訴えると、先生は慌てたようにレントゲン室に連れて行った。高いベッドに横たわるだけでも一苦労だった。そして圧迫骨折を起こして椎骨が六ヶ所潰れていると告げられた。
「潰れた」の言葉だけが鳴り響き、私の体は二度と元に戻ることができないのだという。非情で凍りつくような悲しみに襲われた、あの時間のことは鮮明に覚えている。