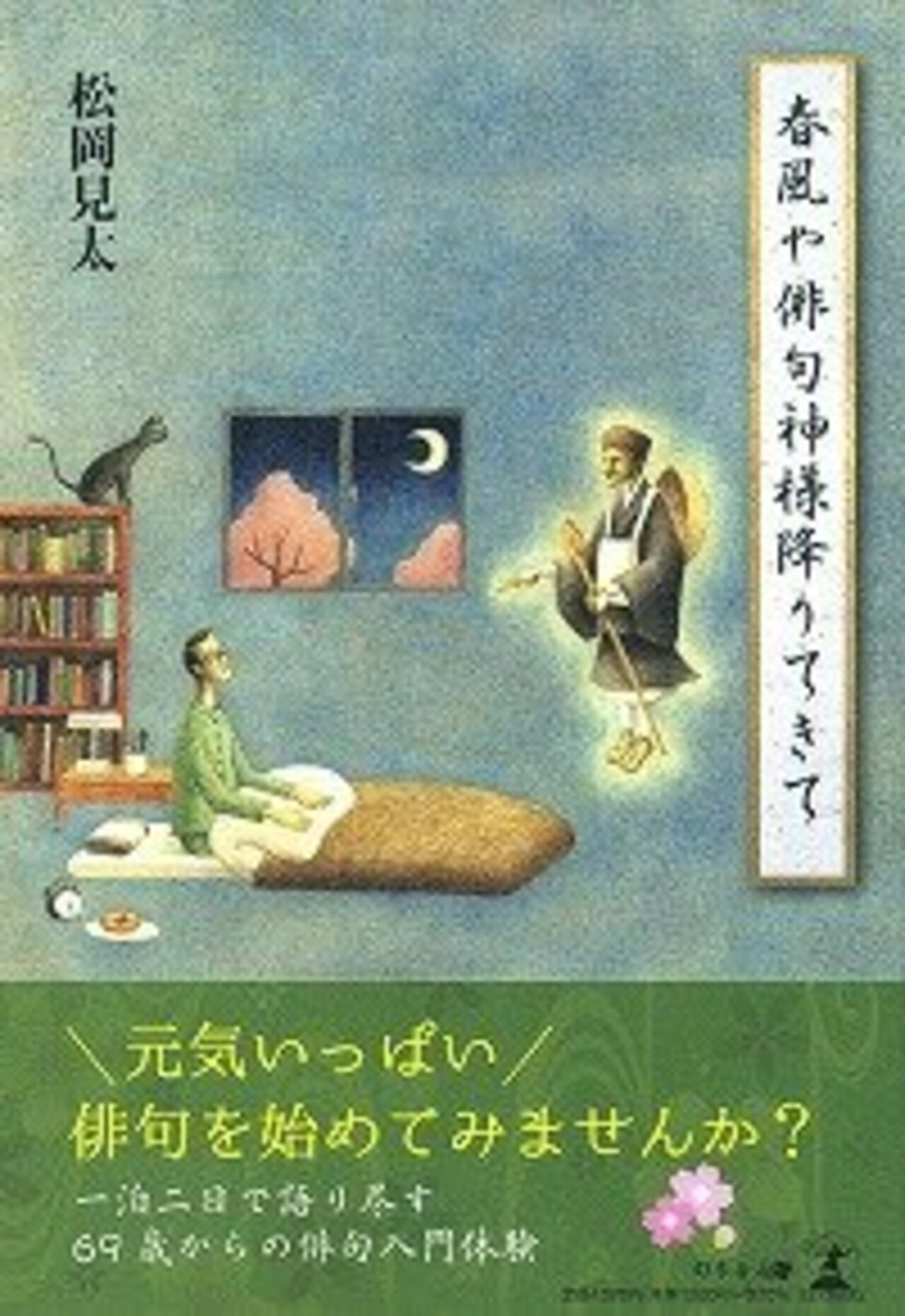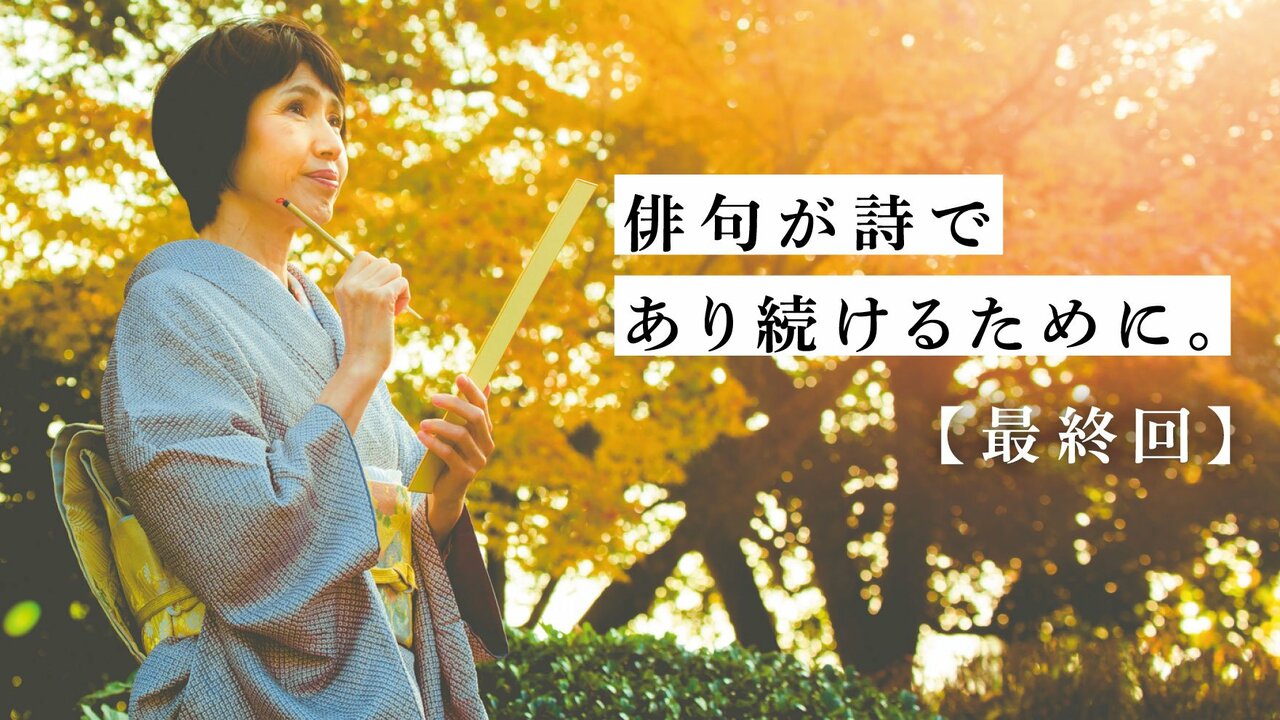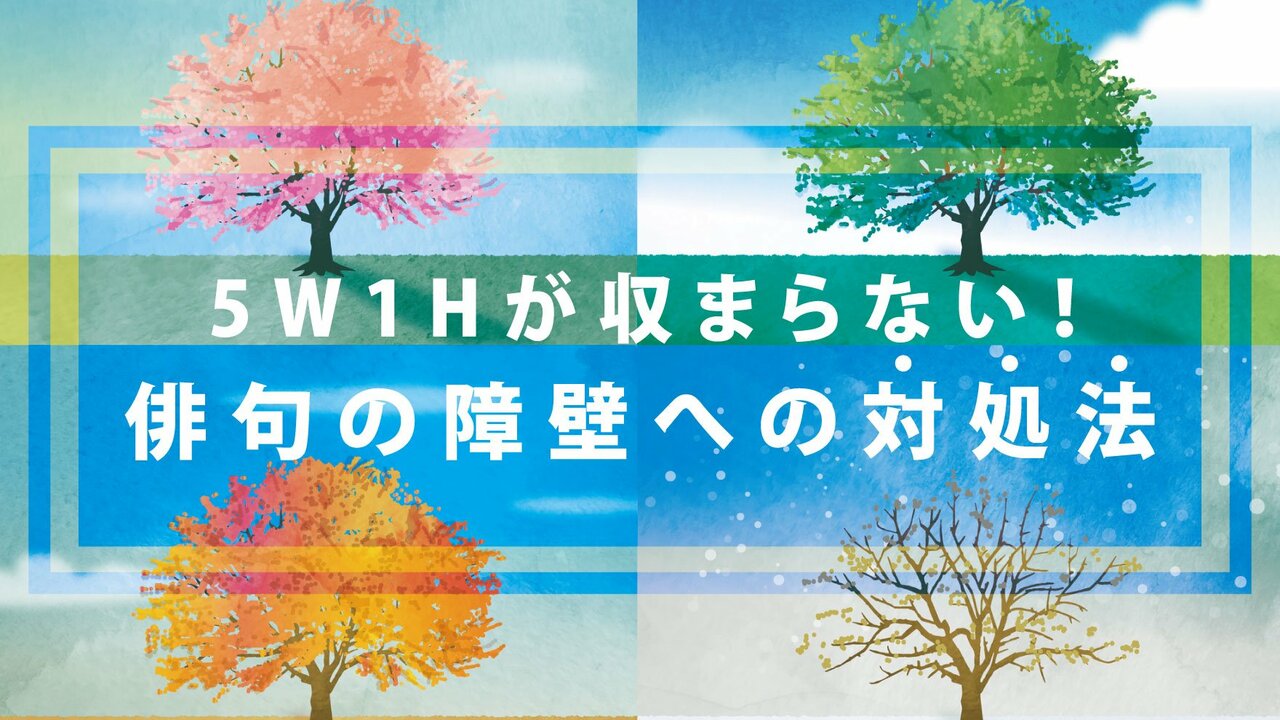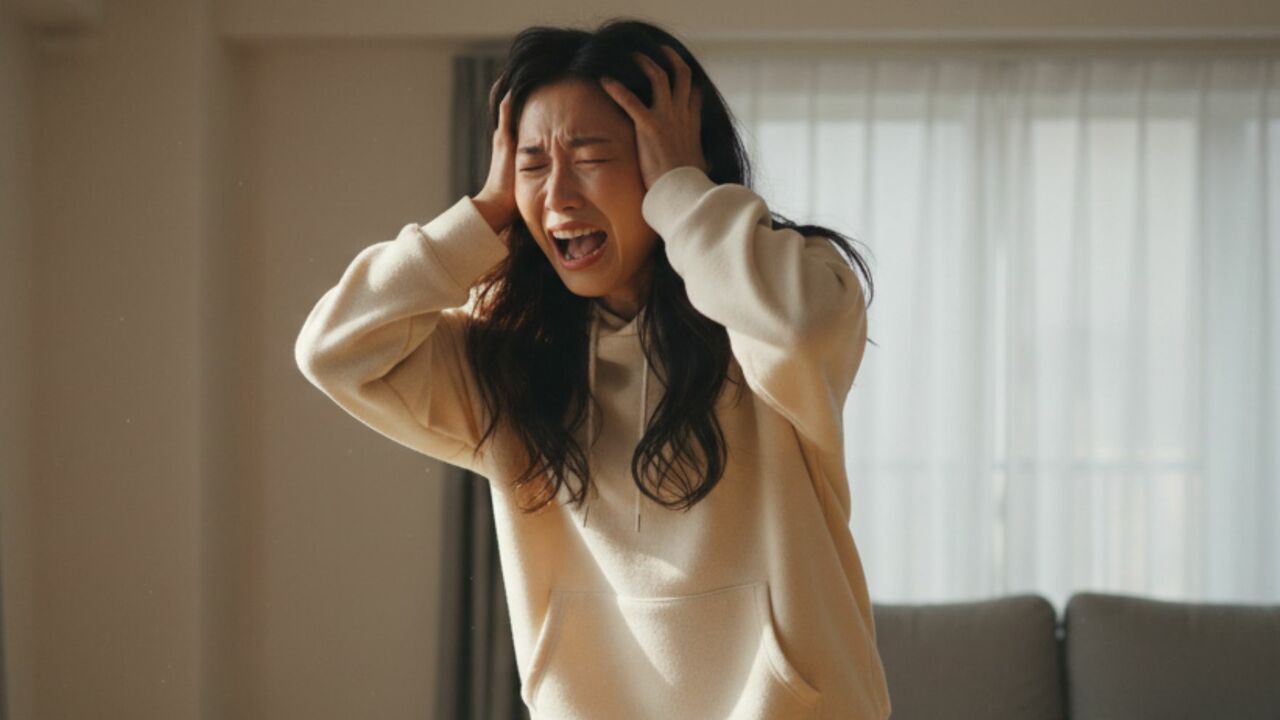神様の答えはまた短かった。そして、少しおいて、言葉を継ぎ足した。
「君はさっきから、この光景を俳句に詠もうとしているようだが、できそうかね」
「難しくて、私にはできません」
「難しく考えず見たまま詠めばよい。まず上五で手毬唄を提示し、中七はどうする」
「『手を動かして』ですか」
「俳句は一人称だから、何も言わないと句を作った君自身の行為とされるだろう。この場合には、主人公を明示する必要があるね。中七は『婆手を上下』としてみよう。さあ、下五はどうする」
「思い浮かびません」
「『毬なくも』はどうか。『手毬唄婆手を上下毬なくも』となる。上五で手毬唄が聞こえ、その方へ目を向けると、老婆が手毬をしている。子供ではなく老婆だ。興味を惹かれて、老婆の手元を見やるが、あるはずの毬がない。その意外性にまず打たれるが、やがて頭のねじが緩んだ老婆が、昔を思い出して幻の毬を打っているのだと気づく。老婆を写生したのだが、季語の手毬唄のなつかしさと下五の意外な味付けで、ちょっと面白い句になったようだ」
神様は優しい微笑みを見せて姿を消した。私は大急ぎで、俳人アルバムをめくった。なんと、今回神様が姿を借りた痩身の老人は、松本たかしだった。
今回の神様は、能の名門宝生流の御曹子に生まれ、病で能を断念した方だった。そのような方に、砧などと能の演目の話をとうとうと語ってしまったのだ。主人に追われ、両手を額に当てて逃げ惑う狂言の太郎冠者に私がなったような、惨めな気分だった。
講義では、理詰めで俳句を構築していく過程を学んだ。また、同じものを見ても、より詩的に捉え表現することが大切だということも教わった。
手毬唄婆手を上下毬なくも
チチポポと鼓打たうよ花月夜 松本たかし