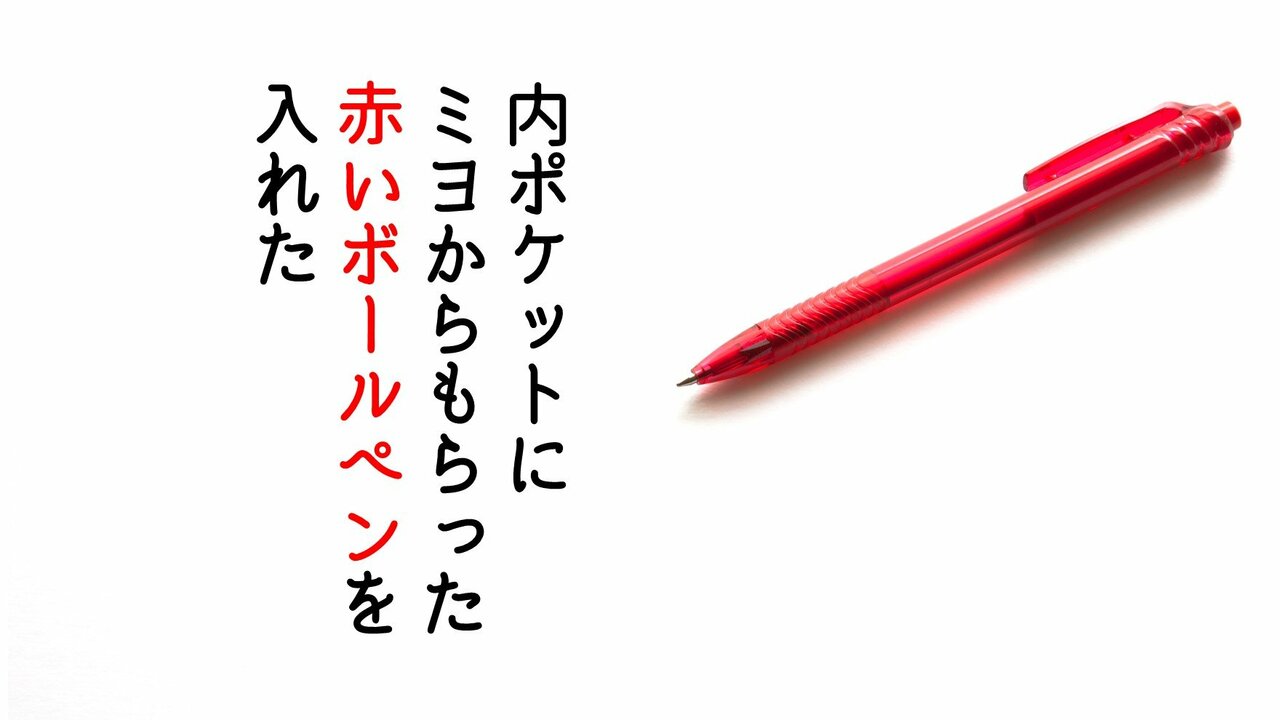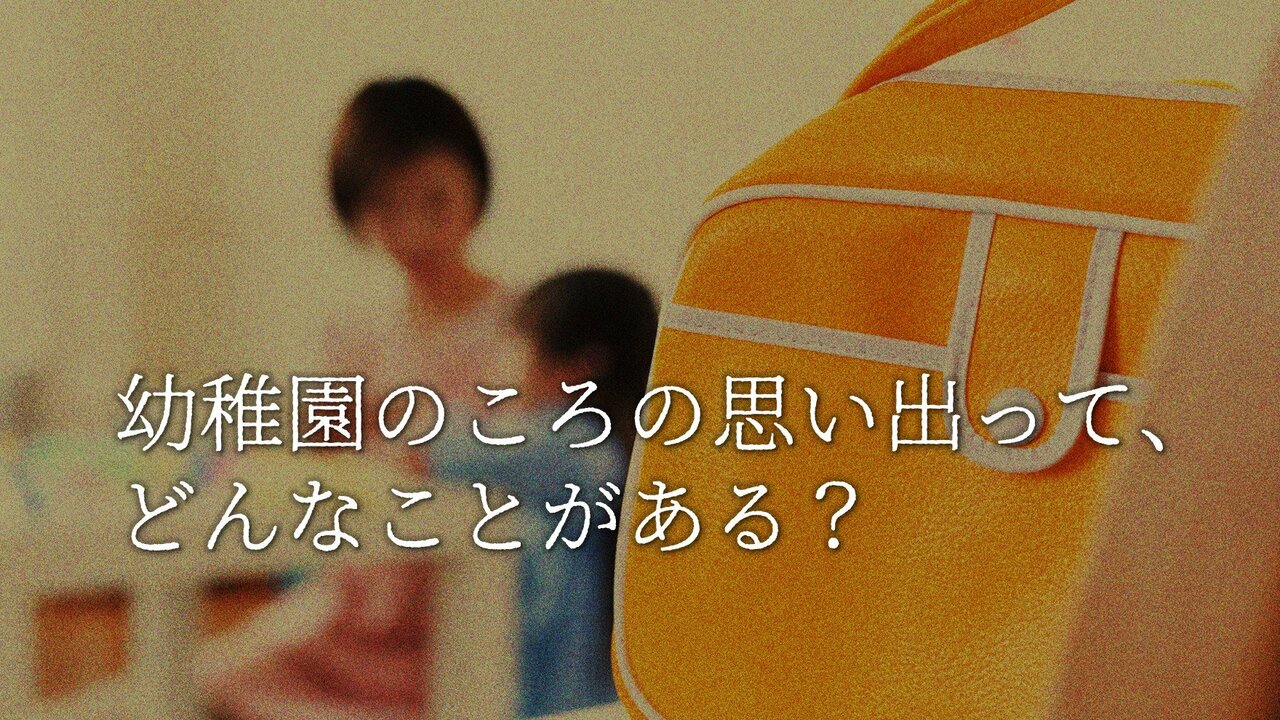第一章 赤い光
三日後、無事に退院したものの何をするわけでもなく、達也は部屋で問題集をぼんやりと眺めていた。塾でのことや今まで抱いていた不満など、達也はすべて両親に打ち明けた。
母は達也の山田学院の退会手続きを済ませたが、八月中旬の、受験生にとって一番大事なこの時期の退会には不安が残った。しかし、退院したばかりの達也に「勉強しろ」とはさすがに言えない。
何度目かのため息をつきながら、リビングで何気なく朝刊を開くと、思わず手が止まった。間違いない。折込みチラシには、達也を救った男性が載っていた。銀色のメガネをかけ、スーツ姿だ。桜華(おうか)進学塾。男性はどうやら塾の講師らしい。最寄りの駅は今までと同じ松本駅だ。
母は、食い入るようにチラシを見続ける。お城口から徒歩五分。山田学院とは反対側の市街地だ。駅が同じなら、息子も通塾しやすいかもしれない。でも帰りにまた悪い奴らにからまれたりしないだろうか。
しばらく悩んだものの、心を決めてチラシを持つと達也の部屋へ向かった。そして、夏休みもあと二週間で終わりというこの時期に達也の転塾が決まったのだった。
九月になり、新学期が始まった。学校から直接、桜華進学塾へ行った達也だったが、一人教室で苛立っていた。通いはじめたばかりの慣れない進学塾での授業。全く解けない問題。休憩時間を惜しんで問題集に目を通すクラスメイト。
同じ中学校の生徒はおらず、互いに無関心の様子で誰一人として話をする者もいない。息の詰まるようなこの雰囲気も、達也をイライラさせるのだ。いくら受験生とはいえ、よく授業が終わってすぐ問題を解こうという気になるなと思ってしまう。
期待を胸にここへ来たものの、やる気をだしては解けない問題にぶつかるの繰り返しだ。文字を綴(つづ)るシャーペンの音が耳に入ってくる。みんな優等生なんだろうな……。
やがてチャイムが鳴り、男性講師が教室に入ってきた。春口努(はるぐちつとむ)、先月のあの暴行事件で達也を救ってくれた人だ。
「今日も全員来てるな、よし」
数学担当で、このクラスの担任でもある。四十代半ばだろうか。春口はスーツ姿で落ち着いた雰囲気があるが、銀色のフレームからのぞく目は時折、どこか寂しげだ。昨年度は多くの生徒を次々と難関高校へ合格させ、桜華進学塾講師歴代一位という実績を残した。
わかりやすい授業と生徒一人ひとりへの手厚い進路指導で、今年度も多くの受験生たちに信頼されている。
「授業を始める前に、先日、君たちに受けてもらった模擬試験の成績表を渡す。名前を呼ばれたら取りに来るように」