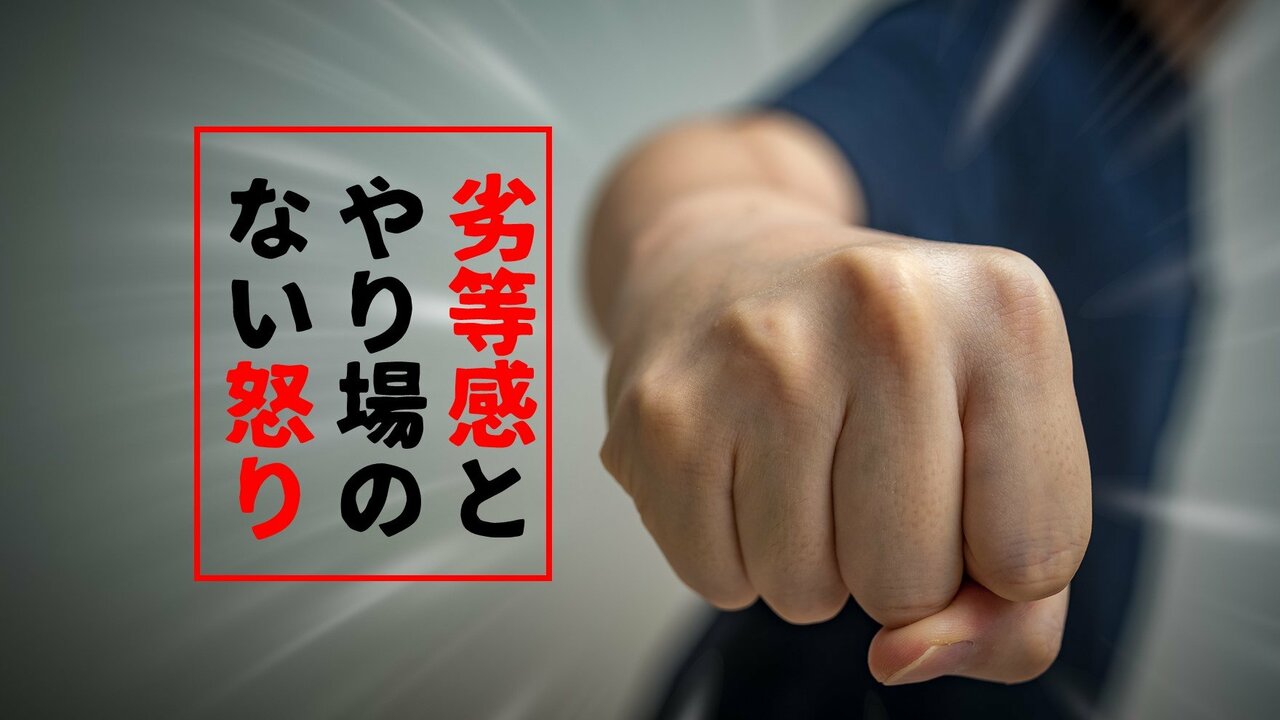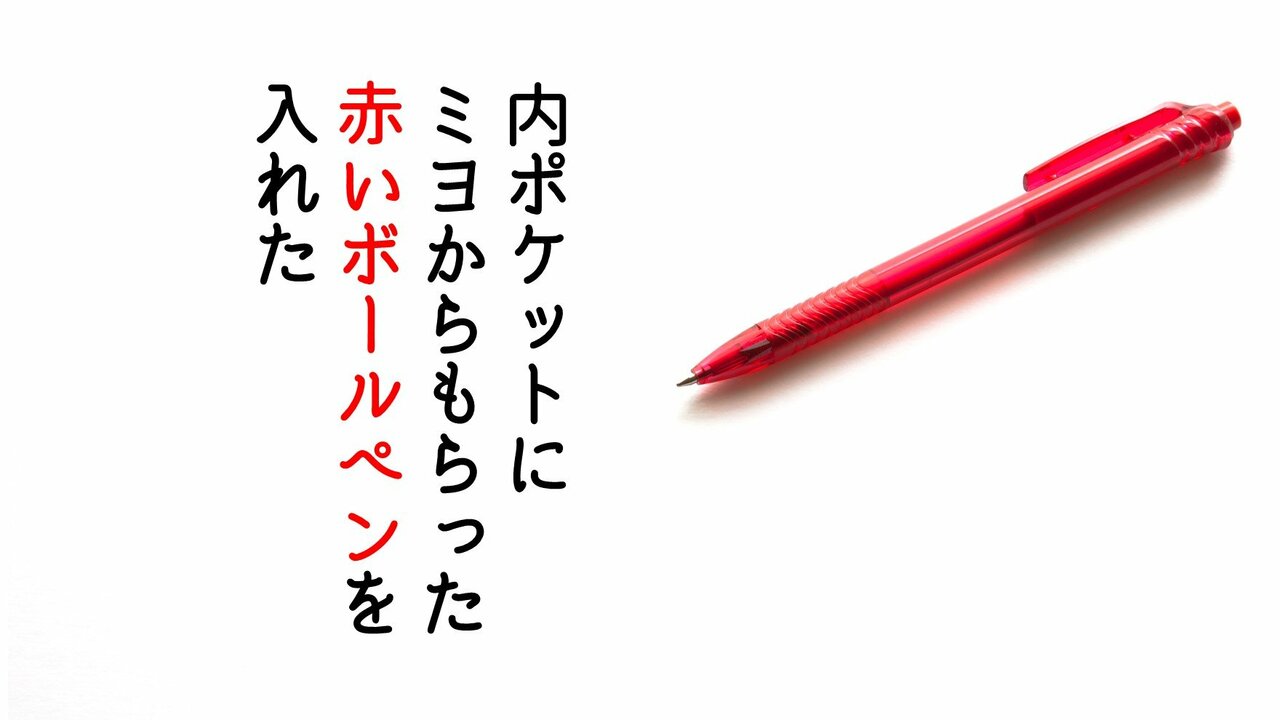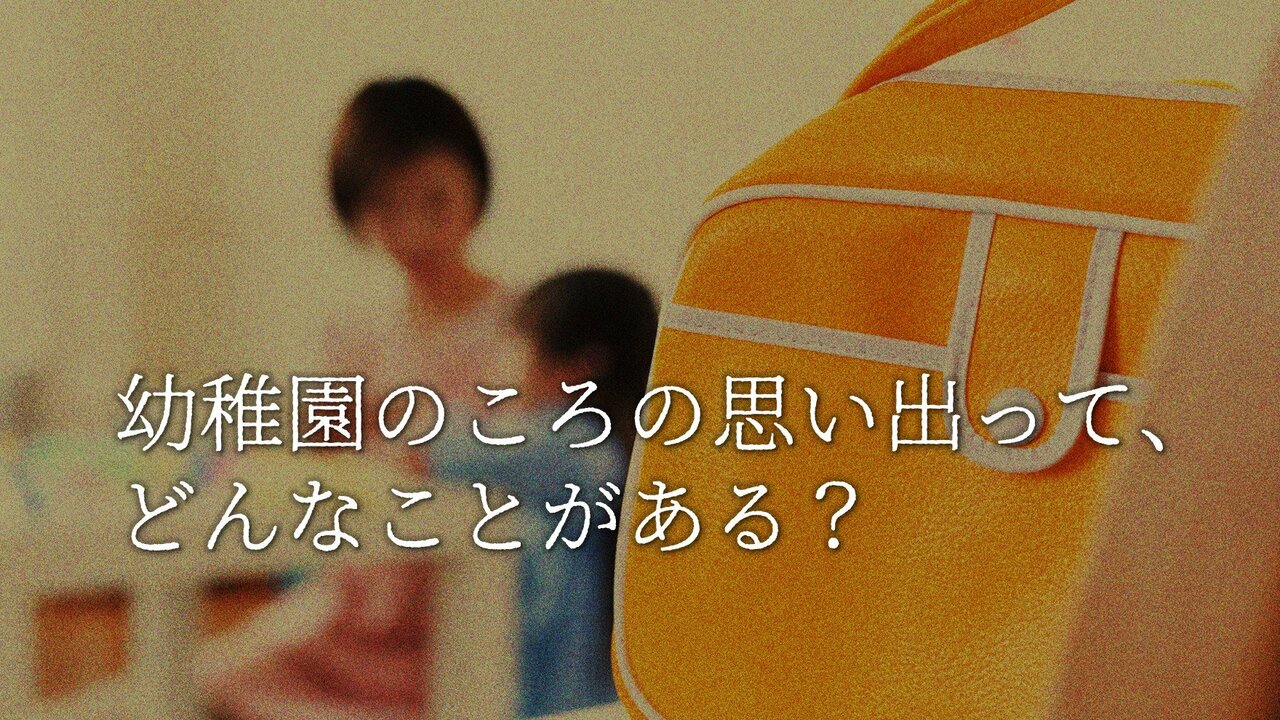プロローグ
小さなピンク色の花束を片手に、「あの場所」へと向かう。日中の曇り空を経て日はすっかり落ちた。家路(いえじ)を急ぐ人が行き交い、商店街はホワイトデーに向けて賑わいを見せている。学生時代とさほど変わらぬ街―。
「カレシに渡されるトコ想像してたでしょ」
「そんなんじゃないよお」
「いいなあ、ウチもカレシ欲しい」
学校帰りの女子高生たちを横目で見ながら、気づくと横断歩道の手前まで歩いていた。信号は赤。この先が駅だ。
ロータリーと駅に挟まれたこの道路は、普段、車の通りはほとんどない。道路幅は三メートルほどだ。
車が来ないことを確認すると、赤信号を無視してさっと渡り駅の改札へと急ぐ人が多い。信号が青に変わる。駅へと向かう人々から離れ独りロータリーへと進む。
三十秒ほど歩いただろうか。バスに乗りこむと最後部の座席に腰かける。走りはじめたバスの車窓から切り取られた風景に記憶を重ねていく。
バスに揺られること十分。バスを降りてバス停近くの石段を登る。白い吐息が石段に消えていく。ようやく登りきると、錆さびた裏門があった。誰もいないグラウンドが目の前に広がる。
十五年ぶりの「あの場所」だ。いつかはもう一度、ここへ戻るような気がしていた。記憶の時計が徐々に回りはじめる。
胸の高鳴りと忘れられぬ痛みが沈黙を刻む。どれほどの祈りを捧げただろう、そして、どれほどの不安を覚え、どれほどの永遠を願っただろう……。スーツの内ポケットに手を伸ばし、かじかむ右手で一本の赤いボールペンを取り出す。
剝(は)がれかけの赤いラベルがペンの中央にあるだけの、透明のプラスチック製のそのペンは、あるはずの滑り止めのゴムもなくインクも入っていない。もはやボールペンとしての機能を果たすことのない「モノ」を眺めながら、冷たい風を背に佇む。
ふと頬に冷たいものがあたる。白く輝くものがひらひらと舞い落ちてきたことに気づく。粉雪だ。そっと腕を伸ばすと、落ちてきた雪はすうっと手のひらに溶けていった。
第一章 赤い光
青い空に入道雲が浮かぶ。蝉(せみ)の鳴き声が園児たちの声と重なり、響き合っている。園庭を駆け回る園児たちから離れ、男の子は流れる雲をぼんやりと見ていた。
やがてヒグラシが夕刻を告げ、迎えに来た母親に連れられて、園児たちは一人、また一人と家へ帰っていく。迎えを待つ間、男の子はやわらかな風を身に受けながらシャボンの泡を弾かせた。勢いよく息を吹いてみる。だが、思い通りの玉にはならず、液は腕を伝い地面にこぼれる。足元に染みこむ液体を見つめると、なんだか心までしぼんでいくようだった。
「ねえねえ、ちょっと貸してみて」
黒髪の女の子が得意顔で手を伸ばした。やわらかそうなまるい頬(ほお)。男の子が容器を手渡すと、女の子はいとも簡単にシャボン玉を作ってみせた。
「ストローをね、こうやって横に向けて、そーっとそーっと息を吹くんだよ。ねえ、やってみて」
男の子が強張(こわば)る表情で慎重に息を吹くと、小さなシャボン玉が舞いあがった。男の子は夢中で追いかけ、キラキラと輝く虹色の玉に手を伸ばそうとした瞬間、シャボン玉は音もなく弾け散った。
「たつや……」
遠くから呼ぶ声が聞こえる。ようやく迎えに来てくれたのだろうか。
「たつやったら……」
声がだんだん近づいてくる。
「……起きなさい。達也(たつや)! 起きなさいったら!」
「うわ! かあ……さん?」
斉藤(さいとう)達也の目の前には、腕を組んだ母の姿があった。達也はゆっくりと華奢(きやしや)な体を起こし、眠たい目をこする。
「呑気(のんき)なものね。いつまで寝ているつもりなのかしら?」
トゲのある言葉。達也はゴクリと唾(つば)を飲みこむ。
「そうやっていつまでもだらしがないからダメなのよ、あなたは。少しはお兄ちゃんを見習いなさい。宿題は終わっているのよね、もちろん」
またか。また、「お兄ちゃん」か。床に落ちたテキストをにらむ。劣等感とやり場のない怒りをずっと我慢し続けてきた達也は、いつからか下唇を噛む痛みさえも感じなくなっていた。
「聞いているの? わかったら早く支度して行きなさい、塾」
夕食の準備の途中だったのか、エプロン姿の母は冷たい言葉を残し部屋をあとにした。ショートレイヤーの髪を指でいじりながら時計に目をやると、六時を指している。
「だりぃな、塾」
中学三年の達也には、夏休みなどない。高校受験を控えて塾通いの毎日だ。制服に着替えると、重い体をひきずるようにして部屋をでた。
「気をつけて行きなさい。寄り道せずに早く帰ってくるのよ」
台所から母の声が聞こえる。それには答えず、達也は外にでると自転車に乗って穂高(ほたか)駅へと向かった。