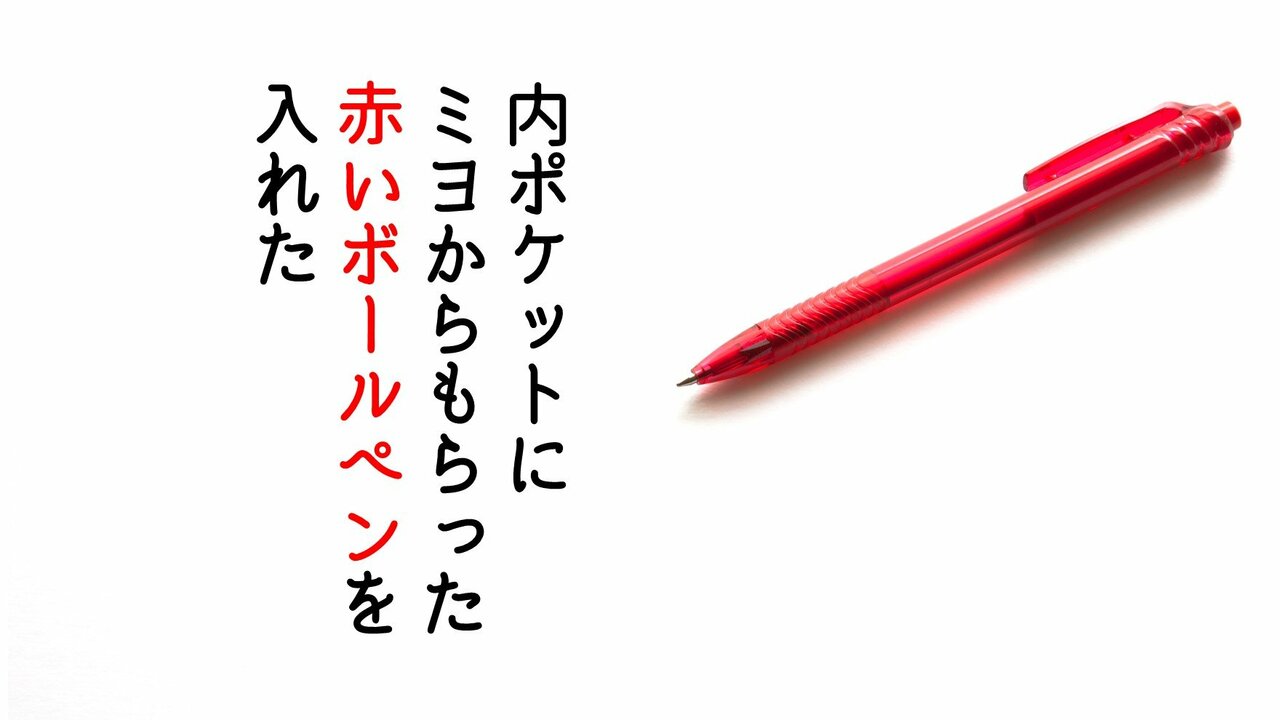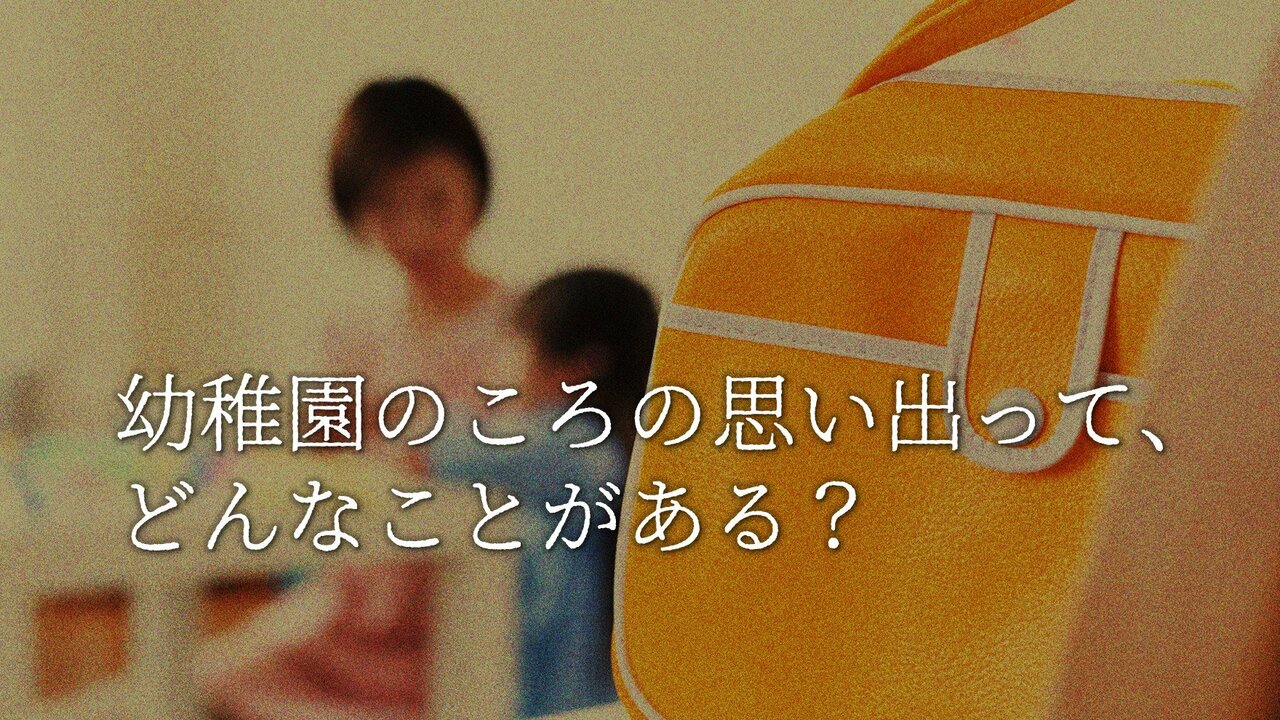第一章 赤い光
昨年の四月、達也が中学二年生に進級した時に、父の仕事の関係でそれまで住んでいた東京を離れ、この街に引っ越してきた。五歳年上の兄は大学二年生で、医学部に通うため都内で一人暮らしをしている。小さいころから優秀で、大学にも次々と合格していた。
「お兄ちゃんはできたのに」
家族のそんな言葉に、達也は少しずつやる気を失った。いよいよ受験となった今でもモチベーションは上がらない。部活をやっていた時はまだストレスを発散できたが、引退後の今ではどうしようもなく、モヤモヤした晴れない気分だけが募るばかりだった。
引っ越してすぐに通いはじめた進学塾の山田学院(やまだがくいん)での勉強は、達也にとって苦痛以外の何ものでもない。それでもなんとか認めてほしくて、こうして塾に通っているのだ。
穂高駅から大糸線に揺られて、十駅先の松本駅に着いた。六時五十五分。あと五分で授業が始まる。いつもは教室へと走っていくが、どうしても塾へ行く気持ちになれない。
「やっぱり、だりぃな」
改札をでて右手に続く閑静な道を三分ほど歩くと山田学院。左手は賑やかな市街地へと続く道だ。将来何かの役に立つらしい、受験勉強という名の漠然とした未来に向かう苦痛より、今を存分に楽しめばいいじゃないか。その代償としていい高校へ行けなくなったとしても、なんだかんだで生きていくことはできるだろう。どうせ最期はみんな空へと旅立ち、そして逝くのだ。
家路を急ぐ大人たちが改札の奥へと消えていく。ありとあらゆる雑音が耳に入っては通りぬけていく。僕の存在など、誰も気にせずに過ぎ去っていく。達也は浮かぬ心を振り払うように山田学院へと急いだ。
達也が教室に着くと、数学講師の藤多(ふじた)がすでに授業を始めていた。生徒たちは黙々と問題に取り組んでいる。二、三分遅れて入った達也に、藤多はいかにも迷惑そうな目を向ける。生徒たちも達也を横目でチラリと確認しただけでまた問題に取りかかった。
「お、遅くなりました」
藤多はアゴで「早く席に着け」とうながす。達也は席へ着いたものの、気が重いままだ。今日も自分だけが正解をだせない授業が進められていくのだろう。先生が実績をだすために必死になるのはわかる。できない僕だけが邪魔者なのもわかっている。だけど……。
「では、次の問題は斉藤、解いてみろ」
藤多に指され答えようとするが、今日もまた答えられず黙りこんでしまう。藤多は薄ら笑いを浮かべている。達也の闘争心が湧きあがるが、考えれば考えるほど頭の中は真っ白になるだけだ。
急いでノートを見返し、前回までの内容を確認する。雑な字で書かれたノート。こんな時だけはていねいに書いておけばよかったと後悔する。右側に座る男子生徒の貧乏揺すりが気持ちをせきたてる。左側に座る女子生徒のボールペンをノックするカチカチという音が確実に時を刻んでいく。