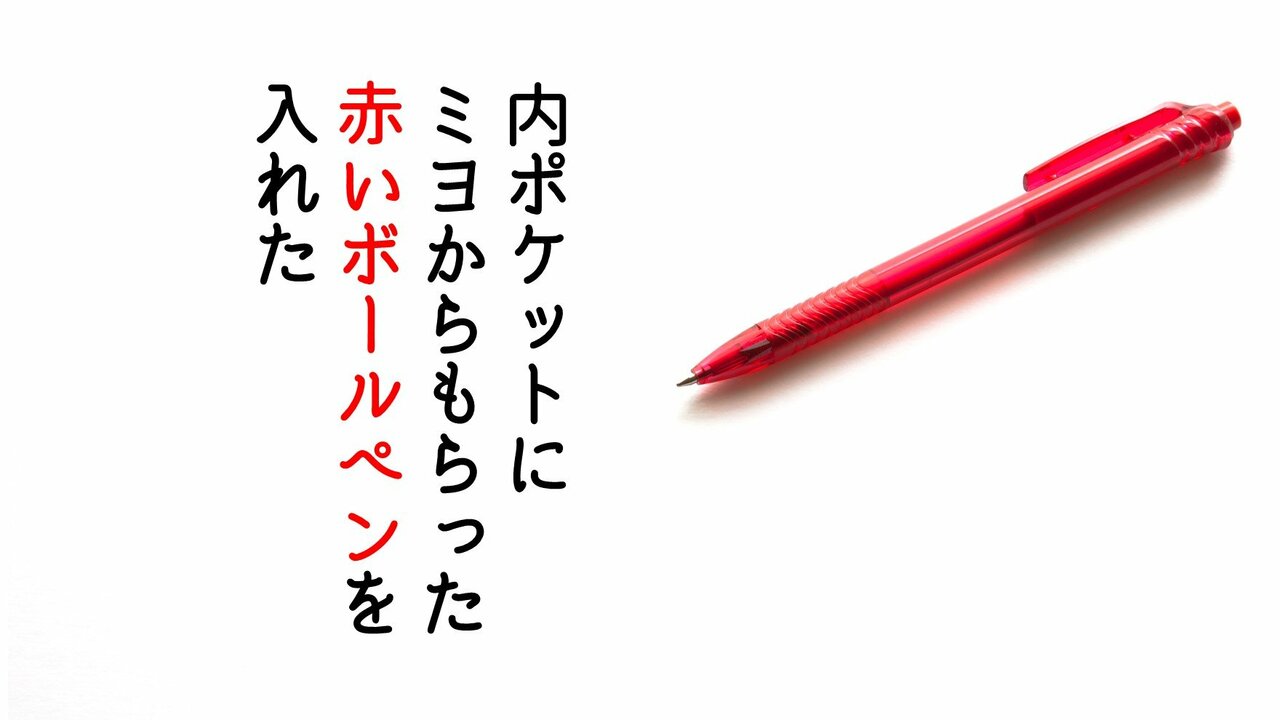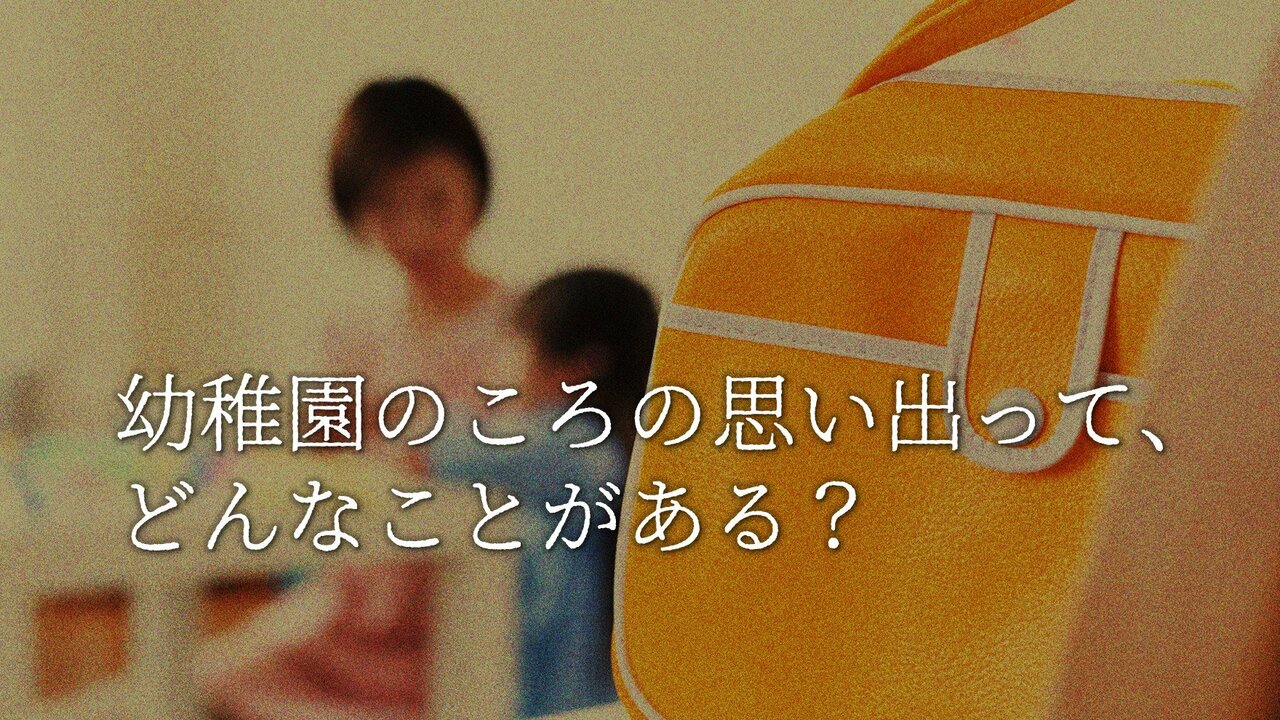第一章 赤い光
ノートを見返しても答えがわからない。今度は塾のテキストを開く。自分の必死さは周
りのみんなからはもたもたしているように見えるのだろうか。あちこちからため息が聞こ
える。耐えられず目をつむりかけるが、藤多が左手人差し指で教卓をトントンと叩き、無
言で正解を迫ってくる。ジトッとした嫌な汗が手の内側から滲みでる。
「あ、あの、僕」
はっきりしない言葉に、前の席に座る男子生徒が達也を振り返りメガネ越しににらんで
きた。一、二秒ではあったものの、ふいに襲われた新たな緊張に背筋がピンと伸びる。
黒板の上にかけられた時計が目に入る。授業が始まって一時間が過ぎようとしていた。
のみこんだ言葉が酸味をおびて、喉元を逆流してくるのを感じる。もう限界だ。達也は勢
いよく立ちあがった。
「どうした?」
「気分が悪いので、早退します」
「そうか。気をつけてな」
藤多は達也を見ようともしない。達也は逃げるように教室をでると、駅へと走った。
視界がにじむたびに、爪が食いこんだ握り拳で目元をぬぐった。
道端に捨てられて踏みつぶされたであろう缶ビールの空き缶。
灰色のコンクリート床に吐き捨てられてへばりついた、真っ黒に変色したガム。
駅までの道中、すでに不要になったゴミばかりが目に留まった。
駅に着いた達也の足が止まる。怒りと呼吸が落ち着きはじめると、惨めな自分が急に悲
しくなってきた。
駅構内の時計は七時四十二分。塾の授業が終わる九時まではまだ時間が早すぎる。
家にはまだ帰れない。いや、帰る気がしない。
どうせ家に帰ったところで、馬鹿にされないように勉強しろと言われるだけだ。
しばらくうつむいた達也は、山田学院とは反対の市街地へと歩きはじめた。
達也はデパートの七階にいた。CDショップと本屋がメインのフロアだ。CDショップ
で好きなバンドのCDをいくつか眺め、本屋へ向かった。
ため息を繰り返しあれこれと物色するうちに、アダルトコーナーの前に来ていた。キョ
ロキョロと辺りを確認してしまう。買い物を済ませようと足早に行き来する主婦たちの目、
仕事帰りに雑誌を立ち読みするサラリーマンの目、レジで客を応対する店員の目。見られ
ているわけではないのに、そこに足を踏み入れようとすると、ジロリと視線を向けられる
気がしてその足を止めてしまう。
ドクン。
後ろめたい気持ちを表にださぬように努めるが、自然に見せようとすればするほど、か
えって不自然さが際立つようだ。扉の前をソワソワと行き来するうちに、徐々に興味の先
へと引きずりこまれていく。
ドクン、ドクン。
高鳴る心臓の音を耳の奥に聞きながら中に入ると、刺激が強い本がズラリと並んでいる。
達也は財布に手を伸ばす。
「三百円しかない」
表紙で微笑む女性。その艶 なま めかしさに、達也は欲望を抑えられなかった。
ドクン、ドクン、ドクン。
一冊手に取ったまま、アダルトコーナーをでて、辺りを確認する。
達也は意を決してレジではなく階段付近のトイレへと向かった。そして中へ入ろうとしたその時だった。
「待て!」
達也の左手はごつい手に握られていた。
「そんなトコに持って行ってどうするつもりだ!」
がっしりとした体の中年男性が声を荒らげている。デパート内を巡回中の私服警官だ。
「こっちへ来い!」
左手をグイと引っ張られ、達也は近くの交番へ連れていかれた。