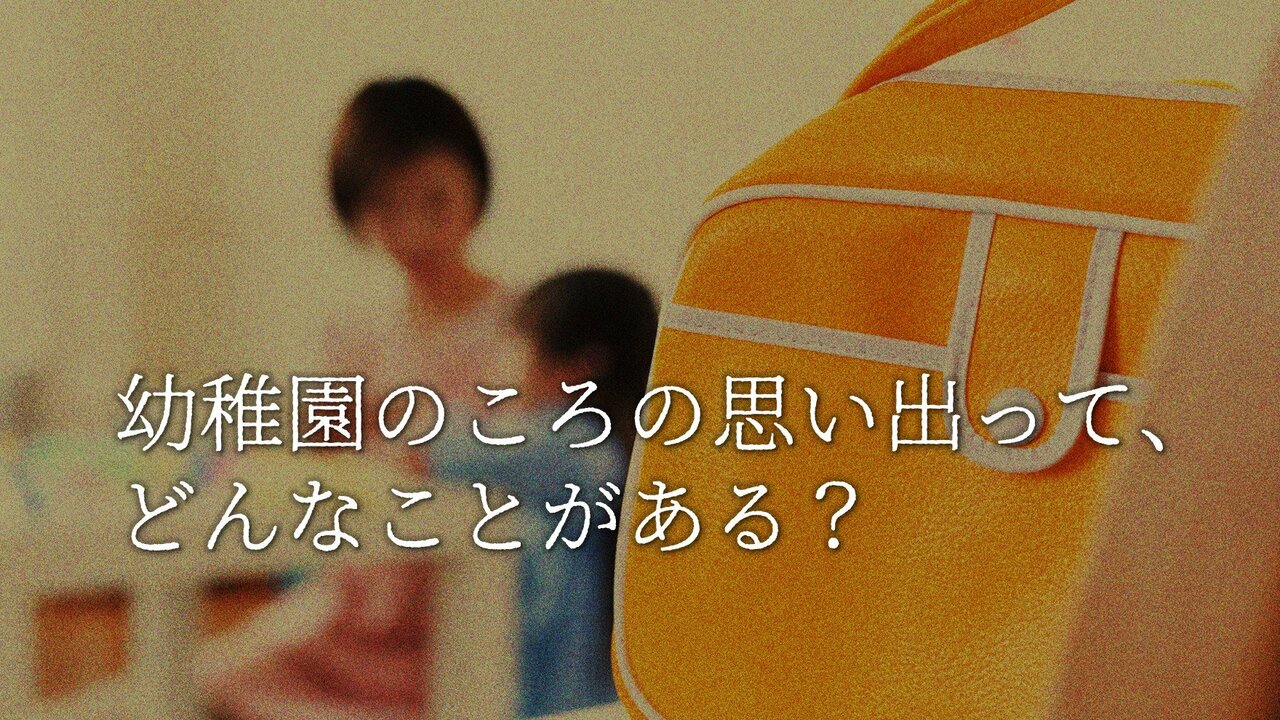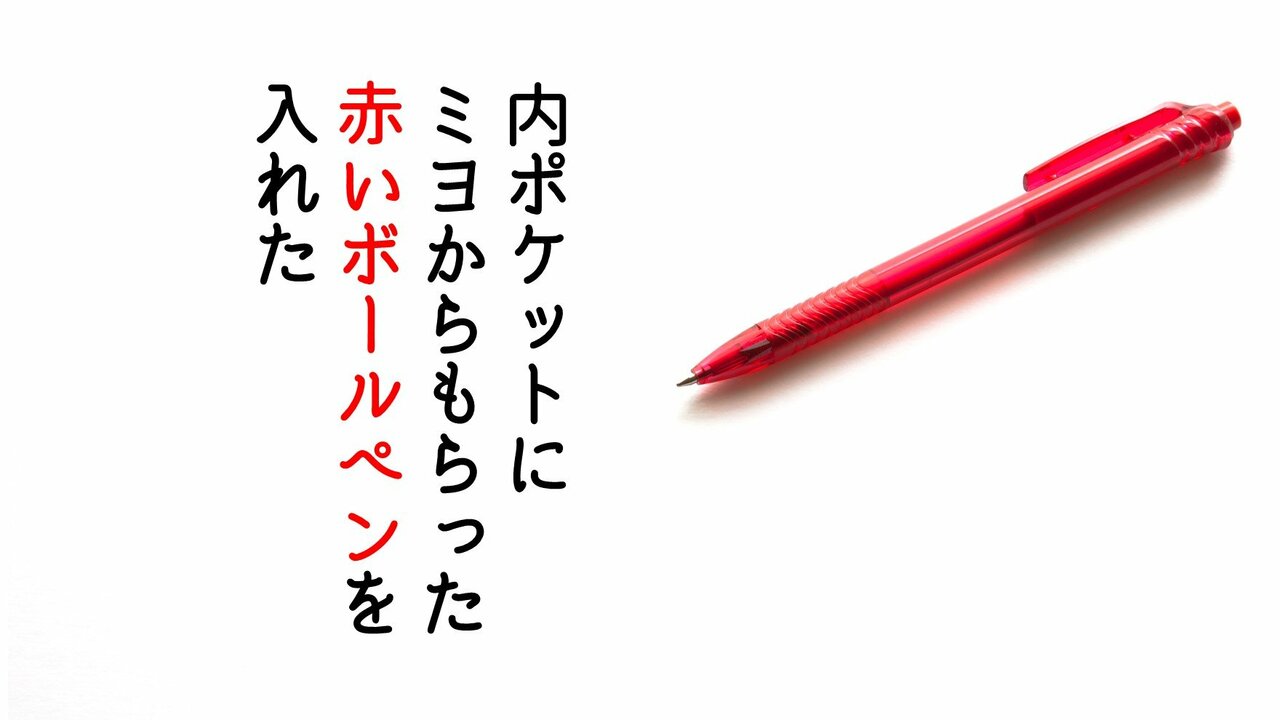第三章 運命の人
十五分ほど待ってバスに乗り、信州中央病院へと向かった。乗客は最後部座席に座る二人だけだ。
走るバスの中、ミヨが息を両手に吹きかけた。
「とても寒かったわね」
「本当ですね」
ミヨは首に巻いていた赤いマフラーに顔を埋め、達也はミヨの左肩から垂れたマフラーに目をとめた。
(あれ? これって)
「MIYO.H」と刺繍(ししゅう)がある。達也の視線に気づいたミヨが目を合わせた。
「あ、いや、別に。あったかそうなマフラーだなって」
「私のお気に入りなの」
ミヨは埋めた顔をだした。
「昔、サンタさんにお願いしてもらったものなの。幼稚園のころだったわ。その時からずっと大切にしてるの」
「宝物なんですね。でもどうしてイニシャルがHなんですか? 神崎ならKのはずじゃ」
ミヨは再びマフラーの中に顔を深く埋めた。
途切れた会話にエンジン音が響く。達也は軽率な言葉であったかもしれないと後悔した。先ほどまで全然気にならなかったバスの横揺れが大きく感じられる。
「ねえ、達也くん。幼稚園のころの思い出って、どんなことがある?」
「幼稚園のころですか? そうだな。あまり、周りの友だちに馴染めなかった記憶しか……だけど僕のことをいつも気にかけてくれた人がいた気がする」
「気にかけていた人?」
埋めた顔をマフラーからだして、ミヨが聞き返した。
「でも、名前が思いだせない。いつもいっしょに遊んでくれたんだ。その人といるとなんか……すごく安心するというか……うまく言えないんですけど」
「写真残ってないの?」
珍しくミヨが執拗に聞いてくる。
「家に帰ればあるとは思うけど、どうかな。そんな古い写真」
ミヨはのぞきこむような目をした。
「もしかして達也くんの初恋だったのかな?」
「そうかもしれないですね。今、どこで何をしてるのかな、その人」
心なしかうつむき加減のミヨがポツリとつぶやいた。
「そろそろ病院ね」
到着すると、達也はエントランスまでミヨを送った。明かりはついているものの、誰もいない。
「今日はとても楽しかったです」
達也の言葉にミヨがゆっくりとうなずく。壁にかかった時計の秒針が、見つめ合う二人の沈黙を刻む。胸の高鳴りと重なっていくようだ。
達也がミヨとの距離を一歩縮める。心臓の鼓動が耳の奥で鳴っている。
胸に両手をあて、頬を赤らめ視線を泳がすミヨ。達也はさらに一歩、縮める。
口の中が乾いていくのがわかる。両手の震えを抑えながら、達也はミヨの肩に両手を添える。ミヨは目をつむり身を縮めた。普段、感情をあまり表にださないミヨだけに、恥じらう気持ちがはっきりと伝わる。
ミヨは瞳を閉じたままだ。達也が意を決して唇を重ねようとしたその時。
「神崎さあん?」
二人のもとへ一人の中年の看護師が足音を一切立てずに現れた。突然の声に二人はあわてて距離をとった。
「遅かったわね。なかなか戻らないから心配して待ってたのよ」
ミヨが無言で頭を下げている。
気のせいだろうか。周囲の気温が下がったように感じられる。鳥肌が立ってきた。
「君は? 神崎さんのお知り合い? もう遅いから、お家の人、心配するわよ」
達也はふてくされ気味に頭を下げた。
「じゃあ、神崎さん。病室へ」
ミヨがゆっくりとうなずく。
ミヨは何度も達也の方を振り返り手を振りながら、看護師とともに病室へと去っていった。
達也はその日の晩、公園で漏らしたミヨの最後の言葉を何度も思い出しては床(とこ)に就いた。