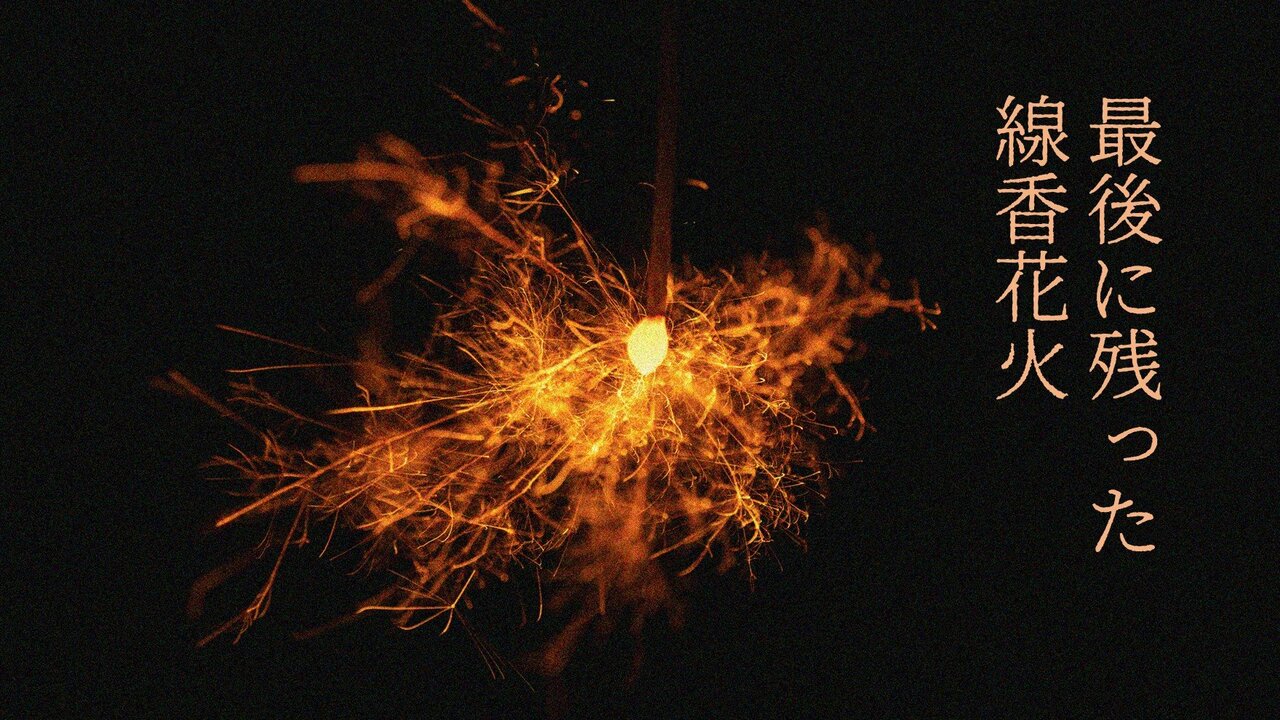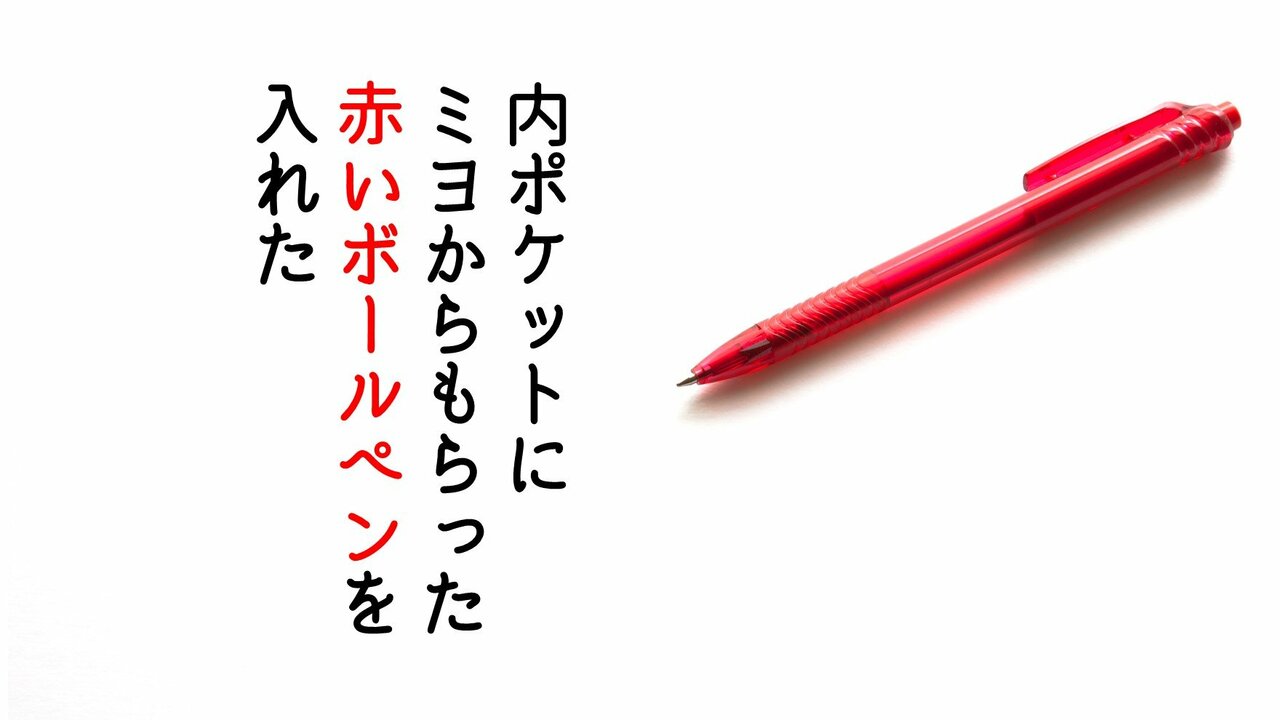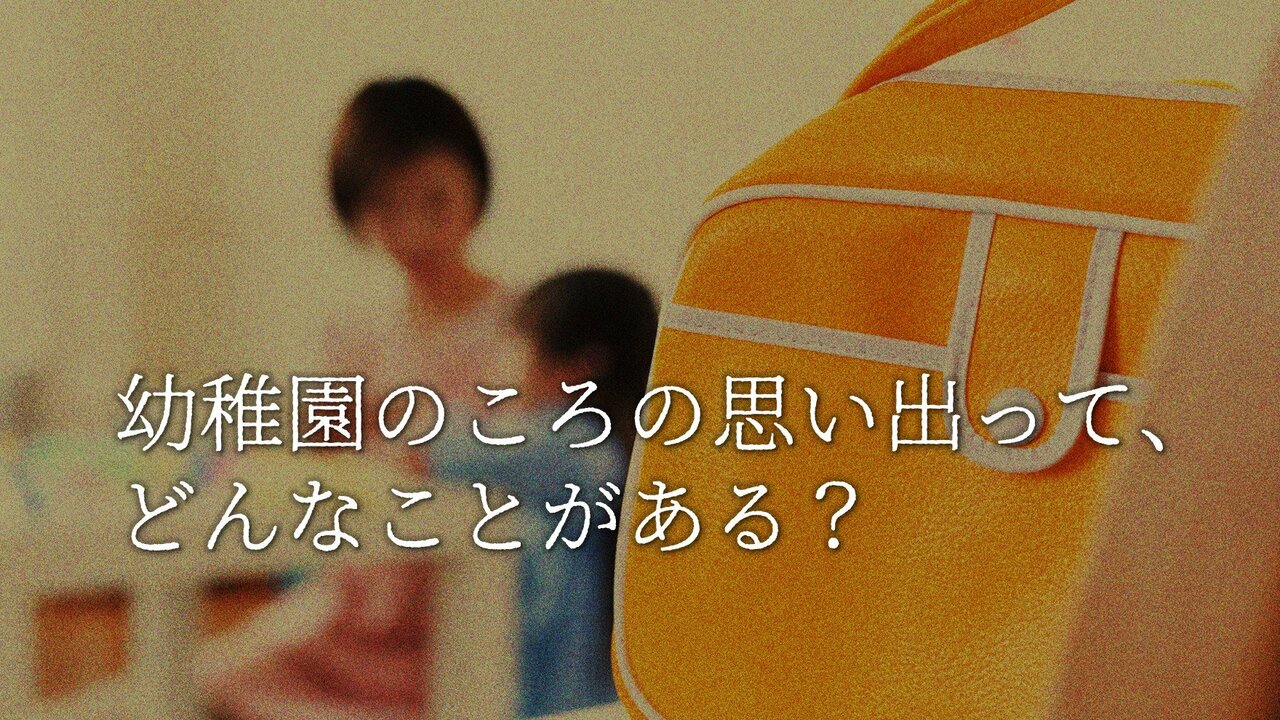第三章 運命の人
ミヨは達也をじっと見つめる。
「もし、二人とも合格したら……付き合うことになるのかしら」
「えっ? 僕と結花が? ないない」
冬空を見上げ笑う達也。ミヨは胸に手をあて視線を落としている。そんなミヨに気づくと達也は、今度は実花を真似てみせた。
「ああ、ひょっとしてミヨ先輩、妬いちゃってるとか?」
ミヨは達也に視線を戻した。
「達也くんを結花ちゃんにとられちゃったらどうしようって」
ミヨは無言のまま後ろを向き、スタスタと歩きはじめた。
「あ、ちょ、ちょっと待って先輩。冗談っすよ、冗談。待って、待って」
ミヨはどこかへ消えてしまいそうで、せきたてられるような胸騒ぎを抱えて、達也はミヨを追いかけた。
二人はしばらく境内を散策した。冬の日暮れは早く、夕刻には薄暗くなりはじめた。
「ミヨ先輩、神社の隣に小さい公園があるから、そこへ行ってみませんか? いい物を持ってきたんですよ」
徒歩で五、六分の所にある小さな公園までやってくると、木製のベンチに二人は腰をかけ、達也はバッグからビニール袋を取り出した。
「実はこれなんです。じゃん」
達也は得意気に花火を取り出した。
「やりません? 季節はずれだけど。先輩、花火大会に参加できなかったって言ってたから。喜んでくれるかなって」
達也の照れ笑いに応えるように、ミヨは微かに微笑んだ。
二人は真冬の花火を楽しんだ。美しい色彩に照らされ、ミヨが微笑んでいる。痩(や)せてしまったその顔に胸を痛める達也だったが、それでもミヨをずっと感じていたかった。
ミヨがうっとりとしている。本当に喜んでくれているようだ。
最後に残った線香花火を手に取ったミヨはつぶやいた。
「花火、最後だね。これで」
二人は一本の線香花火を見つめた。冷たい風が吹きぬける。ミヨの肩が震えている。すっかり遅くなった。そろそろ病院に戻らなくてはならない時間だ。
ミヨがゆっくりと最後の線香花火に点火した。
「やめて」とミヨを制する言葉が思わず口からついてでそうになる。
松葉のような光を見つめるミヨの瞳が潤んでいるのがわかる。
「ずっといっしょにいたい」という気持ちも、この花火が終われば叶わぬ願いとなる。それでもわずかな明かりの中、二人の時間を達也は想った。
こうこうと赤く光っていた灯がついにポトリと落ち、最後を迎えた。
「終わっちゃったわね」
ジンワリとその熱が土に奪われていく火薬を見つめ、ミヨがポツリとつぶやいた。
「私たちは、終わらないわよね……?」
「え?」
土に還ったことを見届けると、ミヨがまたポツリと言った。
「そろそろ帰りましょうか。さすがに冷えてきたわ」
二人は病院へと戻るため、近くのバス停へと向かった。