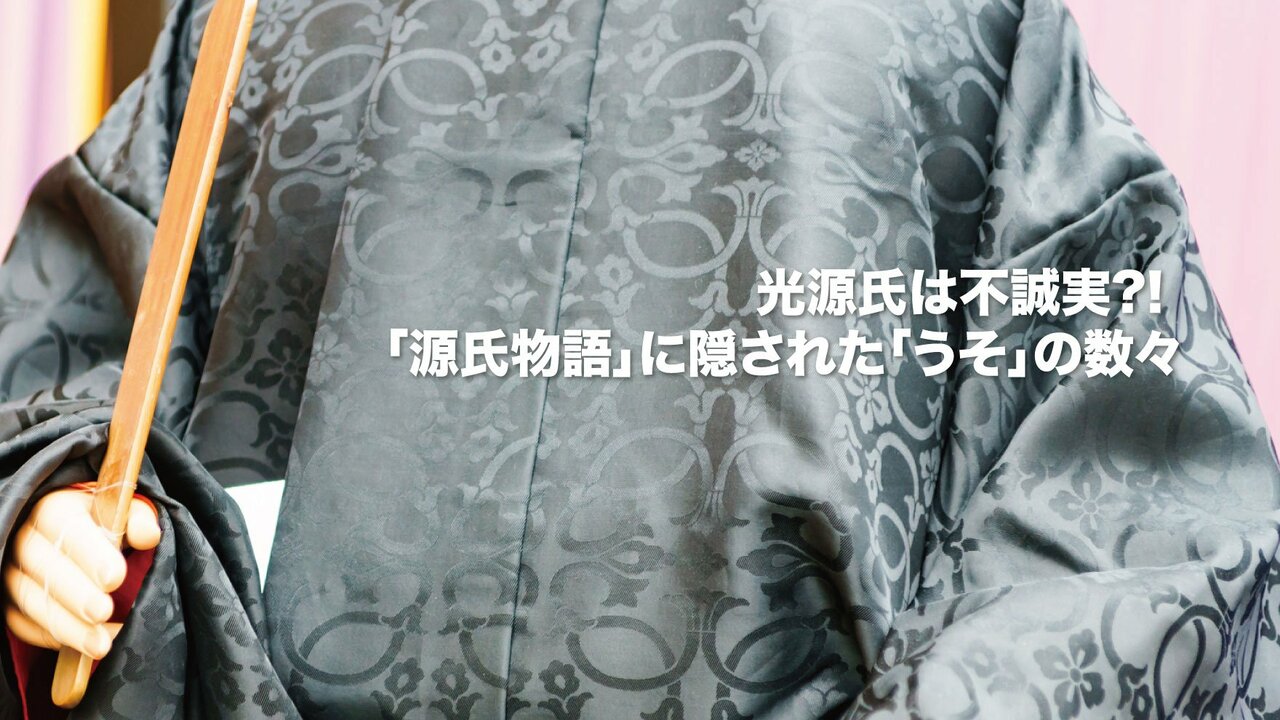うそ
『源氏物語』に「うそ」という言葉は見当たらない。しかし、『源氏物語』には、数多くの「うそ」が登場する。
新宿の朝日カルチャーセンターで行われていたカント哲学の講座で、中島義道先生が「私は三十年考えてきましたが、やはり『うそ』はいけないことですねえ」と言われるのを聞いた。その瞬間、私(睦子)は、『源氏物語』全編を光が突き抜け、目が覚めたように感じた。「うそ」が『源氏物語』を読み解くキー・ワードになる。そう直感した瞬間だった。
『源氏物語』の中で最大の「うそ」は、偽りの皇子が帝位に即いたことである。桐壺帝の皇子ではなく、光源氏と藤壺の間に生まれた子であるにもかかわらず、桐壺帝の皇子であると偽って東宮に立て、さらに冷泉帝として帝位に即くようにする。これ以上の「うそ」はないと言ってよい。
社会が安定し、爛熟してくると、既存の仕組みを自分に都合のよいように操作しようとする人々が現れる。それが時の権力者である場合には、これを阻止することは、極めて困難である。
桐壺帝は、亡き桐壺更衣の形代として宮中に迎えた藤壺が更衣の忘れ形見である光源氏の子を産むように、企まれた。藤壺と光源氏は帝に操られて、不義の子を得た。それが、偽りの皇子であり、後の冷泉帝である。
光源氏は、この成功体験によって、「うそ」によって生きていくことを学んだ。心にもないことを言って女性を口説くことは、光源氏の最も得意とするところであるが、それだけではない。
例えば、内大臣(もとの頭中将)のご落胤である玉鬘を探し当て、自分の子であると世間に吹聴して、男たちをおびき寄せる。「うそ」であることがいずれ露顕するに違いない「うそ」をついて、平然としている。しかも、玉鬘が内大臣の子であることを、切羽詰まるまで内大臣に明かそうとしない。
また、玉鬘の母君である夕顔がどのように亡くなったかについて、内大臣にも玉鬘にも、光源氏はついに語らない。成功体験によって、光源氏は、誠実さのない生き方をも身につけた。
光源氏の誠実さのなさは、冷泉帝との関係で明瞭に示される。自分の父親は光源氏であると夜居の僧からお聞きになった冷泉帝は、真相を確認したいと思って悩んでおられる。それを知りながら、光源氏は、冷泉帝に何も語ろうとしない。のみならず、冷泉帝から准太上天皇の地位を与えられて、栄華を誇っている。
このように、光源氏は、「うそ」と「誠実さのなさ」にまみれて生きた人物であると言っても過言ではない。「うそ」は、遅かれ早かれ、多くの場合、「うそ」であることが露顕する。
しかし、考えてみれば、「うそ」であることが決して露顕しない「うそ」がある。それは、「私は、こういう夢を見ました」と言う「うそ」である。それが「うそ」であるのか「まこと」であるのか、誰にもわからない。