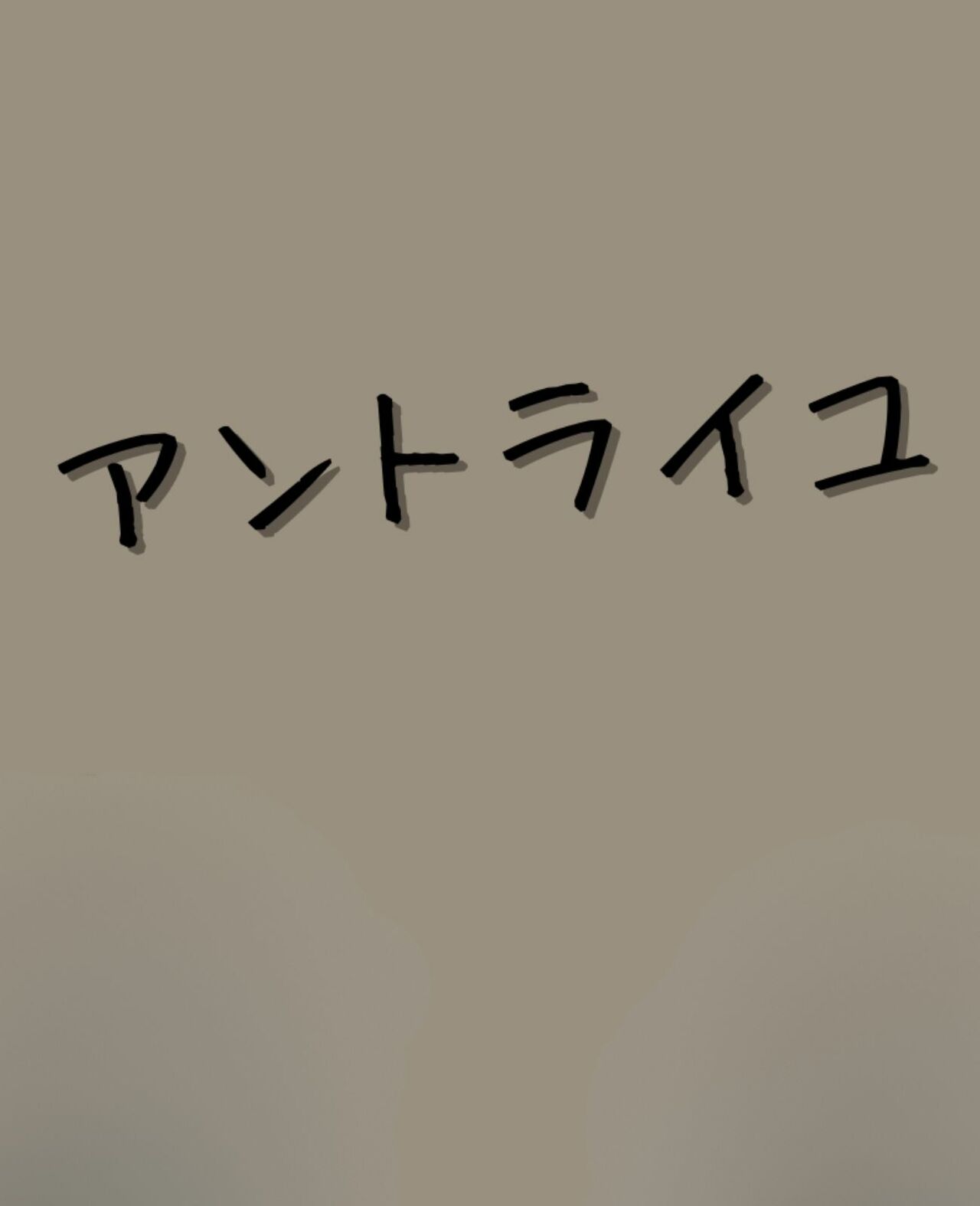【前回の記事を読む】折角着た服はゆっくり脱がされ、力無く床に落ち互いの瞳に溺れた――私たちは溶ける様にベッドに沈んだ
アントライユ
2
海の様に深い夢を見た。
確か中学生の頃の出来事。私も千春もまだ可愛げがあった。
親切にお年寄りに席を譲っていた小学生が、イヤホンをしながら見て見ぬフリをする高校生になって、ボランティアでゴミ拾いをしていた高校生が、道端に落ちている空き缶を拾わない大人になるのは簡単だ。
社会の洗練とは、心身共に疲弊させるものなのだ。道端のゴミを拾える人なんて、心に余裕がある人か、かなりの変人だろう。私たちには、ゴミを拾う勇気も気力もない。
目は開かないのに頭ばかりが冴えて、心地の悪さに毛布を被る。
上手く開かない瞼を必死に動かして目の端で捉えたのは、枕を背もたれにしてスマホを凝視する千春だった。珍しく目が冴えているようだ。いつもは私より遅く寝て、起きるのに。
私は昨夜の余韻に浸るように少しだけ彼に近づいた。Tシャツを軽く掴んでみる。すると私を見つめて髪を掬ってきた。そのままヘアクリップで止めるのを忘れた前髪を梳いて、こつんと額を小突いた。構ってくれたことが嬉しくて、彼の左腕に手を添えた。
「今日起きるの早いね」
「まあ。猫の動画見たかったし」
スマホをスワイプして流れてくる動画は、全て猫の鳴き声がした。ひとしきり見終わったのか、千春はスマホをロックした。
「出かけね?」
思い立ったら吉日と言わんばかりに千春はレンタカーを借りた。
私は、無断欠勤した。
久しぶりの車でソワソワしてしまう。引越しのバイトをしている千春は運転に慣れているのか、涼しい顔で車のエンジンをつけた。ハンドルを握る手は骨ばっていて、細いと言えど、男の人の手だと変に意識してしまい、不自然に体が揺れた。
「どこ行くの?」
「糸魚川」
「家帰るの?」
「帰る訳ないだろ。あんなとこ」
「そっか。っていうか車で行くの?」
「じゃあ電車乗り継いで行けば? かなり面倒くさいと思うけど」
「大人しく乗ってます」
千春と彼の剣幕に押されて萎びた私を乗せた車がゆっくりと発進した。